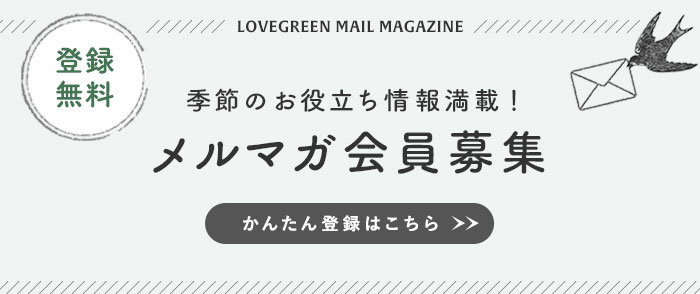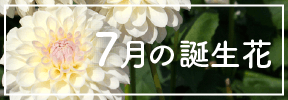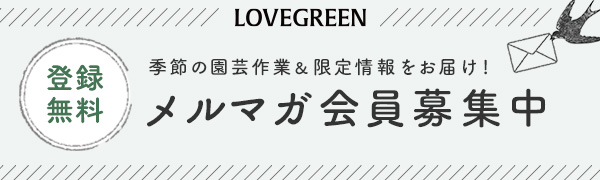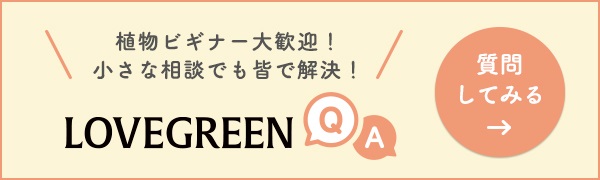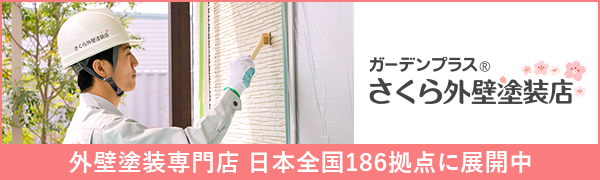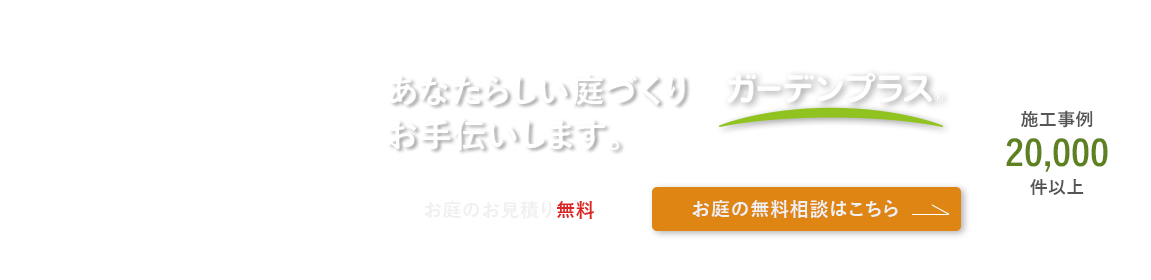縁起もいい!冬に見られる赤い実の植物は何?
LOVEGREEN編集部
このライターの記事一覧

冬はなんだか赤い実が多く見られる。鳥たちが上空から見た時に、緑の葉が落ちた中で赤は目立って、よく食べてもらえるためという説があるそうですよ。冬に見られる赤い実の植物をいくつかピックアップしました。名前の分からなかった赤い実の植物はありましたか?
目次
センリョウ

お正月によく見かけるセンリョウ(千両)。背丈は1メートルもない低木で、ギザギザの葉の中央に赤い実がつきます。次に出てくるマンリョウと間違われやすい植物ですね。鳥たちはマンリョウよりもセンリョウの赤い実の方が好みらしく、先になくなるのはセンリョウのことが多いです。
マンリョウ

こちらも名前がおめでたいことから、センリョウと一緒に並ぶことが多いマンリョウ(万両)。背丈はセンリョウと同じくらいで、マンリョウは葉の下に赤い実がつき、幹をぐるりと囲うように実ります。センリョウはセンリョウ科ですが、マンリョウはサクラソウ科なので、種類も全く違う植物です。
ピラカンサ

ピラカンサはバラ科の植物で、トゲが多くあるのが特徴です。冬に赤い実をつけます。また実におへそのような切れ込みがあるのがバラ科の植物の特徴でもあります。防犯上の理由からトゲのあるピラカンサを好んで植える家が多く、庭木や玄関などに多く植えられています。枝が良く伸びるので生垣などにも使われていますよ。
ナンテン

ナンテンも「難を転じる」と言われ、庭木に多く使われてきました。日が当たりにくい場所でもよく育つので、家の北側の方に植えられていることが多いです。ナンテンの赤い実はブドウの軸をひっくり返したような形になります。冬になれば、葉も赤く紅葉していることが多く、寺社仏閣などでもよく目にします。背丈は1~2メートルほどの低木です。

ちなみに赤い実ではないですが、変わり種の白い実のナンテンもありますよ。色が変わるだけで、雰囲気も変わって面白いですね。
クロガネモチ

こちらは高木の樹木で、大きいもので10メートルほどまで育ちます。高い木の上部にビッシリと赤い実がつき、鳥たちも食べるものが少なくなった頃に食べに来るので、長く赤い実を楽しめます。こちらも庭木や寺社仏閣に多く植栽されている樹木で、雌雄異体なので赤い実がつくのは全てメスの木になります。
気になる赤い実はありましたか?
すでに鳥たちがついばんでしまっている実もあるかと思いますが、少しでも赤い実の植物を覚えてもらえると嬉しいです。
▼関連記事
関連ワード
今月のおすすめコンテンツ
「縁起もいい!冬に見られる赤い実の植物は何?」の記事をみんなにも教えてあげよう♪