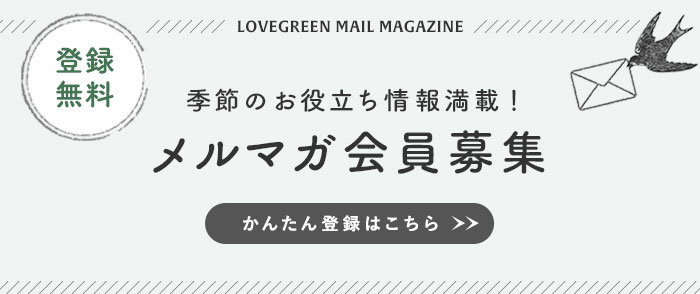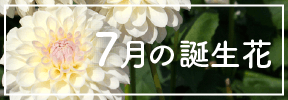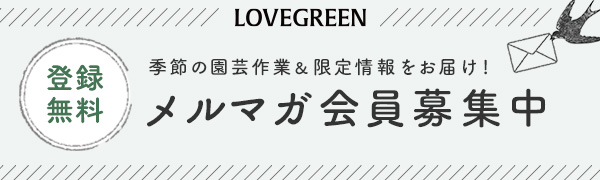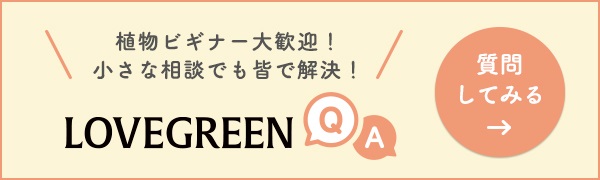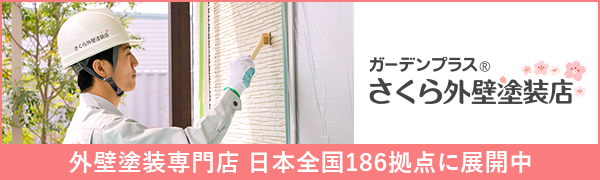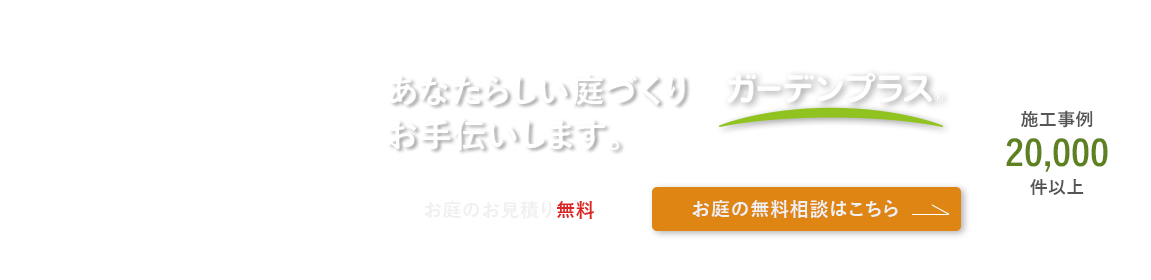ピンクの花が咲く木32種を春、夏、秋、冬の季節ごとに紹介!
山田智美
このライターの記事一覧

ピンクの花が咲く木を、春、夏、秋、冬に分けて季節ごとに紹介します。写真と一緒に花が咲く時期も案内しているので、名前を調べるのにも便利。お探しのピンクの花が咲く木が見つかるかもしれません。
目次
春(3月~4月)にピンクの花が咲く木12種
カワヅザクラ(河津桜)

- 学名:Prunus lannesiana cv. Kawazu-zakura
- 科名:バラ科
- 分類:落葉高木
- 開花期:2月~3月
カワヅザクラの特徴
カワヅザクラは、2月頃から開花し始める、早咲きの桜です。静岡県河津町で発見されたので河津桜と名付けられました。鮮やかなピンク色が美しい桜です。
▼カワヅザクラの育て方
ソメイヨシノ(染井吉野)

- 学名:Prunus x yedoensis
- 科名:バラ科
- 分類:落葉高木
- 開花期:3月~4月
ソメイヨシノの特徴
ソメイヨシノは、桜の中でも最も愛されている品種です。私たちが春の桜の開花を心待ちにしてお花見を楽しんでいるのは、このソメイヨシノです。薄桃色の花びらは風で散ってしまうほど儚く可憐で、その散り際の美しさもソメイヨシノ魅力となっています。
▼ソメイヨシノの育て方
シダレザクラ(枝垂れ桜)

- 学名:Cerasus spachiana
- 科名:バラ科
- 分類:落葉低木
- 開花期:3月~4月
シダレザクラの特徴
シダレザクラは、エドヒガンの枝が柳のように枝垂れているもののことをいいます。イトザクラとも呼ばれます。中でもベニシダレと呼ばれる品種は、ピンク色が濃く、とても鮮やかです。
▼シダレザクラの育て方
アケビ

- 学名:Akebia
- 科名:アケビ科
- 分類:落葉つる性木本
- 開花期:3月~4月
アケビの特徴
アケビは、日本の山野に自生するつる性木本です。秋に熟す果実は甘みがあり、食用になります。アケビの花色は、ピンクの他に白もあります。アケビの花は、大きいのが雌花、小さな花が塊になって咲くのが雄花です。
▼アケビの育て方
桃

![]()
- 学名:Amygdalus persica
- 科名:バラ科
- 分類:落葉高木
- 開花期:3月~4月
桃の特徴
桃は、春に花を咲かせ、夏に甘く瑞々しい果実を実らせる落葉高木です。桃には、果実の収穫よりも花を愛でることを目的に育てるハナモモがあります。桃の花は、ピンクの他に白花もあります。
▼桃の育て方
トキワマンサク(ベニバナトキワマンサク)

- 学名:Loropetalum chinensis
- 科名:マンサク科
- 分類:常緑高木
- 開花期:3月~5月
トキワマンサクの特徴
トキワマンサクは、春、梅より少し遅れて咲き始めます。トキワマンサクの花は、花びらが細く、はたきのような、ちょっと変った形状をしています。花色は、濃いピンクの他に白もあります。
▼トキワマンサクの育て方
カリン

- 学名:Pseudocydonia sinensis
- 科名:バラ科
- 分類:落葉高木
- 開花期:4月
カリンの特徴
カリンは、春に花が咲き、秋に洋梨のような果実を実らせる落葉高木です。カリンの花は、春、ソメイヨシノよりも少し遅れて開花します。明るいピンク色で、リンゴの花に似た可愛らしい花です。
▼カリンの育て方
ハナズオウ

- 学名:Cercis chinensis
- 科名:ジャケツイバラ科
- 分類:落葉低木、高木
- 開花期:4月
ハナズオウの特徴
ハナズオウは、春に小さな濃いピンク色の花を枝いっぱいに咲かせる可愛らしい庭木です。マメ科の樹木なので、花が終わった後には小さなマメが枝いっぱいにぶら下がります。ハナズオウは、他に白花種もあります。
▼ハナズオウの育て方
ウグイスカグラ

- 学名:Lonicera gracilipes
- 科名:スイカズラ科
- 分類:落葉低木
- 開花期:4月~5月
ウグイスカグラの特徴
ウグイスカグラは、日本の山野に自生しているスイカズラ科の落葉高木です。春に小さなピンク色の花を咲かせます。ウグイスカグラの花は、よく見るとラッパのような形をしています。
ハナミズキ

![]()
- 学名:Cornus florida
- 科名:ミズキ科
- 分類:落葉高木
- 開花期:4月~5月
ハナミズキの特徴
ハナミズキは、ソメイヨシノが散った頃から咲き始めます。枝の先に、空に浮かべるように花を咲かせます。ハナミズキの花のように見える部分は、実はガクが変化したもので花ではありません。花色は、ピンクの他に白があります。
▼ハナミズキの育て方
アザレア

![]()
- 学名:Rhododendron
- 科名:ツツジ科
- 分類:常緑低木
- 開花期:4月~5月
アザレアの特徴
アザレアは、日本のツツジを親にしてヨーロッパで改良された常緑低木です。ツツジによく似た花を咲かせます。花は、一重の他に八重咲きがあります。花色は、ピンクの他に白もあります。
▼アザレアの育て方
バラ

- 学名:Rosa
- 科名:バラ科
- 分類:落葉低木
- 開花期:4月~6月
バラの特徴
バラは、花の女王と呼ばれるほど、豪華で美しい花を咲かせる落葉低木です。木立性の他につるバラや半つる性などがあります。バラの花色は、ピンク以外に、白、黄、赤、紫、複色など、バリエーション豊富です。
▼バラの育て方
夏(5月~8月)にピンクの花が咲く木12種
サツキ

- 学名:Rhododendron indicum
- 科名:ツツジ科
- 分類:常緑低木
- 開花期:5月~6月
サツキの特徴
サツキは、とても強健でよく花を咲かせる常緑低木です。育てやすさと花付きの良さから、庭木の他に街路樹や生垣としても愛されています。サツキの花色は、ピンクの他に白、赤、複色などがあります。
▼サツキの育て方
タニウツギ(斑入り)

- 学名:Weigela hortensis
- 科名:タニウツギ科(スイカズラ科)
- 分類:落葉低木
- 開花期:5月~6月
タニウツギの特徴
タニウツギは、初夏に明るいピンク色の花を咲かせる落葉低木です。タニウツギの花色は、ピンクでも濃く赤に近いピンクから、淡く明るいピンクまでバリエーションが豊富です。
シモツケ

- 学名:Spiraea japonica
- 科名:バラ科
- 分類:落葉低木
- 開花期:5月~9月
シモツケの特徴
シモツケは、ピンク色の小さな花を、枝の先に毬のように咲かせる落葉低木です。生長しても1m前後と育てやすいことから、庭木として愛されてきました。シモツケの花色には、ピンクの他に白や赤があります。
ドドナエア

- 学名:Dodonaea
- 科名:ムクロジ科
- 分類:常緑低木
- 開花期:4月
ドドナエアの特徴
ドドナエアは、オリーブのような細い葉と、大きくならない樹形が人気のオーストラリアンプランツです。葉色には、グリーンや銅色があり、庭木として人気です。花と紹介しましたが、写真の花のように見えるものは、花ではなく種子が入っている莢で6月頃にこのような状態になります。
ピンクアナベル

- 学名:Hydrangea arborescens
- 科名:アジサイ科
- 分類:落葉低木
- 開花期:6月~7月
ピンクアナベルの特徴
ピンクアナベルは、ピンク色の花を咲かせるアメリカアジサイの仲間です。白花のアナベルに比べては花が小さいのが特徴です。
▼ピンクアナベルの育て方
スモークツリー

- 学名:Cotinus coggygria
- 科名:ウルシ科
- 分類:落葉高木
- 開花期:6月~8月
スモークツリーの特徴
スモークツリーは、名前の通り、初夏に煙のような、または綿菓子のような花を咲かせる落葉高木です。スモークツリーの花色は、ピンクの他にグリーンがかった白があります。
▼スモークツリーの育て方
ネムノキ

- 学名:Albizia julibrissin
- 科名:マメ科
- 分類:落葉高木
- 開花期:6月~8月
ネムノキの特徴
ネムノキは、初夏から夏にかけて、羽毛のようなふわふわとした可愛らしい花を咲かせる、マメ科の落葉高木です。夜になると葉を閉じることから、ネムノキという名前がつきました。
▼ネムノキの育て方
サルスベリ(百日紅)

- 学名:Logerstroemia indica
- 科名:ミソハギ科
- 分類:落葉高木
- 開花期:6月~9月
サルスベリ(百日紅)の特徴
サルスベリは、漢字で「百日紅」と書くくらい、開花期間の長い落葉高木です。その幹がサルも滑り落ちるくらい滑らかだということから、サルスベリと名付けられました。花色は、ピンクの他に、白、赤、紫などがあります。
▼サルスベリの育て方
ボタンクサギ

- 学名:Clerodendrum bungi
- 科名:シソ科
- 分類:落葉(常緑)低木
- 開花期:6月~10月
ボタンクサギの特徴
ボタンクサギは、濃いピンク色の花が美しい低木です。熱帯地方では常緑樹として扱われます。
コムラサキ

- 学名:Calliparpa dichotoma
- 科名:クマツヅラ科
- 分類:落葉低木
- 開花期:7月~8月
コムラサキの特徴
コムラサキは、夏に淡いピンク色の花を咲かせ、秋には紫色の実をつける落葉低木です。ムラサキシキブと混同されがちですが、コムラサキの方が実の数が多いのが特徴です。
▼ムラサキシキブとコムラサキの見分け方
ムクゲ

- 学名:Hybiscus syriacus
- 科名:アオイ科
- 分類:落葉低木
- 開花期:7月~8月
ムクゲの特徴
ムクゲは、夏の暑い盛りに、大きなハイビスカスのような花を咲かせる落葉低木です。低木といっても大きなものは2mを越すくらいまで生長します。ムクゲの花色は、ピンクの他に、白、紫、複色などがあります。
▼ムクゲの育て方
ハイビスカス

- 学名: Hybiscus
- 科名:アオイ科
- 分類:落葉低木
- 開花期:7月~9月
ハイビスカスの特徴
ハイビスカスは、南国の花のイメージが強いですが、実はムクゲやフヨウの仲間です。ハイビスカスの花は、朝咲いて夕方にはしぼんでしまう一日花です。ハイビスカスの花色は、ピンクの他に、赤、黄、白、複色等があります。
▼ハイビスカスの育て方
秋(9月~11月)にピンクの花が咲く木3種
ハギ(萩)

- 学名:Laspedeza thunbergii
- 科名:マメ科
- 分類:落葉低木
- 開花期:9月~10月
ハギ(萩)の特徴
ハギは、秋の七草にも数えられるくらい、昔から日本で愛されてきたマメ科の落葉低木です。枝垂れるように伸ばした枝の先に小さな花をたわわにに咲かせる姿はとても美しく見応えがあります。ハギの花色は、ピンクの他に、白や紫があります。
▼ハギの育て方
フユザクラ

- 科名:バラ科
- 分類:落葉高木
- 開花期:10~3月
フユザクラの特徴
フユザクラは、日本に自生するヤマザクラやサトザクラ、マメザクラなどの交雑種だと考えられています。秋から冬に花を咲かせるのでフユザクラと呼ばれます。フユザクラには淡いピンク色から白花などがあります。
サザンカ

- 学名:Camellia sasanqua
- 科名:ツバキ科
- 分類:常緑低木
- 開花期:10月~2月
サザンカの特徴
サザンカは、ツバキによく似た花を咲かせる常緑低木です。椿よりも耐寒性が強く、秋から初春まで花を咲かせます。サザンカの花色は、濃いピンクから淡いピンクまであります。
▼サザンカの育て方
冬(12月~2月)にピンクの花が咲く木5種
椿(ツバキ)

- 学名:Camellia japonica
- 科名:ツバキ科
- 分類:常緑高木
- 開花期:11月~4月
椿(ツバキ)の特徴
椿は、日本の冬を代表するような常緑高木です。光沢のあるグリーンの葉が特徴的です。椿の花色は、ピンクの他に、赤や白、複色などがあります。
▼椿の育て方
梅(ウメ)

- 学名:Armeniaca mume
- 科名:バラ科
- 分類:落葉高木
- 開花期:1月~3月
梅(ウメ)の特徴
梅は、春の訪れを代表するような落葉高木です。まだ寒い初春から香りのよい花を咲かせます。梅の花色は、ピンクの他に、白、赤、複色等があります。1本の木で白とピンクの2色の花を咲かせる品種もあります。
▼梅の育て方
沈丁花(ジンチョウゲ)

- 学名:Daphne odora
- 科名:ジンチョウゲ科
- 分類:常緑低木
- 開花期:2月~4月
沈丁花(ジンチョウゲ)の特徴
沈丁花は、爽やかな芳香が印象的な常緑低木です。沈丁花の花の香りが好きだという人も多いようです。沈丁花の花は、外側がピンク色で中は白色です。他に外側も内側も真白な白花種もあります。
▼沈丁花の育て方
アセビ

- 学名:Pieris japonica
- 科名:ツツジ科
- 分類:常緑低木
- 開花期:2月~4月
アセビの特徴
アセビは、小さなつぼ型の花を、かんざしのように房状に下垂させて咲かせる庭木です。鼻を近づけるとほのかに芳香がします。アセビの花色は、ピンクの他に白があります。
▼アセビの育て方
ボケ(木瓜)

- 学名:Chaenomeles speciosa
- 科名:バラ科
- 分類:落葉低木
- 開花期:2月~5月
ボケ(木瓜)の特徴
ボケは、初春にウメに似た可愛らしい花を咲かせる落葉低木です。花の後に洋梨のような果実を実らせますが、食用にはできません。ボケの花色は、ピンクの他に、白、赤、複色があります。
▼ボケの育て方
ピンクの花が咲く木を季節ごとご紹介しました。お探しの木はありましたか?お散歩や庭木探しの参考にしてください。
▼編集部のおすすめ
関連ワード
今月のおすすめコンテンツ
「ピンクの花が咲く木32種を春、夏、秋、冬の季節ごとに紹介!」の記事をみんなにも教えてあげよう♪