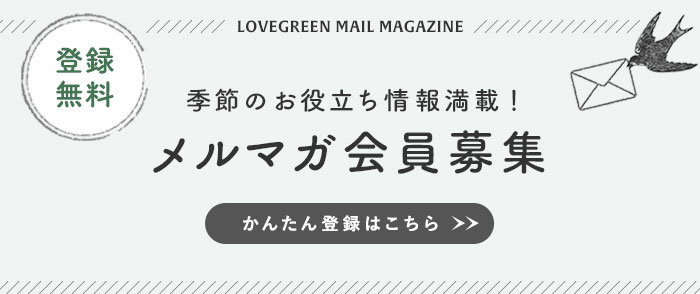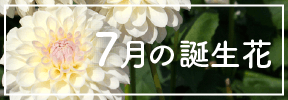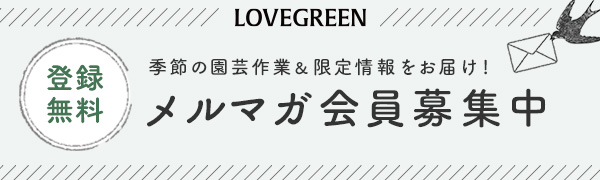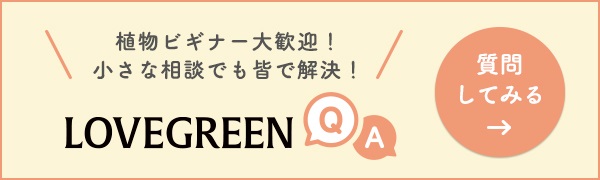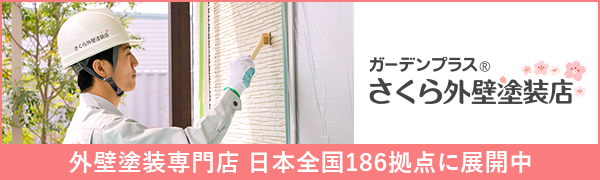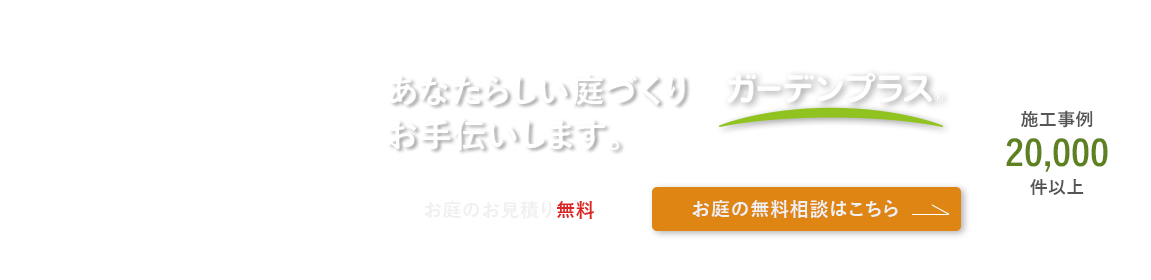赤い実のなる木30種を春、夏、秋、冬の季節別に紹介!食べられる実や毒のある実まで
山田智美
このライターの記事一覧

赤い実のなる木をどれくらいご存知ですか。食べられる赤い実のなる木、毒のある赤い実のなる木も含めて、季節ごとに赤い実のなる木をご紹介します。シンボルツリー選びの参考にもなります。
目次
春~初夏に赤い実のなる木3種
ナワシロイチゴ

- 分類:落葉低木
- 結実期:6月
ナワシロイチゴは春にピンク色の可愛らしい花を咲かせる落葉低木です。低木といっても枝を低く、地面を這うようにほふくさせます。初夏に赤く色づくナワシロイチゴの実は、半透明で宝石かイクラのようです。
クサイチゴ

- 分類:落葉低木
- 結実期:5月~6月
クサイチゴは初春から春にかけて、山林や藪の中で白い花を咲かせる、バラ科の落葉低木です。5月~6月に赤く色づいたクサイチゴの実は、小さな粒の集合して親指の爪ほどの大きさになります。ビーズ細工のようで可愛らしい実です。
ラズベリー

![]()
- 分類:落葉低木
- 結実期:5月~6月
ラズベリーは春に5枚の花びらの可愛らしい花を咲かせ、初夏に真赤な実を付ける、バラ科の落葉低木です。ラズベリーは和名をキイチゴ、フランス名はフランボワーズと呼ばれるベリーです。小さな粒を集合させた果実は香りがよく、ほどよい酸味と甘みがあります。
夏に赤い実のなる木2種
スグリ

- 分類:落葉低木
- 結実期:6月~7月
スグリは初夏に宝石のような半透明の美しい実を付けるスグリ科の落葉低木です。スグリの実の色には、赤や白、黒、グリーンなどがあります。
ユスラウメ

- 分類:落葉低木
- 結実期:6月~7月
ユスラウメは春に梅に似た小さな花を咲かせるバラ科の落葉低木です。初夏にさくらんぼのような直径1㎝程度の真赤な実を枝の先にたわわに実らせます。新芽の明るいグリーンも美しく、花も実もない時期も楽しめます。
秋に赤い実のなる木11種
ツルコケモモ

- 分類:常緑低木
- 結実期:9月~10月
ツルコケモモはつるのように枝を伸ばす。ツツジ科の常緑低木です。春に小さな花を咲かせ、秋に結実します。赤く熟した実は直径1から1.5㎝程度。酸味が強く生食には向きませんが、ジャムや果実酒にして楽しめます。
サンザシ

![]()
- 分類:落葉低木
- 結実期:9月~10月
サンザシは春に梅に似た花を咲かせる、バラ科の落葉低木です。花色は白やピンクがあります。秋に赤く熟すサンザシの実は、酸味が強く生食には向きません。ジャムや果実酒にして利用されます。
クラブアップル(ヒメリンゴ)

- 分類:落葉高木
- 結実期:10月~11月
クラブアップルとは和名をヒメリンゴとも言い、小さなリンゴの実をつけるバラ科の落葉高木の俗称です。クラブアップル(ヒメリンゴ)は実が小さく、酸味も強いので、生食には向きません。ジャムやコンポートなどにして利用されます。
イチゴノキ

- 分類:常緑低木
- 結実期:10月~11月
イチゴノキは春に花を咲かせ、晩秋に赤い実をつける、ツツジ科の落葉低木です。イチゴノキの名前の由来は果実がイチゴに似ているからだと言わています。真赤に色付いたイチゴノキの実はクサイチゴの実によく似ています。
ハナミズキ

- 分類:落葉高木
- 結実期:9月~11月
春に白やピンクの花を咲かせ、秋に赤く色付いた実を付けるハナミズキは、ミズキ科の落葉高木です。秋にはどんぐりのような形状の赤い実を枝の先に数個実らせます。ハナミズキは、春の花、夏の新緑、秋の紅葉と果実と四季を通して楽しめる魅力的な庭木です。
ノイバラの実

- 分類:落葉低木
- 結実期:9月~11月
ノイバラは春に可憐な白い花を咲かせ、秋には小さな赤い実をつけるバラ科の落葉低木です。ノイバラは、枝の先に直径5mm程度の小さな実を複数付けます。ノイバラの実はドライフラワーにして長く楽しむことができます。
ガマズミ

- 分類:落葉高木
- 結実期:10月
ガマズミは春に真白な花を咲かせ、秋に真赤な実を付ける、レンプクソウ科の落葉高木です。秋に実る赤い果実は、小さな実を集合させたような形状をしていて、秋の陽射しに照り輝く姿は宝石のようです。ガマズミの果実は酸味が強く、生食には向きません。果実酒などに利用されます。
アロニア

![]()
- 分類:落葉高木
- 結実期:10月~11月
アロニアは北アメリカ原産のバラ科の落葉高木です。アロニアには赤い実を付ける品種と黒い実を付ける品種があります。赤い実を付けるアロニア・アルブティフォリアのほうが果実自体が小さく、風情があります。
ヨウシュカンボク(ビバーナム・コンパクタ)

![]()
- 分類:落葉低木
- 結実期:10月~11月
ヨウシュカンボク(ビバーナム・コンパクタ)は春に白い花が咲き、秋に真赤に熟す実が美しい落葉低木です。切り花でもビバーナム・コンパクタ、あるいはコンパクタベリーという名前で流通しています。
ウメモドキ

- 分類:落葉低木
- 結実期:10月~11月
ウメモドキは冬に小さな赤い実を付けるトチノキ科の落葉低木です。庭に色が少なる秋から冬に赤い果実を枝に実らせて、庭を賑やかに彩ってくれます。
イイギリ

- 分類:落葉高木
- 結実期:10月~11月
イイギリは高木の上の方に赤い実を下げるように実らせる、イイギリ科の落葉高木です。イイギリの実はブドウのような房状で、熟すと真赤に色付きます。秋も深まり、葉がすべて落ちてからも実だけが枝に残っていることもあります。
冬に赤い実のなる木6種
コトネアスター

- 分類:落葉、または常緑低木
- 結実期:11月~1月
コトネアスターは地面を這うように枝を伸ばして生長していく、バラ科の落葉あるいは常緑低木です。春に白い小さな花を咲かせ、冬に真赤な直径1㎝足らずの実を付けます。地表を覆うように生長していくので、グランドカバーとしても人気があります。
ナンテン(南天)

![]()
- 分類:常緑低木
- 結実期:11月~2月
ナンテン(南天)は冬に色付く赤い実が印象的な、メギ科の常緑低木です。冬の寒い最中に赤果実を実らせることから、縁起がよいとされ、庭木として人気があります。お正月飾りにもよく利用されます。
万両(マンリョウ)

![]()
- 分類:常緑低木
- 結実期:12月~3月
万両(マンリョウ)は冬に赤い実を付けるサクラソウ科の常緑低木です。真赤な小さな実を数個まとめて枝から下げるように実らせる様子が縁起がよいとされ、万両と名付けられました。
千両(センリョウ)

![]()
- 分類:常緑低木
- 結実期:11月~1月
千両(センリョウ)は冬に真赤な実を付ける、センリョウ科の常緑低木です。万両(マンリョウ)との見分け方は、千両(センリョウ)は枝の先端に上向きに粒々とした赤い実を付けます。対して万両(マンリョウ)は枝から下げるように実を付けます。実の付き方で、見分けられます。
セイヨウヒイラギ

![]()
- 分類:常緑高木
- 結実期:11月~1月
セイヨウヒイラギはヒイラギに似たギザギザとした葉を持つ、モチノキ科の常緑高木です。冬に赤い実を付けます。光沢のあるグリーンの葉と赤い実のコントラストが美しい庭木です。セイヨウヒイラギは、果実がクリスマスの頃に赤く色付くことから、クリスマスホーリーという別名もあります。
アオキ

![]()
- 分類:常緑低木
- 結実期:12月~4月
アオキは耐陰性の強い、アオキ科の常緑低木です。葉が大きく光沢があり深いグリーンをしています。斑入り種などもあります。日当たりの悪い場所で元気に育ってくれる、シェードガーデンの味方です。冬にはアーモンド形の赤い実を付けます。
食べられる赤い実のなる木5種
ジューンベリー

- 分類:落葉高木
- 結実期:6月
ジューンベリーは春に桜に似た、桜よりも小さな白い花を枝いっぱいに咲かせる、バラ科の落葉高木です。春の開花後、6月に真赤な直径1㎝程度の実を付けます。ジューンベリーの実は黒に近い赤まで熟してから食べると、酸味はなく甘く、生食できます。他にもジャムやコンポートにして利用されます。
サクランボ

![]()
- 分類:落葉高木
- 結実期:5月~7月
サクランボは春に桜の花を咲かせ、初夏に結実する、バラ科の落葉低木です。サクランボという名前は桜ん坊のことで、名前の通り桜の果実です。ただし、すべての桜の果実が食べられるわけではなく、サクランボが実る品種というものがありますので、購入時に確認してください。
ヤマモモ

- 分類:常緑高木
- 結実期:6月~7月
ヤマモモは初夏に真赤な実を付ける、ヤマモモ科の常緑高木です。雌雄異株で、雌株にしか果実は付きません。とても大きな木にの上の方に果実をつけるので収穫は困難ですが、黒に近い赤まで熟した実は甘く、塩を振って食べます。果肉部分は少なく、中には大きな種が入っていて、勢いよく噛むと固いので気をつけてください。
リンゴ(セイヨウリンゴ)

![]()
- 分類:落葉高木
- 結実期:9月~11月
リンゴは春に桜に似た花を咲かせ、秋に真赤な実を付ける落葉高木です。果樹として人気があります。食用になるリンゴは正確にはセイヨウリンゴという種類です。
ヤマボウシ

- 分類:落葉あるいは常緑高木
- 結実期:9月~10月
ヤマボウシは春にハナミズキに似た花を咲かせる、ミズキ科の落葉あるいは常緑高木です。秋に朱に近い赤い実を実らせます。ヤマボウシの実は外側の固い果皮を剥き、内側の柔らかい果肉を食べることができます。
毒のある赤い実のなる木3種
ピラカンサ

- 分類:常緑低木
- 結実期:11月~2月
ピラカンサは春に小さな白い花を枝いっぱいに咲かせ、冬に真赤な実をたわわに実らせる、バラ科の常緑低木です。低木といっても放っておくと3m程まで大きくなります。ピラカンサの実には有毒成分が含まれていると言われいます。きれいな色をしていますが、食べないように気をつけてください。
ヒョウタンボク

Adobe Stock
- 分類:落葉低木
- 結実期:6月~7月
ヒョウタンボクは春にスイカズラによく似た花を咲かせ、初夏には真赤なきれいな実を付けるスイカズラ科の落葉低木です。ヒョウタンボクの名前の由来は、初夏に結実する実が枝の両脇に2つ並んで付くところからヒョウタンを連想させるからだそうです。ヒョウタンを連想させるかどうかは人それぞれですが、初夏に色付く果実は赤く半透明で美しく、観賞価値があります。ただし、ヒョウタンボクの実は有毒です。間違って食べないように気をつけてください。
イチイ

- 分類:常緑低木
- 結実期:6月~7月
イチイは初夏に赤い実を付ける、イチイ科の常緑低木です。オンコという別名でよばれることもあります。針のような濃いグリーンの葉の間から中心部が少しくぼんだ赤い実を覗かせます。イチイの種子は有毒ですので、間違って食べないようにしてください。
赤い実のなる木を探してみよう

グリーンの葉に赤い実は補色の組み合わせでとても目を惹きます。春から初夏の若葉の季節の赤い実も、秋から冬の葉が落ちてから枝に残る赤い実も、どちらも美しく見ごたえがあります。赤い実のなる木をお庭のシンボルツリーとして迎えれば、家族の記憶にも残るでしょう。
赤い実のなる木は身近にもたくさんあります。赤い実がなる木を探してみませんか。
▼編集部のおすすめ
関連ワード
今月のおすすめコンテンツ
「赤い実のなる木30種を春、夏、秋、冬の季節別に紹介!食べられる実や毒のある実まで」の記事をみんなにも教えてあげよう♪