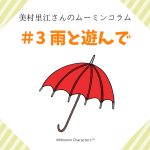庭木におすすめの常緑樹38種!低木、中木、高木、花木、果樹、ハーブも
更新
公開

常緑樹とは?常緑樹の定義から庭木やシンボルツリーにおすすめの理由を説明します。さらに常緑樹を低木、中木、高木、花木、果樹、さらにハーブまでずらり38種類。洋風のお庭にも、和風のお庭にもよく馴染む常緑樹を紹介します。
目次
- 常緑樹とは?常緑樹の定義
- 常緑樹は庭木、シンボルツリーにおすすめ
- 庭木におすすめ!低木の常緑樹5種類
- 庭木におすすめ!中木の常緑樹2種類
- 庭木におすすめ!高木の常緑樹2種類
- 花が咲く常緑樹14種類
- 実がなる木!常緑の果樹8種類
- おしゃれなハーブの常緑樹6種類
常緑樹とは?

常緑樹とは、一年を通しグリーンの葉を絶やさない樹木のことを指します。冬でも青々とした葉を茂らせる松やモミの木などが常緑樹です。
常緑樹は落葉しないわけではありません。種類によりますが、多くは1年~3年のサイクルで新しい葉が出て古い葉が落ちていきます。冬にも青々とした葉を絶やさない常緑樹は、永遠や生命の象徴として神聖視されることもあります。
常緑樹は庭木、シンボルツリーにおすすめ

常緑樹は庭木やシンボルツリーにおすすめです。一年を通して葉を絶やさない常緑樹はお庭の景観を司る頼もしい存在。冬のお庭でも存在感を発揮します。
紅葉も落葉もしない常緑樹は四季を感じることができない、景色が単調だという意見もありますが、そんなことはありません。常緑樹は表情豊か。新芽のグリーンは色鮮やかです。花を咲かせ、実を結ぶ種類もたくさんあります。季節ごとに違う表情を見せてくれる上に、一年中グリーンの葉が茂る常緑樹は庭木、シンボルツリーにおすすめです。
目隠しにおすすめ
冬になっても落葉しない常緑樹は目隠しにおすすめです。隣家や通りからの気になる目線からプライバシーを守りたいけれど、無機質なフェンスでは味気ないという時に常緑樹の目隠しは活躍してくれます。しっかり目隠しになる上に風や日光は通してくれるのが常緑樹の目隠しです。
生垣におすすめ
常緑樹は生垣にもおすすめ。生垣は植物で作る垣根です。一年中グリーンの葉を絶やさない常緑樹なら防犯や不要なゴミや動物の侵入を防ぐ役割をしてくれます。
庭木におすすめ!低木の常緑樹5種類
ツゲ

- 花期:3月~4月
- 樹高:3m以上
ツゲは、小さく丸みを帯びた光沢のある葉が美しい常緑樹です。放っておくと3mを越す大きな木になりますが、刈り込みに堪える強さがあるので、生垣やトピアリーとして利用されます。
シキミ

- 花期:3月~4月
- 樹高:3m程度
シキミは、葉や枝に芳香があるシキミ科の常緑低木です。耐陰性も強く、手間のかからない丈夫な庭木です。秋になる実は中華料理などで使用される八角(スターアニス)に似ていますが、シキミは毒性が強いので間違えて食べないように注意が必要です。
シルバープリベッド

- 花期:4月~5月
- 樹高:1~3m
シルバープリベッドは、斑入りの小さな葉が可愛らしいモクセイ科の低木です。半落葉ですが温暖な地域では、ほぼ常緑です。春に小さな香りの良い花を咲かせ、秋に黒い果実を付けます。
マホニア

- 花期:11月~12月
- 樹高:1~2m
マホニアは、細くギザギザとした葉が特徴的な常緑低木です。冬に明るい黄色の花を咲かせます。あまり大きくならないので育てやすい庭木です。
フィリフェラオーレア

- 樹高:0.5~3m
フィリフェラオーレアは、ヒノキ科ヒノキ属の常緑低木です。強い刈り込みにも耐えるので、生垣にも好まれます。明るいライムグリーンの葉が美しい庭木です。
庭木におすすめ!中木の常緑樹2種類
ネズミモチ

- 花期:5月~6月
- 樹高:3~5m
ネズミモチは、光沢のある濃いグリーンの葉が美しい常緑中高木。初夏に香りの良い白い花を咲かせ、秋から冬に黒い果実を実らせます。
ヒイラギ

- 花期:10月~12月
- 樹高:3m以上
ヒイラギは、ギザギザとしたノコギリのような葉が印象的な中国原産の常緑樹です。クリスマスの時期に赤い実を付ける西洋ヒイラギとは別種です。葉の表面には光沢があります。葉が尖っているので防犯の役割を果たすとされ、生垣として人気があります。
庭木におすすめ!高木の常緑樹2種類
ヒイラギモクセイ

- 花期:10月
- 樹高:5~6m
ヒイラギモクセイは、キンモクセイよりも少し遅れて香りの良い花を咲かせる常緑高木です。葉はヒイラギのようなギザギザとした形状で、秋に小さな白い花を咲かせます。常緑で葉の密度も高く、防犯の役割も果たすとして生垣に好まれます。
ユズリハ

- 樹高:5~15m
ユズリハは、古い葉が下を向き新しい葉が上を向くところから、世代交代、子孫繁栄の木とされています。光沢のある大きな葉が印象的な庭木です。
花が咲く常緑樹15種類
アセビ

- 花期:2月~4月
- 樹高:1~3m
アセビは、小さな壺状の花をかんざしのように下垂させて咲かせる姿が美しい庭木です。丈夫で大きくならないため、生垣として使いやすい庭木です。
ジンチョウゲ

- 花期:3月~4月
- 樹高:1.5m程度
ジンチョウゲは、春に爽やかな香りの良い花を咲かせる常緑低木です。ジンチョウゲには白花種と赤花種があります。常緑で丈夫なため、生垣や庭木として好まれます。
ミモザ

- 花期:3月~4月
- 樹高:5~10m
ミモザは、春にふわふわの羽毛のような黄色い花を咲かせる常緑高木です。花の美しさと合わせて香りも良いことからシンボルツリーとして好まれます。
トキワマンサク

- 花期:4月~5月
- 樹高:3~5m
トキワマンサクは、ほうきのような、筆のような、変わった花を咲かせるマンサク科の庭木です。トキワマンサクというと通常ベニバナトキワマンサクを指しますが、白花種もあります。
ツツジ、サツキ

- 花期:4月~5月(四季咲き)
- 樹高:1~3m
ツツジとサツキは、鮮やかな花色が印象的なツツジ科の常緑低木です。葉の表面には産毛のような毛があります。花色は白やピンク、濃いピンクなど。環境が合えば夏や秋でも花を咲かせます。
カラタネオガタマ

- 花期:4月~5月
- 樹高:3~5m
カラタネオガタマは、夏に甘い香りの花を咲かせる常緑高木です。葉の密度が高く目隠しとしても活躍します。
ハクチョウゲ

- 花期:5月~6月
- 樹高:1~3m
ハクチョウゲは、アカネ科の常緑低木です。常緑ですが、冬には葉を少し落とします。初夏に直径1cm足らずの小さな花を咲かせます。花にはほのかに芳香があります。
シャリンバイ

- 花期:5月~6月
- 樹高:1~3m
シャリンバイは、厚みと光沢のある葉が印象的な常緑低木です。春に咲く花は白く、花びらが5枚で梅を思わせます。非常に丈夫なため街路樹にも利用されます。
クチナシ

- 花期:6月~7月
- 樹高:1~3m
クチナシは、初夏にうっとりするくらい甘い香りの花を花を咲かせる常緑低木です。花色は白、一重咲きと八重咲きがあります。花径が小さなサイズの品種もあります。
アベリア

- 花期:四季咲き
- 樹高:1~2m
アベリアは、スイカズラ科の常緑低木です。環境が合えばほぼ四季咲きで、ピンクや白の小さな花を咲かせます。剪定時期をあまり選ばず、強い刈り込みにも耐える育てやすい庭木です。
常緑ヤマボウシ

- 花期:6月~7月
- 樹高:5~10m
常緑ヤマボウシは、ミズキ科の常緑高木です。初夏にクリーム色がかった白の花を咲かせます。常緑ヤマボウシは樹形が乱れにくく管理が楽なので、目隠しや生垣として人気のある庭木です。
タイサンボク

- 花期:6月~7月
- 樹高:10m以上
タイサンボクは、高木の上の方に大きくて香りの良い真白な花を咲かせます。葉の表面は光沢があるグリーンで裏は茶色です。香料の「マグノリア」は、タイサンボクのことを指します。
ジャスミン(マツリカ)

- 花期:7月~9月
- 樹高:~3m
ジャスミンは、香りの良い花を咲かせることで有名なモクセイ科ソケイ属の常緑低木です。ジャスミンの花の香りは、香水の原料にされたりお茶に混ぜてジャスミン茶にされたりしています。
キンモクセイ

- 花期:9月~10月
- 樹高:5~10m
キンモクセイは、秋に甘く香りの良い花を咲かせることで人気の常緑高木です。オレンジ色の小さな花を枝いっぱいに咲かせます。キンモクセイは葉の密度も高く、丈夫で強い刈り込みにも耐えるので、目隠しとして人気があります。
ツバキ

- 花期:11月~12月、1月~3月
- 樹高:5~10m
ツバキは、冬に美しい花を咲かせる常緑高木です。花は一重咲きから八重咲きまであります。光沢のある濃いグリーンの葉は密度が高く、生垣や目隠しとしても人気です。ツバキはチャドクガの幼虫の被害にあいやすいので注意が必要です。
実がなる木!常緑の果樹8種類
ナワシログミ

- 収穫期:5月~6月
- 樹高:1~3m
ナワシログミは、銀色がかった光沢のある葉が特徴の常緑低木です。赤く熟したナワシログミの実は柔らかく、酸味と甘みがあります。強い刈り込みにも耐えるので、生垣として利用されます。
ビワ

- 収穫期:6月
- 樹高:5~10m
ビワは、冬に白い花を咲かせ、初夏に果実を実らせる果樹です。放っておくと大きくなるので、適宜剪定が必要です。大きな葉が印象的な庭木です。
ヤマモモ

- 収穫期:6月~7月
- 樹高:5~10m
ヤマモモは、高木の枝の先にみっしりと赤い果実を実らせる果樹です。雌雄異株で実がなるのは雌株のみです。
クランベリー(ツルコケモモ)

- 収穫期:9月~12月
- 樹高:10~20cm(ほふく性)
クランベリーは、秋から冬にかけて真赤な果実を実らせる常緑低木です。木立ではなく、つるを伸ばすように地面をほふくして生長します。クランベリーの果実は非常に酸味が強く生食には向きません。ジャムやジュースにして楽しめます。
レモン

- 収穫期:11月~3月
- 樹高:5m
レモンは、香りの良い実を付ける常緑高木です。春から夏に咲く花も香りが良いのが特徴です。耐寒性が強くないので、暖地での栽培に向いています。
ピラカンサ

- 観賞期:11月~2月
- 樹高:3~5m
ピラカンサは、枝の先に真赤な実をたわわに下げるように実らせる常緑低木です。果実は食用にはできません。枝に小さなトゲがあるので防犯の役割も果たすとして生垣としても人気です。
ソヨゴ

- 観賞期:11月~2月
- 樹高:5~10m
ソヨゴは、モチノキ科モチノキ属の常緑高木です。乾燥に強い上に自然樹形で整うので育てやすいのが特徴。秋に真赤に色付く実が可愛らしい庭木です。
万両

- 観賞期:11月~2月
- 樹高:~1m
万両は、お正月のお飾りも使用される常緑低木です。枝葉を広げず、樹高も1m以内とコンパクトと場所を取りません。
おしゃれなハーブの常緑樹6種類
月桂樹(ローリエ)

- 花期:4月~5月
- 樹高:10m以上
月桂樹は、クスノキ科の常緑高木。別名をローリエまたはローレルとも呼ばれ、葉をハーブとして使用します。月桂樹は比較的病害虫の被害も少なく、育てやすい庭木です。
マートル

- 花期:5月~6月
- 樹高:1~3m
マートルは、地中海地方原産のフトモモ科の常緑低木です。光沢のある葉が美しい庭木です。和名をギンバイカと言い、初夏に梅に似た白い花を咲かせます。
フェイジョア

- 花期:7月~8月
- 樹高:5~6m
フェイジョアは、ピンクの花を咲かせる常緑高木です。強い刈り込みにも耐えるので、低く刈り込んで管理することも可能です。夏に咲く花はエディブルフラワーとして食用にできます。
ラベンダー

- 花期:5月~7月
- 樹高:30~100cm
ラベンダーは、香りの良い花を咲かせる常緑低木です。ラベンダーには多くの種類がありますが、ラベンダー独特の甘い芳香を楽しむなら、イングリッシュラベンダーがおすすめです。
ローズマリー

- 花期:四季咲き
- 樹高:~2m
ローズマリーは、香りが良いことで有名なシソ科の常緑低木です。葉の密度が高く、刈り込みに耐えます。香りの良い葉は、料理やポプリに使用するなどハーブとして活躍します。
ウェストリンギア

- 花期:四季咲き
- 樹高:~1.5m
ウェストリンギアは、別名を「オーストラリアンローズマリー」ともいう、シソ科の常緑低木です。見た目はローズマリーによく似ていますが、食用にはできません。細い葉と華奢な樹形が美しい低木です。
常緑樹の魅力をお伝えしました。一年中グリーンを絶やさず、季節ごとに違う表情を見せてくれる常緑樹。常緑樹があれば、冬でもお庭が寂しくなることはありません。お気に入りの常緑樹を見つけて庭木やシンボルツリーとして迎えてください。
▼編集部のおすすめ