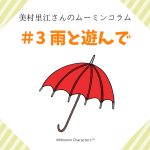実のなる木図鑑|食べられる実や木になる実の種類を季節ごとに紹介
更新
公開

実のなる木の種類を紹介します。食べられる実や木になる美しい実を、季節ごとに写真付きで説明しているので名前がわかります。
目次
食べられる実のなる木
クサイチゴ

- 学名:Rubus hirsutus
- 科名:バラ科
- 分類:落葉低木
- 花期:3月~4月
- 果期:5月~6月
クサイチゴは明るい半日陰を好む野生のイチゴです。口に入れると甘く瑞々しく、タネの粒々とした食感を楽しめます。
ナワシロイチゴ

- 学名:Rubus hirsutus
- 科名:バラ科
- 分類:落葉低木
- 花期:3月~4月
- 果期:5月~6月
ナワシロ(苗代)はイネを育苗する苗床のこと。田植えの頃に熟すのでナワシロイチゴと呼ばれます。果実は甘く、口の中でプチプチと潰れていくような食感を楽しめます。
ナツグミ

- 学名:Elaeagnus multiflora
- 科名:グミ科
- 分類:落葉低木
- 花期:4月~5月
- 果期:5月~7月
ナツグミは田植えの頃に赤く熟すのでナツグミと呼ばれます。果実には酸味と甘さがあります。
ジューンベリー

- 学名:Amelancher
- 科名:バラ科
- 分類:落葉高木
- 花期:3月~4月
- 果期:6月
ジューンベリーは6月に熟すのでジューンベリー。黒に近いくらい赤く熟した実は生食の他、果実酒やジャムなどにして楽しめます。
ユスラウメ

- 学名:Prunus tomentosa
- 科名:バラ科
- 分類:落葉低木
- 花期:3月~4月
- 果期:5月~6月
ユスラウメは直径1cm程度のサクランボのような実が可愛らしい植物。食べると甘く瑞々しいのが特徴です。
ラズベリー

- 学名:Rubus idaeus
- 科名:バラ科
- 分類:落葉つる性木本
- 花期:4月~5月
- 果期:6月~7月
ラズベリーはフランボワーズというフランス名でも有名なキイチゴです。赤く熟した実は甘く瑞々しく、香りの良い果物です。
ブラックベリー

- 学名:Rubus
- 科名:バラ科
- 分類:落葉つる性木本
- 花期:5月~6月
- 果期:6月~8月
ブラックベリーは名前の通り真っ黒なキイチゴ。果実は瑞々しくて甘いのが特徴です。
ヤマモモ

- 学名:Myrica rubra
- 科名:ヤマモモ科
- 分類:常緑高木
- 花期:3月~4月
- 果期:6月~7月
ヤマモモは日本の山野に自生する花木です。果実には甘味がありますが、タネが大きいので食べるときには注意が必要です。
フサスグリ

- 学名:Ribes rubrum
- 科名:スグリ科
- 分類:落葉低木
- 花期:4月~5月
- 果期:6月~7月
フサスグリはレッドカラントとも呼ばれる果樹です。酸味が強いので、生食よりもジャムなどに加工して楽しみます。
ブルーベリー

- 学名:Vaccinium corymbosum
- 科名:ツツジ科
- 分類:落葉低木
- 花期:4月
- 果期:6月~8月
ブルーベリーは青黒い果実が特徴のツツジ科の花木です。ブルーベリーは同一系統の2品種を近くに植えておくと結実しやすくなると言われています。
ザクロ

- 学名:Punica granatum
- 科名:ミソハギ科
- 分類:落葉高木
- 花期:6月~7月
- 果期:9月~10月
ザクロは宝石のような果実が美しい果樹です。ザクロの果実は瑞々しく甘く、香りが良いのが特徴です。
ヤマボウシ

- 学名:Cornus kousa
- 科名:ミズキ科
- 分類:落葉高木
- 花期:6月~7月
- 果期:9月~10月
ヤマボウシの秋に熟す実は食べることができます。しゃりしゃりとして甘味の強い果物です。
栗(クリ)

- 学名:Castanea crenata
- 科名:ブナ科
- 分類:落葉高木
- 花期:5月~6月
- 果期:9月~10月
栗(クリ)は秋の味覚の代表です。栗の渋皮剥きは根気のいる作業ですが、やり遂げた達成感と栗(クリ)のおいしさは何ものにも変えられません。
クランベリー

- 学名:Vaccinium macrocarpon
- 科名:ツツジ科
- 分類:常緑つる性木本
- 花期:5月~6月
- 果期:9月~12月
長く伸びたつるの先に、ころころとした赤い実をつけるクランベリー。クランベリーの実は酸味が強く生食できません。ジャムやジュースに加工します。
キウイフルーツ

- 学名:Actinidia chinensis
- 科名:マタタビ科
- 分類:落葉つる性木本
- 花期:5月~6月
- 果期:10月~11月
キウイフルーツは金色の産毛で覆われたようなフォルムが特徴の果物です。中の果肉は爽やかなグリーンで甘味と酸味があります。
ガマズミ

- 学名:Viburnum dilatatum
- 科名:レンプクソウ科
- 分類:落葉高木
- 花期:3月~5月
- 果期:10月
ガマズミは赤い粒々とした果実が美しい庭木です。ガマズミの実は酸味が強く生食せずにジュースや果実酒にして楽しみます。
ムベ

- 学名:Stauntonia hexaphylla
- 科名:アケビ科
- 分類:常緑つる性木本
- 花期:5月
- 果期:10月~11月
ムベはアケビの仲間のつる性植物。アケビとの違いは常緑であること、果実が割れないことです。昔は不老不死の果物と言われ珍重されていたそうです。
クコ

- 学名:Lycium chinense
- 科名:ナス科
- 分類:落葉低木
- 花期:9月~10月
- 果期:10月~11月
クコの実は秋に赤く熟します。昔から漢方や薬膳料理などで利用されてきました。乾燥させたものを料理やお菓子に使用します。
カボス

- 学名:Citrus sphaerocarpa
- 科名:ミカン科
- 分類:常緑低木
- 花期:5月~6月
- 果期:8月~10月
カボスは晩夏から秋に流通するミカン科の果物です。甘味はなく、酸味と爽やかな香りが特徴です。
ユズ(柚子)

- 学名:Citrus junos
- 科名:ミカン科
- 分類:常緑低木
- 花期:5月~6月
- 果期:10月~12月
黄色のちょっとぼこぼことした果皮が特徴のユズ(柚子)。香りが良いのが特徴です。料理の香り付けや彩りに使用します。
ダイダイ(橙)

- 学名:Citrus aurantium
- 科名:ミカン科
- 分類:常緑低木
- 花期:5月~6月
- 果期:11月~1月
ダイダイ(橙)は橙色の語源となっている果実です。明るい黄味の強いオレンジ色が特徴です。香りが良いので料理の香り付けに使用されます。
レモン

- 学名:Citrus limon
- 科名:ミカン科
- 分類:常緑低木
- 花期:4月~7月
- 果期:11月~3月
レモンは地中海沿岸が原産のミカン科の果樹です。爽やかな香りと酸味が特徴です。
キンカン(金柑)

- 学名:Fortunella
- 科名:ミカン科
- 分類:常緑低木
- 花期:7月~8月
- 果期:12月~3月
キンカン(金柑)は直径3cm程度と小さく、丸みを帯びた果実が可愛い果樹です。キンカン(金柑)の実は果皮を食べます。
実のなる木|初夏~夏
アオハダ

- 学名:Ilex macropoda
- 科名:モチノキ科
- 分類:落葉高木
- 花期:4月~5月
- 果期:8月~9月
アオハダは夏に赤い実をつける落葉高木です。
サンゴジュ

- 学名:Viburnum odoratissimum
- 科名:レンプクソウ科
- 分類:常緑高木
- 花期:5月~6月
- 果期:8月
サンゴジュは真赤な果実をブドウのように枝から実らせます。
サネカズラ(ビナンカズラ)

- 学名:Kadsura japonica
- 科名:マツブサ科
- 分類:常緑つる性木本
- 花期:7月~8月
- 果期:9月~11月
サネカズラ(ビナンカズラ)は赤い粒々とした果実が美しいつる植物です。
実のなる木|秋
シロヤマブキ

- 学名:Rhodotypos scandens
- 科名:バラ科
- 分類:落葉低木
- 花期:4月~5月
- 果期:10月~11月
シロヤマブキは初夏に白い花が咲いた後、秋に風情のある黒い実を付けます。その実は茶花でも好まれます。
コムラサキ

- 学名:Callicarpa dichotoma
- 科名:シソ科
- 分類:落葉低木
- 花期:7月~8月
- 果期:10月~11月
コムラサキは薄紫色の小さな実を枝いっぱいに実らせるのが特徴です。
ムラサキシキブ

- 学名:Callicarpa japonica
- 科名:シソ科
- 分類:落葉低木
- 花期:6月~7月
- 果期:9月~11月
ムラサキシキブは秋に紫色の小さな実を付ける落葉低木です。
マユミ

- 学名:Euonymus sieboldianus
- 科名:ニシキギ科
- 分類:落葉低木
- 花期:5月~6月
- 果期:10月~11月
マユミはピンク色の皮が割れて朱色のタネを見せる、とても美しい庭木です。
ツリバナ

- 学名:Euonymus oxyphyllus
- 科名:ニシキギ科
- 分類:落葉低木
- 花期:4月~5月
- 果期:9月~11月
ツリバナは名前の通り、枝からぶら下げるように果実を実らせます。
ツルウメモドキ

- 学名:Celastrus orbiculatus
- 科名:ニシキギ科
- 分類:落葉つる性木本
- 花期:5月
- 果期:10月~12月
ツルウメモドキは他の木に絡まり、その先に実を付けるつる植物です。
ゴンズイ

- 学名:Euscaphis japonica
- 科名:ミツバウツギ科
- 分類:落葉高木
- 花期:4月~5月
- 果期:10月~11月
ちょっと特徴的な実をつけるゴンズイ。高木なので山野で上の方を見ながら歩いていると見つけられます。
クサギ

- 学名:Clerodendrum trichotomum
- 科名:シソ科
- 分類:落葉低木
- 花期:7月~8月
- 果期:10月
クサギという名前の由来は葉や枝を折ると臭いがするから臭木。秋につける実は宝石のような美しさです。
コナラ

- 学名:Quercus serrata
- 科名:ブナ科
- 分類:落葉高木
- 花期:5月~6月
- 果期:9月~10月
コナラの実はドングリの中の1種。落葉する少し前からたくさんのドングリを実らせます。
サンキライ(サルトリイバラ)

- 学名:Smilax china
- 科名:サルトリイバラ科
- 分類:落葉つる性木本
- 花期:4月~5月
- 果期:11月~1月
サンキライ(サルトリイバラ)は赤い実が可愛らしいつる植物です。トゲがあるので、枝を触るときには注意しましょう。
シキミ

- 学名:Illicium anisatum
- 科名:マツブサ科
- 分類:常緑高木
- 花期:1月~3月
- 果期:10月~11月
シキミの実はハーブのスターアニスによく似ています。似ていますがシキミの実は有毒なので食べないようにしましょう。
ノイバラ

- 学名:Rosa multiflora
- 科名:バラ科
- 分類:落葉低木
- 花期:5月~6月
- 果期:9月~11月
秋に赤く熟すノイバラの実は小さく控えめな可愛らしさです。
オトコヨウゾメ

- 学名:Viburnum phlebotrichum
- 科名:レンプクソウ科
- 分類:落葉低木
- 花期:4月~5月
- 果期:10月~11月
オトコヨウゾメは秋に赤い実を付ける落葉低木です。
カクレミノ

- 学名:Dendropanax trifidus
- 科名:ウコギ科
- 分類:常緑低木
- 花期:7月~8月
- 果期:11月
黒い実が特徴的なカクレミノは常緑なので目隠しとしても好まれます。
シルバープリベッド

- 学名:Ligustrum sinense ‘Variegatum’
- 科名:モクセイ科
- 分類:常緑低木
- 花期:5月~6月
- 果期:10月~12月
シルバープリベッドは春に香りの良い白い花を咲かせ、秋には黒い実を実らせます。
実のなる木|冬
ソヨゴ

- 学名:Ilex pedunculosa
- 科名:モチノキ科
- 分類:常緑高木
- 花期:5月~6月
- 果期:10月~12月
ソヨゴは秋から冬に真赤な実を実らせます。
クロガネモチ

- 学名:Ilex rotunda
- 科名:モチノキ科
- 分類:常緑高木
- 花期:6月
- 果期:11月~12月
クロガネモチは上の枝の方に赤い小さな実を実らせます。
ネズミモチ

- 学名:Ligustrum japonicum
- 科名:モクセイ科
- 分類:常緑高木
- 花期:5月~6月
- 果期:11月~12月
ネズミモチは光沢のある葉と黒い実が特徴的な庭木です。
ピラカンサ

- 学名:Pyracantha
- 科名:バラ科
- 分類:常緑低木
- 花期:5月~6月
- 果期:11月~2月
ピラカンサは枝の先に赤い実をたわわに実らせます。
ヤブコウジ

- 学名:Ardisia japonica
- 科名:サクラソウ科
- 分類:常緑低木
- 花期:7月~8月
- 果期:10月~1月
ヤブコウジは樹高10~30cm程度の低木で、秋から冬に赤い実を付けます。
セイヨウヒイラギ

Adobe Stock
- 花期:5月~6月
- 果期:11月~1月
クリスマスの頃に赤い実を付けるのは、このセイヨウヒイラギです。
センリョウ(千両)

- 学名:Sarcandra glabra
- 科名:センリョウ科
- 分類:常緑低木
- 花期:6月
- 果期:11月~1月
センリョウ(千両)はお正月飾りに欠かせない冬に実を付ける庭木です。
ナンテン(南天)

- 学名:Nandina domestica
- 科名:メギ科
- 分類:常緑低木
- 花期:6月~7月
- 果期:11月~2月
ナンテン(南天)はその名前から難を転ずると言われ、縁起物とされている庭木です。
マンリョウ(万両)

- 学名:Ardisia crenata
- 科名:サクラソウ科
- 分類:常緑低木
- 花期:7月~8月
- 果期:11月~2月
マンリョウ(万両)はお金にちなんだ名前から縁起が良いと言われている庭木です。
実のなる木は、食べられるものや見て美しいものなど様々です。気になる木は見つかりましたか。一年を通して実のなる木はたくさんあります。お散歩しながら実のなる木を探す楽しみが増えますように。
▼編集部のおすすめ