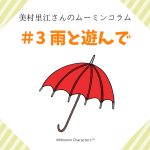スミレ(菫)の花言葉|種類、花の特徴と花言葉の由来、色別の花言葉
更新
公開

スミレ(菫)の花言葉と由来、色別の花言葉、種類や花の特徴についてご紹介。スミレ(菫)は道端にひっそりと咲き、春を教えてくれる可憐な花。
目次
- スミレ(菫)の花言葉
- スミレ(菫)の色別の花言葉
- スミレ(菫)が誕生花になっている日
- スミレ(菫)について|基本情報
- スミレ(菫)とは|花の季節と特徴
- スミレ(菫)の花言葉の由来
- スミレ(菫)の種類
- スミレ(菫)の育て方
スミレ(菫)の花言葉

スミレの花言葉は「謙虚」「誠実」
スミレ(菫)の色別の花言葉

紫のスミレの花言葉は「貞節」「愛」
白いスミレの花言葉は「あどけない恋」「無邪気な恋」
黄色いスミレの花言葉は「田園の幸福」「つつましい喜び」
ピンクのスミレの花言葉は「愛」「希望」
スミレ(菫)が誕生花になっている日

スミレは、1月9日の誕生花です。
スミレ(菫)について|基本情報
| 科・属 | スミレ科・スミレ属 |
| 和名 | 菫 |
| 英名 | Violet |
| 学名 | Viola (Viola mandshurica) |
| 原産地 | 日本 |
| 開花期 | 3月~5月 |
スミレ(菫)とは|花の季節と特徴

スミレとは、スミレ科スミレ属の多年草。世界の温帯に400種類が存在していると言われています。そのなかでも56種類が自生する日本はスミレ王国です。
スミレという名前はスミレ属の総称として使われていますが、厳密には Viola mandshurica という種類を指す名称です。Viola mandshurica は、日本原産のスミレで、濃い紫色の花が美しい種類です。他のスミレ類と区別するためにニホンスミレと呼ばれることもあります。
スミレの花の季節
スミレの花が咲く季節は、3月~5月頃。まだ風の冷たい早春に早咲きのスミレが咲き始め、その後5月頃まで次々と花を咲かせ続けます。
桜の花が咲き誇り、みんなが頭上の桜に見とれている頃に、スミレの花は足元でひっそりと花を咲かせているのです。
スミレの花の特徴と名前の由来
スミレの花の特徴は、花径1~2cm程度、色は紫、薄紫、ピンク、白などで、花びらは5枚、花の後ろに距(きょ)という突起があり、この中に蜜が入っています。うつむくように咲く姿が印象的です。
スミレという名前の由来は、花のフォルムが「墨入れ」という大工道具に似ているからだと言われています。
スミレ(菫)の花言葉の由来

スミレの花言葉は、ギリシャ神話に由来します。
一人の可憐な娘が、太陽神アポロンから求愛されて困っていました。アポロンはとても情熱的で、困っている彼女を熱烈に追いかけます。乙女の味方である女神ディアナが、彼女の姿を小さなスミレの花に変え、草むらの中に隠して救ってあげたそうです。
スミレの花は草丈低く、草むらのなかで太陽の視線から身を隠すようにうつむいて咲きます。このことから、「謙虚」という花言葉がついたとされています。
スミレ(菫)の種類
スミレ(ニホンスミレ)

- 学名:viola mandshurica
- 花色:濃い紫
日本に昔から自生しているスミレです。ニホンスミレと呼ばれることもあります。濃く深い紫色の花を咲かせます。民家に近い公園や道端から明るい山野まで自生している身近な場所で見かけるスミレです。
タチツボスミレ

- 学名:Viola grypoceras
- 花色:淡い紫
タチツボスミレは、山野や公園、道路脇など身近な場所で見かけるスミレです。名前は株元から花茎を立ち上げて咲くことに由来します。
コスミレ

- 学名:Viola japonica
- 花色:淡い紫
コスミレは、淡い紫色のスミレ。種小名が japonica であるように、日本原産のスミレです。山野の落葉樹の足元など、明るい日陰を好みます。
アオイスミレ

- 学名:Viola hondoensis
- 花色:淡い紫
アオイスミレは、淡い紫色のスミレ。丸みを帯びたスペード型の葉が特徴です。
オオバキスミレ

- 学名:Viola brevistipulata
- 花色:明るい黄色
オオバキスミレは日当たりの良い森の中や山野に生えています。葉は大きく、スペード型をしています。花が明るい黄色なので、スミレだとわからないくらいです。
アメリカスミレサイシン

- 学名:Viola sororia
- 花色:白に薄紫、白
アメリカスミレサイシンは、外来種のスミレです。園芸用として入ってきたものが野生化した品種です。
スミレ(菫)の育て方

置き場所
スミレは、冬から春は日当たりが良く、夏は半日陰になるような落葉樹の下などを好みます。あまり日当たりが悪いと花付きが悪くなるので注意しましょう。
水やり
表土が乾いて白っぽくなったら、たっぷりと水やりをしましょう。乾燥が続くと株が弱ってしまいます。水切れに注意してください。
種まき
スミレの種まきは、採取してすぐにまきます。一度乾燥させて保存した種は、寒さに当てる必要があるので、1月~2月頃にまくようにしてください。
赤玉土小粒などに種をまき、発芽までは水を切らさないようにします。本葉が出たら、好きな鉢や花壇に定植しましょう。
種まきには園芸用培養土などではなく、栄養分のない赤玉土が向いています。
種を採取するコツ

スミレは花が咲かない時期でも種を作ります。これは閉鎖花といって、開花することなく、つぼみの中で受粉が行われ、結実するという不思議な仕組みです。

スミレの果実は出来たばかりのときはうつむくように下を向いています。熟すにつれ上を向き始め、完全に上を向くと弾けて周囲に種を飛ばします。
スミレの種を採取するなら、横向きから斜め上を向いているくらいで採取するのがベストです。
花をたくさん楽しむコツ
スミレの種を採取する予定がないのであれば、花が終わったらこまめに花がらを摘むようにしましょう。花がらを摘むことで余計な栄養を消費することがなくなり、次の花が咲きやすくなります。種は開花時期が過ぎてからでも採取できます。
▼スミレの育て方
▼スミレの関連記事
▼前向きな花言葉一覧
▼366日誕生花一覧