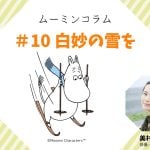ススキの花言葉|花の特徴、名前や花言葉の由来、種類
更新
公開

ススキの花言葉や花の特徴、名前や花言葉の由来、種類をご紹介!ススキは、十五夜の飾りや秋をイメージする植物。茅葺屋根の材料に使われるなど古くから日本文化の中で大切にされてきました。
目次
ススキの花言葉
ススキの花言葉は「活力」「生命力」
ススキとは|花の特徴、名前や花言葉の由来

ススキは、日本の秋を代表する植物。中秋の名月にもススキを飾るのが習わしとなっている他、秋の七草のひとつである尾花(オバナ)はススキのことを指します。昔は茅葺屋根の材料でしたが、今では利用されることもなくなり、秋の風情を感じさせる野草として愛されています。
ススキは、平地からやや高い山までの草原など日当たりの良い場所を好み群生します。痩せ地でもよく育つため、あまり土壌を選びません。秋になると河原や線路わきなどで群になって生えている様子が見られます。種が風に乗って周囲に飛んでいく他、地下茎でも増えます。
ススキは、草丈1~2mほどまで生長します。夏は青々とした葉を伸ばし、晩夏から秋にかけて細い葉と茎の間から長さ15~25cmほどの花穂を出します。夏に青々とした草原のようだったススキは、秋には輝くような黄金色に様変わりします。
ススキは冬になると枯れ、咲いていたときのような姿でドライフラワーになるので、その姿を枯れ薄(かれすすき)と呼び、季語として使用されます。ススキは冬に地上部が枯れますが、また春になると芽吹いて大きく育ちます。
ススキという名前の由来は、すくすくと立っていることにちなんでいるそうです。尾花(オバナ)というススキの別名は、花穂を動物の尻尾に見立てたことが由来となっています。
ススキの花言葉「活力」「生命力」は、暑さにも寒さにも強いススキの強い生命力に由来しているそうです。
ススキの種類
タカノハススキ

タカノハススキは、葉に縞模様が入ったススキの仲間。穂がない時期も葉を眺めて楽しめるのが魅力です。
シマイトススキ

シマイトススキは、糸のように細い葉に白斑が入ったススキの仲間。グリーンの葉のイトススキの斑入り種です。ススキよりも全体的にコンパクトなので、扱いやすいのが魅力です。
ススキの生け花やアレンジメント
お月見と言えばススキを飾るイメージですが、ススキを飾る理由は諸説あります。
稲穂に似たススキを飾って「豊作を願う」という理由。他にも、ススキは神様の拠り所であり、魔除けの効果があると伝えられてきたからという理由などがあります。
お月見以外でもススキ使うと容易に秋の雰囲気を演出できます。自宅用の切り花としてはもちろん、花束やアレンジメントにもおすすめです。
▼ススキの育て方
▼ススキの関連記事はこちら
▼前向きな花言葉一覧
▼366日誕生花一覧