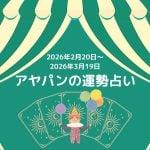カラスノエンドウ|花の季節や特徴、似た種類と見分け方
更新
公開

カラスノエンドウは緑肥にもなるお役立ち植物。花の季節や特徴、食べられるのかどうか、似た植物との見分け方、緑肥としての使い方、遊び方まで。カラスノエンドウについて、ちょっと詳しくなってみませんか。
目次
- カラスノエンドウとは?基本情報
- カラスノエンドウの花の季節と特徴
- カラスノエンドウ豆の特徴
- カラスノエンドウは食べられる?
- カラスノエンドウに似た種類と見分け方
- カラスノエンドウを緑肥にしよう
- カラスノエンドウは虫と仲良し
- カラスノエンドウで笛を作って遊ぼう
カラスノエンドウとは?基本情報

- 学名:Vicia sativa
- 植物名:ヤハズエンドウ
- 科名、属名:マメ科ソラマメ属
- 分類:越年性一年草
カラスノエンドウの特徴
カラスノエンドウは、マメ科ソラマメ属の越年草。春になると、河原や公園、畑、空地、お庭など、身近な場所で見かける、身近な野草です。直径1㎝程度の小さな花を咲かせ、巻きひげを伸ばして周囲の植物に絡みつきながら生長します。花の後には小さな実をつけ、やがて枯れていくというサイクルの植物。
葉の付け根の短毛から蜜を分泌していて、この蜜を求めて蟻が群がってくるため、他の害虫を寄せ付けないといわれています。
カラスノエンドウの名前の由来
カラスノエンドウという名前の由来は、種子が熟すと真黒になる点が鳥類のカラスを連想させることによります。漢字にすると烏野豌豆、「カラスのエンドウ」ではなく、「カラス 野エンドウ」です。カラスの為のエンドウ豆ではありませんでした。さらに補足すると、カラスがこの豆を好んで食べるというような話は聞いたことがありません。
カラスノエンドウの別名
カラスノエンドウは、標準和名をヤハズノエンドウといいます。正しくは、カラスノエンドウという名前の方が別名に当たりますが、こちらの名前で親しまれています。ヤハズ(矢筈)とは矢のお尻にある、弓に掛けるためのくぼみのことです。葉の先端に小さなくぼみがあり、それがヤハズに似ていることが名前の由来です。
変異種に葉がヤハズのようにくぼまないホソバカラスノエンドウや、巻きひげのないツルナシカラスノエンドウなどもあります。
▼カラスノエンドウの育て方はこちら
カラスノエンドウの花の季節と特徴

カラスノエンドウの花咲く季節
カラスノエンドウの花咲く季節は3月~5月です。桜のつぼみがほころび始め、ツクシが顔を出す頃、カラスノエンドウは足元で小さなマメの花を咲かせます。そのまま初夏まで次々と花を咲かせます。
カラスノエンドウは越年草です。秋に芽吹き、緑を絶やさずに冬を越して、春に花を咲かせます。冬を越して青々と繁った葉の中に咲く小さな花は、春の訪れを報せる野花として、見ている側を優しい気持ちにさせてくれます。
カラスノエンドウの花の色
カラスノエンドウの花の色はピンクと濃いピンクの2色です。2種類の花があるという意味ではなく、1つの花のなかに2色入っています。上の花びらがピンク、下の花びらが濃いピンクです。
カラスノエンドウの花のつくり
カラスノエンドウの花は5枚の花びらからできています。正面から見て一番後ろにある花びらは大きな1枚で、中央に2枚の花びらが合わさって袋のようになったもの、その外側に小さな花びらが2枚あります。中央の大きな2枚の花びらのなかに雄しべと雌しべが入っています。これはマメ科の花によく見られるつくりです。虫が蜜を吸うために中央の花びらの上に乗ると、その重みで花が開き、中の雄しべや雌しべが現れます。虫たちが花から花へと蜜を求めて移動することで、授粉が行われる仕組みになっています。
カラスノエンドウの花の特徴
カラスノエンドウの花は、葉の脇から大体1~3個くらいの花を咲かせます。花柄はなく、茎に直接花が付いているような咲き方をします。花のフォルムは、マメ科によく見られる蝶形花で、スイートピーを小さくしたような可愛らしい花です。
カラスノエンドウの豆の特徴

カラスノエンドウの種子は、小さなエンドウ豆になります。花後、長さ2~3cmのエンドウ豆を実らせ、熟すと真黒になります。

完熟したカラスノエンドウは、さやが弾けて、中から種が飛び出します。飛び出した種は周囲に飛び散り、秋に発芽するという仕組みです。残ったさやは、螺旋(らせん)状になって残ります。
カラスノエンドウは食べられる?
カラスノエンドウは、食べることができます。聞いた話では、若い芽をお浸しにしたり、小さなエンドウ豆をゆでたり、煎ったりして食べるそうです。私自身はカラスノエンドウを食べたことがないので、味や食感の説明ができないのが残念です。
カラスノエンドウに似た種類と見分け方
スズメノエンドウ

- 学名:Vicia hirsuta
スズメノエンドウは、カラスノエンドウに比べて小さいのでスズメノエンドウ。スズメが食べるからではありません。とても小さな白に近い薄紫色の花が咲きます。カラスノエンドウと同じく、小さいながらもマメの花の形をしています。
見分け方
花色が白っぽく、花や葉が小さいという点で見分けます。
カスマグサ

- 学名:Vicia tetrasperma
カラスノエンドウとスズメノエンドウの中間くらいのサイズだから、カスマグサ。ふざけているようですが、正式名称です。カラスノエンドウより一回り小さな薄紫色の花を咲かせます。楚々として、可憐な花です。頻繁には見かけるものではないので、出会えると嬉しくて小さく叫んでしまいます。
見分け方
花色が薄紫色で、花や葉がカラスノエンドウよりも小ぶりであるという点で見分けます。
ナヨクサフジ

- 学名:Vicia villosa
ナヨクサフジは鮮やかな紫色の花を咲かせる、美しいマメ科の植物です。空き地や川原などで群生している姿を見かけます。
見分け方
カラスノエンドウよりも全体的に大きく、花は穂のように長く、たくさんの花を咲かせるという点で見分けます。
イブキノエンドウ
- 学名:Vicia sepium
イブキノエンドウは北海道と、本州では伊吹山にしか生えていないといわれています。
見分け方
カラスノエンドウによく似ていますが、花色は淡いピンク色をしています。
カラスノエンドウを緑肥にしよう

カラスノエンドウは、根に根粒菌を寄生させています。これはカラスノエンドウだけでなく、マメ科の多くの植物の特徴です。根粒菌は植物にとって大切な栄養素である窒素を固定させるので、土壌が肥沃になります。さらにカラスノエンドウを抜かずに刈り取って土に漉き込めば、根や葉茎がそのまま緑肥となり、土壌が肥沃になるという仕組みです。抜いて捨ててしまうのではなく、緑肥として有効活用してみませんか。
カラスノエンドウは虫と仲良し

カラスノエンドウにはアブラムシが好んで寄ってきます。そのアブラムシを求めて、テントウムシがやってきます。アブラムシはテントウムシの大好物です。さらに虫媒花なので、蜂や蝶といった、花粉の運び屋となる虫たちが次々と訪れます。カラスノエンドウにはたくさんの可愛らしい虫が集まってきます。
カラスノエンドウで笛を作って遊ぼう

カラスノエンドウの花後、小さなエンドウ豆ができているのを見つけたら、笛を作って遊んでみましょう。カラスノエンドウの豆のさやが、ぷくぷくに膨らんでいるものがいいでしょう。
エンドウ豆の筋を取るように、さやのお尻のほうから筋とヘタを取ります。さやを開いて中の豆と白いワタを取ります。爪で擦るようにすると、簡単に取れます。そのまま唇で挟んで息を吹き入れてみてください。カラスノエンドウの笛が楽しめます。コツを掴めばきれいな高音を出せるようになります。
野草、雑草と言われ、あまり注目されないカラスノエンドウ。よく見ると花も可愛らしいし、緑肥にもなる優れた植物です。カラスノエンドウの魅力を見直してみませんか?
▼編集部のおすすめ