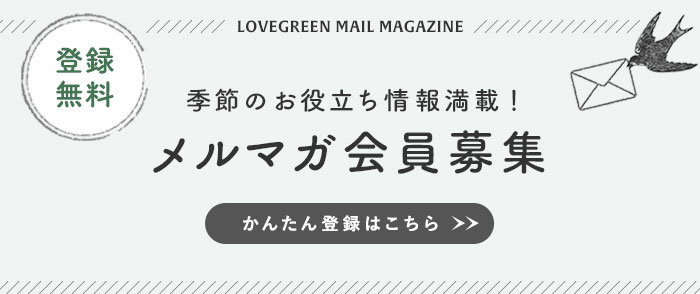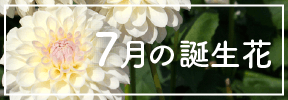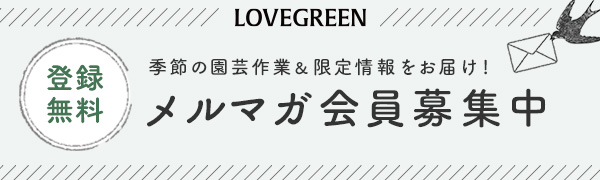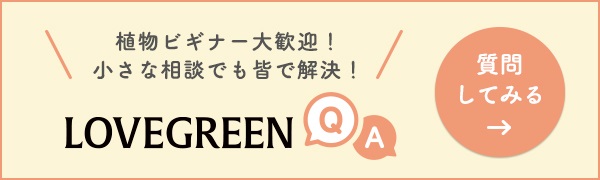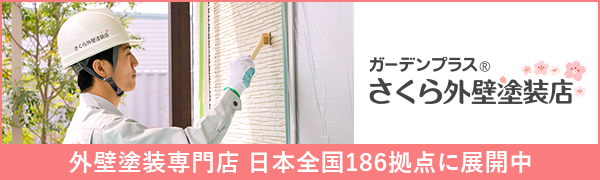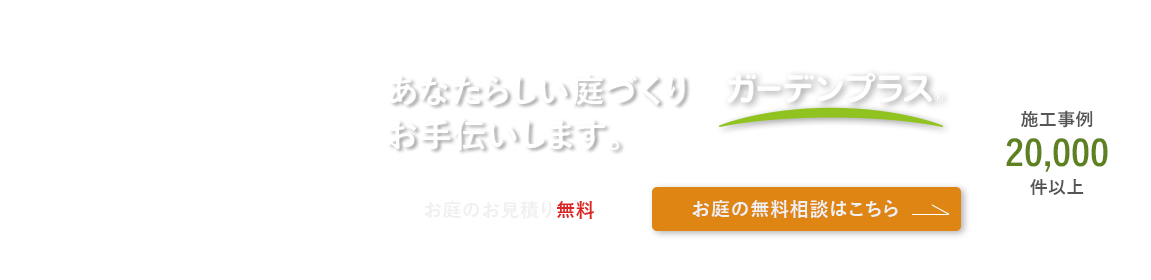9月の寄せ植えに使いたい花10選とカラーリーフ5選
戸松敦子
このライターの記事一覧

9月の寄せ植えに使いたい花とカラーリーフをご紹介!9月は残暑も厳しいけれど朝晩に吹く風は少し涼しく、秋の香りを感じるようになる季節の変わり目。秋だから楽しめる、秋の到来を感じる植物を育てて秋を思い切り満喫しましょう。9月の寄せ植えづくりのポイントや管理方法についてもお話しします。
目次
9月の寄せ植えづくりのポイント

季節の移ろいを感じるようになる9月は、日中まだ厳しい暑さが残っていたり、少し涼しい日があったり。夏の名残を感じながらも秋の香りを楽しめるようになり、暑さがやわらいでくると植物も人間と同じようにほっとした表情になって花や葉がみずみずしく変化するように見えます。
この季節の変わり目に秋に美しく咲く秋ならではの苗をそろえて、しっとりとした秋の寄せ植えを作りましょう。9月早々に寄せ植えを作っておくと、秋本番にはしっかりと根付いて華やかな鉢に生長します。
秋らしい植物を使うと、野の趣があふれる寄せ植えができます。こっくりとした色合いの花をメインに、実もの、グラス類をポイントにして苗選びをするのがおすすめです。ふわふわした感触の暖かみがある植物もいいですね。
今回紹介する花とカラーリーフの中から好みの苗を3ポット組み合わせるだけでも秋の寄せ植えができます。花色や咲き方も様々あるので好みの組み合わせを見つけられるはず。通年出回っている花やカラーリーフであれば、秋色を選んでみてはいかがでしょうか。園芸店の苗売り場にも秋の苗がたくさん並び始めているのでは。ぜひ、秋の寄せ植えを作ってお楽しみください。
▼プロトリーフガーデンアイランド玉川店の垂井愛さんに教わった秋の寄せ植えはこちら
9月の寄せ植えに使いたい花10選
ケイトウ ~ヒユ科 非耐寒性一年草~

ケイトウは、フワフワ、モコモコとした質感の花が特徴的です。ケイトウの名前は、花の形が鶏のトサカに似ていることに由来しています。花の形や大きさ、色も多種多様で、茎が長いもの、短いものとあります。美しい花色を保つためには、水やりの際は花に水をかけず、株元にたっぷりあげるようにしましょう。夏の暑さに強いですが、寒さには弱い一年草です。
ナデシコ ~ナデシコ科 耐寒性多年草~

ナデシコは四季咲き性のものが多く、常緑で耐寒性も強いので、品種や場所によってはほぼ周年にわたって観賞できるほど。耐寒性はありますが、夏の暑さは少し苦手。真夏は半日陰の風通しが良い場所を好みます。秋にはしっとりと美しく咲くので秋の寄せ植えにおすすめです。咲き終わった花をこまめに摘み、新芽を伸ばすと次々と咲きます。こっくりとした色を選ぶと秋らしいですね。
ポットマム ~キク科 耐寒性多年草~

ポットマムは鉢植え(ポット)のキク。鉢植え向きの矮性園芸品種として改良され、ポットマムという名がつけられました。キク本来の特徴として、日が短くなると蕾をつけて花を咲かせる性質をもっているため、秋になると美しく咲きます。照明が夜中ついている場所では蕾をつけないことがあるので気を付けてあげましょう。
ランタナ ~クマツヅラ科 半耐寒性常緑低木~

ランタナは、春から秋まで開花期が長い低木。秋色のランタナを選んで、手毬状のかわいい小花を次々と咲かせましょう。花の彩りが変化する様子は、まさに紅葉のようです。育てやすくとても丈夫です。
キンギョソウ ~ゴマノハグサ科 耐寒性多年草~

キンギョソウは本来は5月頃が開花の盛期で、夏の暑さに弱いため日本では一年草として扱われることが多かった植物です。品種改良により、秋にも咲くタイプやダークな葉、斑入りの葉の品種も増えています。耐寒性があるので、シックな色のキンギョソウは秋の寄せ植えにぴったりです。
センニチコウ ~ヒユ科 非耐寒性一年草~

センニチコウは、その可愛い花姿(苞)が切り花やドライフラワーとしても好まれています。苞の色は紅紫色やピンク、赤、白などがあり、鮮やかな花色が長期間楽しめます。暑さや乾燥に強く、寒さに弱い一年草です。
センニチコボウ ~ヒユ科 半耐寒性多年草~

センニチコボウは、センニチコウを小さくしたような可愛い花をたくさん咲かせます。花穂の大きさは、5~10mmほど。花持ちが良く、寄せ植えに使うとメインの花を引き立てる花としても大活躍したり、逆にメインの花にセンニチコボウの可憐な可愛らしさが引き立てられることも。ふんわりとした優しい風情を感じられます。
チェッカーベリー ~ツツジ科 耐寒性常緑低木~

チェッカーベリーは、初夏から夏に白い釣り鐘形の花を咲かせ、秋に赤い実をつける低木。草丈が低くこんもりと茂り、華やかな実が冬の間中楽しめるので、秋から冬の寄せ植えにぴったりです。光沢のあるグリーンの葉が、寒くなると少しずつ赤銅色に変わっていく姿からも秋を感じることができます。
アメジストセージ(サルビア・レウカンサ) ~シソ科 耐寒性多年草~

アメジストセージは、ふわふわとした質感の花姿が人気の多年草。実は、秋に楽しむベルベットのような質感の部分は花ではなくガクです。花は、ガクから突き出すようにして咲きます。薬効のあるセージとは異なり観賞用のセージとして親しまれています。シルバーグリーンの葉もとても美しいです。
フランネルフラワー ~セリ科 非耐寒性多年草~

![]()
フランネルフラワーは、花も葉もふわふわした感触の多年草。細かい毛がびっしりと生えていて、まるでネルシャツの素材であるフランネルを触った時の感触に似ていることが、その名前の由来といわれています。暑さ、寒さにやや弱くどちらかというとデリケートなところがあるので、秋の間にそのふわふわした可愛い姿を思い切り楽しみたい植物です。
▼グリーンギャラリーガーデンズの市原璃彩さんに教わった、ケイトウを使った寄せ植えはこちら
9月の寄せ植えに使いたいカラーリーフ5選
アルテルナンテラ ~ヒユ科 非耐寒性多年草~

アルテルナンテラは葉色がカラフルで美しく、大きさや草姿も様々。横に広がるほふく性のもの、こんもりと茂るもの、木立ち性に育つものなどがあるので、作りたい寄せ植えのイメージに合わせてタイプを使い分けましょう。寒さには弱いので戸外では一年草扱いとされています。
ハツユキカズラ ~キョウチクトウ科 耐寒性木本~

ハツユキカズラは新しい葉にピンク色と白の斑が入る姿が美しい植物。斑の入り方は生長するにしたがって変化し、新芽は濃いピンク色。だんだんピンク色が薄くなっていき、緑色に白の斑が入るようになり、やがて緑色になります。寒くなってくると紅葉する様子も美しいです。暑さ寒さに強く耐陰性もあり、とても丈夫です。
ヒューケラ ~ユキノシタ科 耐寒性多年草~

ヒューケラは葉色の種類が豊富で、丸い葉がふんわり重なるように茂り人気があります。寒さにも強く耐陰性もあり、ほとんど手がかからずよく育ちます。秋色のタイプを選ぶと秋の寄せ植えにぴったりです。色違いのヒューケラを3種類合わせるだけでもボリュームのある秋色の寄せ植えが作れます。
ペニセツム(ペニセタム) ~イネ科 半耐寒性多年草~

ペニセツムは、猫じゃらしのような穂が風に揺れる草姿が美しいグラス類。草色は明るいグリーンから濃いグリーン、銅葉まで様々あります。寄せ植えの背景となり、秋の風情を感じさせてくれます。
モミジバゼラニウム ~フウロソウ科 半耐寒性宿根草~

モミジバゼラニウムは、名前のように葉の形がモミジの葉によく似ています。花は星形に咲きますが、ゼラニウムの花と比べるとそれほど華やかさはないので、美しい葉をメインで楽しむことをおすすめします。暑さ寒さにやや弱く、ゼラニウムよりも少しデリケートなので、秋にその美しさをたっぷり堪能しましょう。
▼秋色の育てるリースの作り方はこちら
9月の寄せ植えの管理ポイント
置く場所
寄せ植えは屋外の風通しの良い日なた~半日陰に置きます。
水やり・肥料
雨が降って土が湿っているときを除き、土が乾いたら株元にたっぷりと水を与えましょう。
植え付けるときに肥料入りの培養土を使った場合は、肥料は1カ月後から与えます。
花がら取り・切り戻し
咲き終わった花は見た目も悪く、病害虫の発生も促すのでこまめに取ります。
育ちすぎて姿が乱れてしまったときは、軽く切り戻して再び美しく楽しみます。切り戻しに合わせて薄めの液肥を施すと、新芽の生長が良くなります。 切り戻した部分は、切り花として部屋に飾ってもいいですね。
冬越し
秋の寄せ植えは、寒さに弱く一年草扱いされている植物を使うこともあります。そのため、9月につくった寄せ植えは寒さが厳しくなる頃まで全体が美しく保てれば成功といえます。寒さに弱い植物はそのままにしておくと枯れてしまいますが、多年草や宿根草であれば冬の間だけ室内に取り込めば冬越しできます。寒さに強い植物だけ屋外で残し、次に作る寄せ植えに再利用する方法もあります。
▼寄せ植えをきれいに手直しする方法はこちら
▼渋谷園芸の樺澤智江さんに教わった、秋のグラスを使った寄せ植えはこちら
▼ガーデンセンターさにべるの間室みどりさんに教わった、3ポットでできる秋の寄せ植えはこちら
関連ワード
今月のおすすめコンテンツ
「9月の寄せ植えに使いたい花10選とカラーリーフ5選」の記事をみんなにも教えてあげよう♪