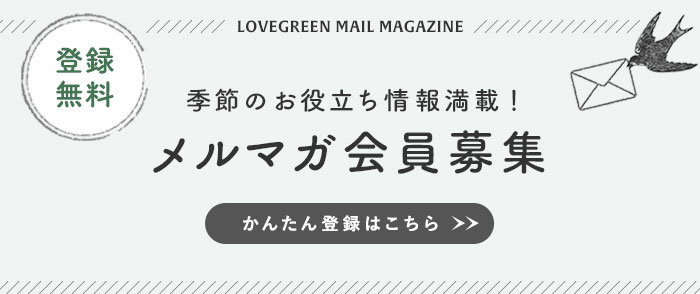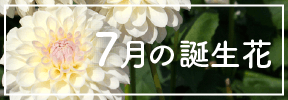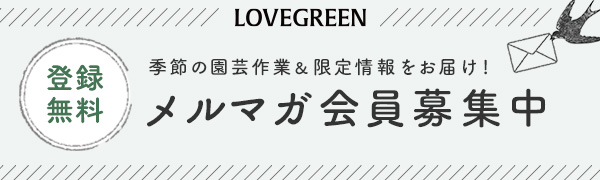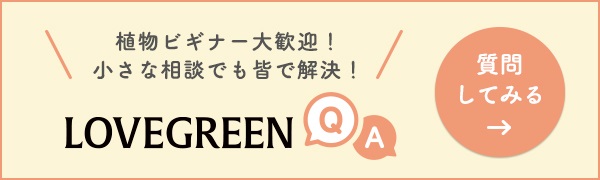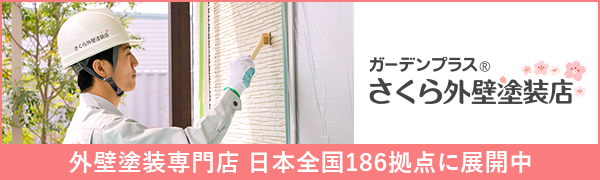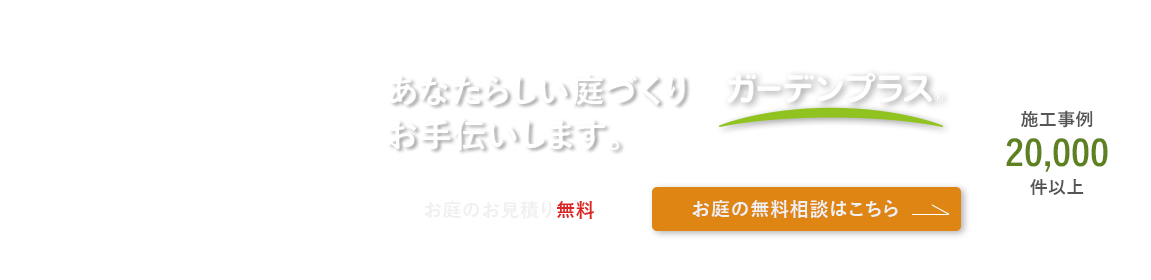8月の寄せ植えにおすすめの花12選
戸松敦子
このライターの記事一覧

8月の寄せ植えにおすすめの草花をご紹介!
8月は人間もぐったりするような暑い日が続き、日差しが強い日中は植物も暑さに耐えているように見えるほど。でも、夕方涼しくなってからの水やりタイムは人も植物もほっとする癒しの時間ですよね。そんな8月は、暑さに負けずに咲き続ける花や、高温多湿を好む観葉植物、丈夫で涼し気なカラーリーフを使って寄せ植えを作りましょう。8月の寄せ植え作りのポイントや管理方法についてもお話しします。
目次
8月の寄せ植え作りのポイント
暑さに強い草花の寄せ植え

8月は、暑さに強い草花を使って寄せ植えを作ると安心して育てられます。うっかり水やりを忘れてしまって花が下を向いてしまっても、根が枯れていなければ、水やりして日陰で休ませると花首を立ち上げて元気を取り戻します。
強い日差しがぴったりなルドベキアは、パッと目を引く大輪の花を咲かせ、まるで絵画のように芸術的な雰囲気を作ってくれるので、8月の寄せ植えのメインの花としておすすめです。
寄せ植えに使った草花
▼寄せ植えの基本についてはこちら
▼植物と暮らすとどうして癒されるの?ガーデニングの魅力についてはこちら
イエロー×ブルーのコントラスト

こちらは、反対色であるイエローとブルーのコントラストを活かして、白い小花と明るい斑入りの小葉を合わせた夏らしい組み合わせです。ブリキの器に4ポット仮置きしていますが、草花用の培養土を使ってしっかりと植え付けた方がしっかり根付いて大きく育ちます。
寄せ植えに使った草花
▼寄せ植えの疑問はこれを読んで解決!
▼ポットのまま飾る方法はこちら
小花とカラーリーフ

暑いときは、逆にあまり派手な色を使わずに、楚々とした小花や小葉を集めて作る寄せ植えも暑苦しくなく涼しくて私は好きです。そんな組み合わせの時は、小輪のニチニチソウが堂々とメインの花になります。
寄せ植えに使った草花
▼数種類のカラーリーフで作る育てるリースはこちら
8月の寄せ植えにおすすめの草花12選

それでは、8月の寄せ植えにおすすめの草花を紹介していきます。暑い中でも次々咲くものや、高温多湿を好むもの、丈夫で涼し気なカラーリーフを集めました。前回紹介した「7月の寄せ植えにおすすめの花12選」の植物は、もちろん8月にも使えるので合わせて参考にしてみてくださいね。
ルドベキア ~キク科 非耐寒性一・二年草、または耐寒性多年草~
オータムカラーズ

ルドベキアは北アメリカ原産の一・二年草、または多年草。暑い夏にぴったりの華やかで見ごたえのある花です。花期は6月~10月頃で、品種が豊富で花の大きさは、直径3~4cmくらいから10cm以上にもなるものがあります。草丈も40~150cmほどと幅広く、花色は黄色、茶色、レンガ色、アンティークカラー、複色など様々です。八重咲きタイプもあります。日当たりと風通しの良い場所を好みます。
写真の少しオレンジがかったシックなブラウン系のルドベキアは、「オータムカラーズ」。オータムカラーズは、耐寒性のある多年草タイプのルドベキアなので、地上部を枯らして越冬し、春に再び芽吹きます。
トト・ゴールデン

写真の黄色いルドベキアは「トト・ゴールデン」。トトはコンパクトな草姿のルドベキアです。側枝を次々と出すので、たくさんの花を長期間咲かせます。
▼ルドベキアのさらに詳しい育て方はこちら
▼ルドベキアの関連記事はこちら
メランポジウム ~キク科 非耐寒性一年草~

メランポジウムは4月~11月頃の長い期間花を咲かせる、暑さに強く丈夫で育てやすい植物です。こんもりと茂った株に、黄色い小さな花を休みなく咲かせます。花が咲き終わると、その上に新芽が伸びて次の花が咲くので、特に花がら摘みをしなくてもいつもきれいな株姿に整います。
▼メランポジウムの花言葉はこちら
ブルーサルビア ~シソ科 非耐寒性一年草~

ブルーサルビアは、ラベンダーに似た青い花を5月~11月頃まで咲かせます。丈夫で暑さに強いことから、夏から秋にかけて使う花苗として人気があります。原産地では宿根草ですが、寒さに弱いため日本では一年草として分類されています。
▼ブルーサルビアについて詳しくはこちら
ニチニチソウ’夏花火’ ~キョウチクトウ科 非耐寒性一年草~

ニチニチソウ’夏花火’は、ニチニチソウの小輪タイプ。普通のニチニチソウよりも花のサイズが小さい特徴があります。5月~10月頃、可愛い小花が花火のように次々と咲き広がります。白い花びらで中心が赤いからでしょうか、ホワイトレッドアイという名もついています。

日当たりと風通しが良い場所を好みます。本来は多年草ですが、寒さに弱いため日本では一年草扱いされていることが多いです。ルドベキアなど、大きく華やかな花と合わせると、ニチニチソウ’夏花火’の可憐な美しさが強調されて互いに引き立て合います。
▼ニチニチソウについて詳しくはこちら
ネコノヒゲ ~シソ科 非耐寒性一年草~

ネコノヒゲは6月~11月頃、ネコのヒゲを連想させるような花を咲かせます。長い雄しべと雌しべがやや上向きにピンと反る花姿はとてもユニークです。花色は真っ白と薄紫色があります。黒みを帯びた茎と花とのコントラストが美しく、様々な草花と合わせやすいです。
風通しの良い日なた~半日陰と水はけの良い用土を好みます。本来は多年草ですが、寒さに弱いため日本では一年草として扱われています。
▼ネコノヒゲのさらに詳しい育て方はこちら
ポーチュラカ ~スベリヒユ科 非耐寒性一年草~

ポーチュラカは5月~10月頃、ピンク、赤、橙、黄、白などカラフルな可愛い花を次々と咲かせます。多肉質の葉と茎をもち、暑さや乾燥に強い花です。丈夫で育てやすく、這うように広がる性質があります。寒さに弱く日本では一年草扱いされていますが、挿し芽で簡単に増やすことができるので、9月頃に挿し芽で小苗を作って室内で冬越しすると翌年も楽しめます。

ポーチュラカは、この写真のように八重咲きタイプも出回っています。また、花だけでなく葉も楽しめる斑入りタイプも出てきています。
▼ポーチュラカのさらに詳しい育て方はこちら
▼ポーチュラカの花言葉はこちら
アンスリウム ~サトイモ科 非耐寒性多年草~

アンスリウムは5月~10月頃、赤、ピンク、白、グリーン色のハート型の花を咲かせるトロピカルな雰囲気の観葉植物。花に見える華やかな部分は仏炎苞(ぶつえんほう)と言い、本当の花は仏炎苞から出る細くて黄色い突起です。
春から秋までの暖かい時期は屋外で育てる事ができ、寄せ植えにも使えます。ただ、夏の強い直射日光に当てると葉焼けしてしまうので、半日陰か明るい日陰で管理しましょう。寒くなる前に室内に取り込むと周年楽しめます。
▼アンスリウムのさらに詳しい育て方はこちら
▼渋谷園芸の樺澤智江さんに教わったアンスリウムを使った寄せ植えはこちら
クルクマ ~ショウガ科 非耐寒性多年草(球根)~

クルクマは7月~9月頃、白やピンク、グリーンなどの爽やかで可憐な花を咲かせます。花の形は蓮を思わせるような姿をしていますが、花に見える部分は花ではなく包葉(ほうよう)といって、花を包んでいる葉です。この包葉の中に小さな花が咲いています。寒さに弱いので、球根は寒くなる前に掘り出し、10℃以下にならない場所で保管して春に再び植え付けます。
▼クルクマのさらに詳しい育て方はこちら
▼クルクマの花言葉はこちら
アンゲロニア ~ゴマノハグサ科 非耐寒性一年草~

アンゲロニアは5月~10月頃、小さな花を次々と咲かせます。茎は直立して生長し、茎の先端や葉の付け根に穂状の花をつけます。花色は紫色やピンク、白、二色混ざったタイプなどがあります。くせが無い爽やかな花なのでどんな花とも合わせやすいです。
アンゲロニアは夏の高温に強く、半日陰でも花を咲かせるなど丈夫な植物ですが、寒さに弱いので日本では一年草として扱われることが多い花です。
▼アンゲロニアのさらに詳しい育て方はこちら
▼はな*いとし*こいし主宰中島紀子さんに教わったアンゲロニアを使った寄せ植え
スピランサス’ゴールデンたまごぼーる’ ~キク科 非耐寒性一年草~

スピランサス’ゴールデンたまごぼーる’は5月~10月頃、卵の形をした小さな可愛い花を咲かせます。その花の形から、たまごぼーるという名前が付けられました。花の中心が褐色で周りが黄色い「たまごぼーる」という品種もありますが、「ゴールデンたまごぼーる」は黄色一色の花です。

スピランサス’ゴールデンたまごぼーる’は暑さに強く、夏から秋に勢いを増して咲きます。咲き終わった花をそのままにしておくと種ができて種に栄養がいってしまいます。枯れた花を摘み取ることで、長期間咲き続けます。寒さに弱いため日本では一年草扱いされることが多い植物です。
▼スピランサス’たまごぼーる’のさらに詳しい育て方はこちら
▼スピランサス’ゴールデンたまごぼーる’の関連記事はこちら
斑入りアメリカヅタ ~ブドウ科 耐寒性落葉木本~

葉の表面に白や明るいグリーンの斑が入るアメリカヅタ。寄せ植えに使うと、切り込みが入った繊細な葉が涼し気で、可愛い新芽が伸びるやわらかな草姿もアクセントになります。花は小さくて目立ちませんが、6月~7月頃に咲きます。秋には小さな黒い実をつけ、冬に落葉して越冬します。
▼アメリカヅタのさらに詳しい育て方はこちら
▼渋谷園芸の樺澤智江さんに教わったアメリカヅタを使った寄せ植えはこちら
デュランタ・ライム ~クマツヅラ科 非耐寒性常緑低木~

デュランタ・ライムは、どちらかというと花よりもカラーリーフとして葉を楽しむデュランタです。緑葉の品種よりも花が咲きにくいですが、環境が合うと6月~10月頃にブルーの小花が集まって房になり、垂れ下がって花を咲かせます。寒さにあまり強くないので、霜に当たらないように冬越し対策が必要です。
▼デュランタのさらに詳しい育て方はこちら
▼デュランタの花言葉はこちら
8月の寄せ植えの管理ポイント

8月におすすめする、暑さに強い植物で作った寄せ植えの管理ポイントをお話しします。
置く場所
寄せ植えは、屋外の風通しの良い日なた~半日陰に置きます。暑さに強い植物でも真夏の直射日光が当たり続けると色が褪せたりすることがあるので、真夏は半日陰くらいの方が状態良く育ちます。
水やり・肥料
株元の土の乾き具合を確認して水切れしないように水やりします。雨に当たった日は、水やりはお休みしましょう。真夏の水やりは、高温多湿を避けるため、早朝や夕方以降の涼しい時間帯に行います。土の乾きが早い場合は、朝晩水やりしましょう。
ルドベキアやメランポジウムなど、花期が長いものは肥料が必要です。植え付けるときに肥料入りの培養土を使った場合は、1カ月後から液肥や固形肥料を与えましょう。
花がら取り
咲き終わった花(花がら)や古い葉は、見た目も悪く病害虫の発生の原因となるので早めに取り除きます。花がらを取ることで、次の花が咲きやすくなります。
花後の管理
茂りすぎたら全体のバランスを見て切り戻すときれいな寄せ植えがキープできます。
メランポジウムなどの一年草は寒くなったら抜き取り、寒さに強い植物に植え替えましょう。本来多年草で、寒さに弱いため日本では一年草扱いされているものは、室内に取り込んで管理すると越冬できます。
まとめ
暑さの厳しい8月は、暑い中でも咲き続ける花を上手に選んで育てると安心です。夕方、少し暑さが和らいだ時間に水やりをすると植物が気持ち良さそうに見えます。自分も夕涼みができて癒されるので、夏の夕方の水やりタイムが好きです。夏も寄せ植えを育てて植物から元気をもらいましょう!
▼編集部のおすすめ
関連ワード
今月のおすすめコンテンツ
「8月の寄せ植えにおすすめの花12選」の記事をみんなにも教えてあげよう♪