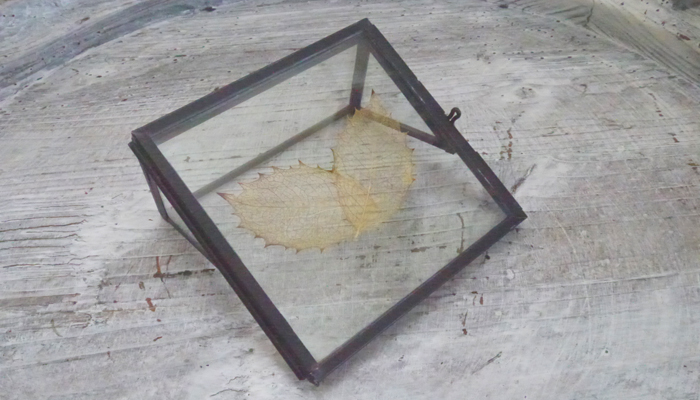オジギソウはなぜおじぎをするの?種の取り方やミモザとの関係も紹介
更新
公開

オジギソウがおじぎをする仕組みを、わかりやすく解説。種の取り方やまき方、ミモザとの関係や学名の由来も紹介します。
目次
オジギソウがおじぎをする仕組みを解説

オジギソウの特徴
オジギソウは、マメ科オジギソウ属の植物。南アメリカ原産で、熱帯地域では多年草ですが、日本では概ね一年草として扱われています。沖縄や九州のような暖かい地域では自生していることもあります。ミモザの花は一日花で、色はピンク、ネムノキやミモザのような、ふわふわとした丸いフォルムが印象的です。
オジギソウは、葉に触れると、葉が閉じて、葉の基部から下向きに垂れ下がる特徴から、「動く植物」として有名です。また、下向きに葉を閉じる様子がおじぎをしているように見えることから、オジギソウと名付けられました。
オジギソウがおじぎをする仕組み

オジギソウがおじぎをする仕組みは、刺激を受けることで、葉柄や小葉の基部にある「葉枕(ようちん)」の水分量が増減することによって起こります。

葉枕とは、葉柄や小葉の基部にある部分のことで、普段は水分を含んでふくらんでいます。オジギソウの葉が接触や振動、熱といった刺激を受けると、「刺激を受けた」という信号が葉枕に届き、中の水分が片側だけ抜けて縮みます。葉枕の片側が縮んで、反対側がふくらんでいることで、バランスが変わり、小葉が折りたたまれて閉じるという仕組みです。水分が抜けた様子は、見た目ではわかりません。
葉が刺激を受けてから、葉枕に信号が届き、おじぎをするまでにかかる時間は、コンマ数秒という速さです。続いて、ゆっくりとした速度で、周りの葉にも信号が伝達されるので、つられるように周囲の葉もおじぎを始めます。刺激が大きいと株全体に伝達されて、すべての葉が閉じてしまうこともあります。
オジギソウがおじぎをする理由
オジギソウは、刺激を受けた時以外にも、夜間、水枯れなどの理由でおじぎをします。おじぎをする理由は、虫の食害から身を守るためや、葉の熱や水分が逃げないようにするためなどといわれています。特に虫の食害については、葉を閉じてしまうと、どこに葉があるのかがわかりづらくなるほか、虫たちにとっては足場がなくなってしまい、動きづらくなることから、他の植物に移動していくというメリットがあるようです。オジギソウがおじぎをする理由は、自分の身を守るための生存戦略。植物の賢さには、本当にいつも感心させられるばかりです。
オジギソウ以外にも、ネムノキやエバーフレッシュなども夜になると葉を閉じます。これは、就眠運動と呼ばれ、夜間に葉の熱が空気中に逃げないようにするためだといわれています。
オジギソウとミモザの関係

オジギソウの学名は Mimosa pudica で、マメ科オジギソウ属の植物。私たちが日頃ミモザと呼んでいるのは、マメ科アカシア属の黄色い花を咲かせる樹木の総称です。遠い昔に様々な誤解や行き違いがあった結果、黄色い花を咲かせるアカシア属がミモザと呼ばれるようになり、そのまま定着しました。欧米でも日本でもミモザといったら、一般的に黄色い花を咲かせるミモザのことを指しますが、学名の Mimosa とは、オジギソウのことだと理解していただけると幸いです。
恥ずかしがり屋のミモザ

オジギソウの属名 Mimosa は「ものまね師」という意味で、由来は、葉がおじぎをすると周囲の葉もまねるようにおじぎをするからだとか、動物の動きをまねているからだとか、諸説あります。
また、種小名の pudica は「内気」や「恥ずかしがり屋」という意味のラテン語で、フランスでは「恥ずかしがり屋のミモザ」と呼ばれているそうです。
実際に、葉を閉じて折りたたむ様子も、ピンク色の小さな花も、頬を染めて恥ずかしがっているようで、オジギソウの特徴をよく捉えたかわいらしい名前だと思います。初めて「恥ずかしがり屋のミモザ」という名前を聞いてから、それまで以上にオジギソウがかわいく見えるようになりました。
オジギソウは木になる?

オジギソウは、大きくなっても草丈30~50cm程度と小さく、木にはなりません。小低木状草本と分類されています。
茎はしっかりと太さがあり、よく枝分かれする様子が低木のようです。ただし、じっくり観察すると、木質化することはないので、草本であることがわかります。また、茎や葉の基部に細かい毛やトゲがあります。指や手に刺さるとそれなりに痛いので、植え替えや手入れの際には、注意が必要です。
オジギソウの種の取り方、育て方

種の採り方
オジギソウは、夏にピンク色のふわふわとした花を咲かせ、その後金平糖のようなフォルムの実を付けます。茶色く熟した実は乾燥して崩れやすいので、そっと収穫しましょう。
種の保存方法
収獲したオジギソウの種は、紙の封筒や不織布の袋などに入れて、通気性の良い冷暗所で保管します。冷蔵庫の中でも良いでしょう。
種まき
オジギソウの発芽適温は25℃です。種まき適期は5月~6月頃、気温が十分に上がってから行います。種まき後は軽く土をかけ、乾燥させないように水やりしましょう。
通常10日~2週間程度で発芽するので、本葉が2枚になったら鉢に植え替えます。
場所・用土
日当たりの良い場所を好みます。用土は、水はけと保水性の良い土壌を好みます。鉢植えは市販の園芸用培養土で問題なく育てられます。
水やり
表土が乾いたら水やりしましょう。乾燥すると葉が閉じてしまいます。特に鉢植えは、夏は朝と夕方に確認して、乾いていたら水やりをしてください。
肥料
植え付け時に元肥を施したら、特に追肥の必要はありません。
病害虫
風通しが悪いと、カイガラムシの被害にあうことがあります。見つけ次第、歯ブラシなどでこそぎ落とすようにしましょう。
動く植物として知られるオジギソウ。葉を触ると閉じる動作がおもしろくて、いつまでも遊んでいたくなります。童心を思い出して、オジギソウを育ててみませんか。
▼編集部のおすすめ