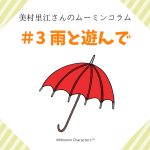編集部のこぼれ種#23「可愛い青い花が咲くオオイヌノフグリ|名前の由来にびっくり」
更新
公開

植物と一緒に暮らしているLOVEGREEN編集部の、何気ない出来事や発見、雑談などなど……日々の一部をふらっとのぞいてみてください。早春に小さな青い花を咲かせるオオイヌノフグリ。ちょっとびっくりするその名の由来を知っていますか?

寒い日が続いていますが、春の訪れを知らせるようにオオイヌノフグリが咲き始めました。
オオイヌノフグリは、ネモフィラを小さくしたような青い花を咲かせるオオバコ科の一年草。花径8~10mmくらいのとても小さな花ですが、地面一面にコバルトブルーの花が広がる様子はとても美しく、散歩中に見つけると足を止めてしばらく愛でたくなります。
▼オオイヌノフグリの育て方はこちら

オオイヌノフグリは、その可憐な花姿からは想像できないくらい丈夫で、繁殖力が強い植物です。庭や空き地、畑などに自然に生えてくるので雑草とも呼ばれていますが、雑草と言うのが失礼なくらい可愛い花が咲きます。
日当たりが好きだけれど草丈が低いため、他の草が茂らない早春の寒いうちから活動を始めるのだそうです。賢いですよね。
▼オオイヌノフグリの花言葉はこちら

そして、オオイヌノフグリという名前について。ご存知の方も多いかと思いますが、フグリは陰嚢の古語なのでオオイヌノフグリは漢字で書くと「大犬の陰嚢」。どうしてこんな可愛い花にそのような名が付いたのか不思議です。
名前の由来は、もともと日本には花径3~5mmほどの淡いピンク色の花が咲くイヌノフグリという在来種があり、外国から来た青い花が咲く近縁種は在来種より全体的に大きかったことから「大」が付けられたとのこと。ちなみに在来種のイヌノフグリの名は、花ではなく実の形から命名されたそうです。

オオイヌノフグリは、日本の植物学の父と言われる植物学者の牧野富太郎博士が発見して名前を付けたと言われています。では、在来種のイヌノフグリは誰が命名したのでしょうか?牧野富太郎博士が命名したと言う人がいたり、牧野富太郎博士が生まれる前からイヌノフグリの名は付いていたという話があったり。植物の命名の歴史を紐解いていくのも面白いなと思うこの頃です。オオイヌノフグリには「星の瞳」という素敵な別名もあったり、本当に奥深いです。
余談ですが、牧野富太郎博士をモデルにした朝ドラも始まると聞いて楽しみにしています。LOVEGREEN編集部も、練馬にある牧野記念庭園に行ってみたいという話で盛り上がっています。高知県にある牧野植物園もいつか行きたいなあと思っています。
(編集:T)