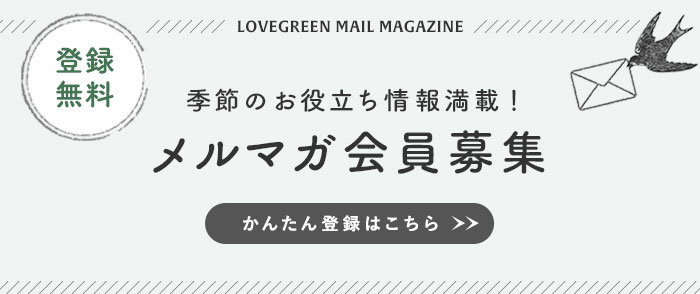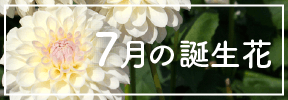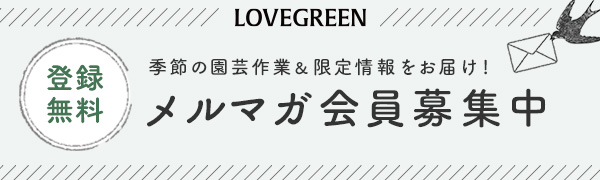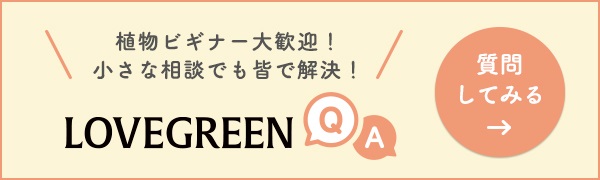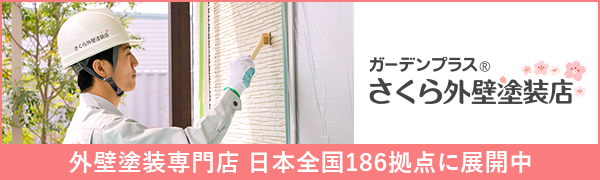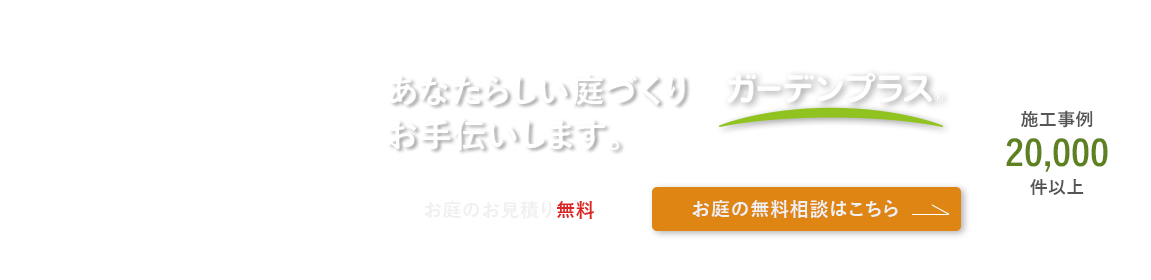お正月に飾りたい縁起のいい赤い実11種!|正月の花
山田智美
このライターの記事一覧

お正月にはなぜ赤い実を飾るのでしょうか?縁起がいいと言われている、赤い実を付ける植物を11種類紹介します。さらにお正月に赤い実を飾る理由や、赤い実が縁起がいいと言われる理由も併せてお話しします。
目次
- お正月に赤い実が縁起がいい理由とは?
- 南天(ナンテン)
- 万両(マンリョウ)
- 千両(センリョウ)
- 百両(カラタチバナ)
- 十両(ヤブコウジ)
- 一両(アリドオシ)
- 万年青(オモト)
- ピラカンサ
- クロガネモチ
- ソヨゴ
- ヒイラギは?
お正月に赤い実が縁起がいい理由とは?

お正月に赤い実が縁起がいいと言われる理由は、冬の寂しい景色の中で、一際目立つ鮮やかな赤い実は、富と繁栄を連想させるからだと言われています。
さらにお正月の縁起物と呼ばれる赤い実は常緑樹ばかり。一年を通して青々とした葉を絶やさず、冬には豊かな赤い実を実らせる植物たちは、長く続く富と繁栄の象徴として重宝されてきました。現在でもその縁起にあやかろうと、お正月に赤い実を飾る習慣が残っています。
南天(ナンテン)

- 学名:Nandina domestica
- 科名:メギ科
- 分類:常緑低木
南天(ナンテン)が縁起がいい理由
南天(ナンテン)は細く華奢な枝に笹を思わせるような細い葉をつける常緑低木です。
南天(ナンテン)が縁起がいいと言われる理由は、南天(ナンテン)という名前の音から「難を転じる」とされ、災い事を遠ざけ福を呼ぶとされてきました。
切り花としての流通も多く、12月の半ば頃から花き市場でも多く出回るようになります。
南天(ナンテン)の花言葉
- 良い家庭
- 福をなす
万両(マンリョウ)

- 学名:Ardisia crenata
- 科名:サクラソウ科
- 分類:常緑低木
万両(マンリョウ)が縁起がいい理由
万両(マンリョウ)はツヤのある葉とぶら下がるように実る赤い実が印象的な常緑低木です.
万両(マンリョウ)が縁起がいいと言われるのは、「万両」というお金の単位がついた名前がたくさんの富を連想させるから。さらに実が大きく、実付きが良いのも縁起がいいとされる理由です。
万両(マンリョウ)の花言葉
- 寿ぎ(ことほぎ)
- 陰徳
千両(センリョウ)

- 学名:Sarcandra glabra
- 科名:センリョウ科
- 分類:常緑低木
千両(センリョウ)が縁起がいい理由
千両(センリョウ)は枝の先に粒々とした赤や黄、オレンジ色の実をつける常緑低木です。万両(マンリョウ)がぶら下げるように実をつけるのに対し、千両(センリョウ)は枝の先に実を付けます。
千両(センリョウ)が縁起がいいと言われる理由も万両(マンリョウ)と同じく名前から。赤い実と同じく黄やオレンジ色の実も富を連想させるということからお正月に好んで飾られます。
毎年12月の半ばには花き市場にて「千両市」という千両(センリョウ)だけのセリが行われるほど、お正月には欠かせない縁起物とされています。
千両(センリョウ)の花言葉

黄色い実の千両(センリョウ)
- 利益
- 裕福
百両(カラタチバナ)

- 学名:Ardisia crispa
- 科名:サクラソウ科
- 分類:常緑低木
百両(カラタチバナ)が縁起がいい理由
百両はカラタチバナ(唐橘)とも呼ばれる、秋から初春にかけて赤い実を実らせる常緑低木です。万両(マンリョウ)と似ていますが違いは、万両(マンリョウ)は下向きに実を付け、百両(カラタチバナ)は上向きに実を付けます。
百両(カラタチバナ)が縁起がいいと言われる理由も万両(マンリョウ)や千両(センリョウ)と同じくその名前です。江戸時代には大流行し、斑入りなど美しい品種は高額で取引されたこともあったそうです。
百両(カラタチバナ)の花言葉
- 富
- 財産
十両(ヤブコウジ)

- 学名:Ardisia japonica
- 科名:サクラソウ科
- 分類:常緑低木
十両(ヤブコウジ)が縁起がいい理由
十両(ヤブコウジ)はヤブコウジ(藪柑子)とも呼ばれる、赤い実を付ける常緑低木です。樹高は15cmから大きくてもせいぜい30cm程度と小さな庭木です。
十両(ヤブコウジ)が縁起がいいと言われる理由も万両(マンリョウ)や千両(センリョウ)と同じくその名前。十両という名前は、万両(マンリョウ)や千両(センリョウ)と比べて樹高が小さく控え目なところから名付けられたと言われています。
十両(ヤブコウジ)の花言葉
- 明日の幸福
一両(アリドオシ)

Adobe Stock
- 学名:Damnacanthus indicus
- 科名:アカネ科
- 分類:常緑低木
一両(アリドオシ)が縁起がいい理由
万両、千両、百両、十両ときたら一両。一両と呼ばれる植物もちゃんとあります。
一両はアリドオシ(蟻通し)とも呼ばれる、冬に赤い実をつける常緑低木です。低木と言っても地面を這うように生長するほふく性です。アリドオシ(蟻通し)という変わった名前の由来は蟻を刺して通すくらい鋭い棘があることから。
一両(アリドオシ)が縁起がいいと言われる理由は、千両(センリョウ)や百両(カラタチバナ)と同じくその名前です。
万年青(オモト)

- 学名:Rohdea japonica
- 科名:ユリ科
- 分類:常緑多年草
万年青(オモト)が縁起がいい理由
万年青(オモト)は冬でも青々とした葉を絶やさない常緑多年草。常緑であることから縁起がいいとされ、特に引っ越し祝いに贈られる習慣のある鉢植えです。
さらに冬には真赤な実をぎっしりと実らせます。万年青(オモト)の赤い実は年末になると市場に出回るようになり、縁起物としてお正月の花生けに使用されます。
万年青(オモト)の花言葉
- 長寿
ピラカンサ

- 学名:Pyracantha
- 科名:バラ科
- 分類:常緑高木
ピラカンサが縁起がいい理由
ピラカンサは和名ではトキワサンザシ(常盤山査子)と呼ばれるバラ科の常緑高木。初夏に真白な花を咲かせ冬には赤やオレンジ色のな実をたわわに実らせます。
トキワサンザシのトキワ(常盤)とは永遠のこと。ピラカンサが常緑であることが由来です。常緑で実付きも良いピラカンサは縁起のいい庭木として好まれます。
ピラカンサの花言葉
- 美しさはあなたの魅力
- 愛嬌
クロガネモチ

- 学名:Ilex rotunda
- 科名:モチノキ科
- 分類:常緑高木
クロガネモチが縁起がいい理由
クロガネモチは秋から冬の間真赤な実を付ける常緑高木です。
クロガネモチはその名前が「苦労のない金持ち」を連想させるとして、縁起のいい庭木として人気があります。
クロガネモチの花言葉
- 魅力
- 寛容
- 執着
- 仕掛け
ソヨゴ

- 学名:Ilex pedunculosa
- 科名:モチノキ科
- 分類:常緑高木
ソヨゴが縁起がいい理由
ソヨゴはグリーンの葉の間からサクランボのように赤い実をぶら下げる常緑高木です。名前は漢字で書くと冬青、冬でも青々とした葉を絶やさず赤い実を付けることから縁起のいい庭木として好まれています。
ソヨゴの花言葉
- 先見の明
ヒイラギは?

- 学名:Osmanthus heterophyllus
- 科名:モクセイ科
- 分類:常緑高木
▼ヒイラギについて詳しく紹介しています。
ヒイラギは縁起がいい?
クリスマスの時期に見かける赤い実が付いたヒイラギは、クリスマスホーリーや西洋ヒイラギと呼ばれる樹木。ヒイラギ(Osmanthus heterophyllus)とは別種です。ヒイラギ(Osmanthus heterophyllus)は赤い実は付けないので、特にお正月に飾られることはありません。
ヒイラギが活躍するのは節分です。トゲのある葉が鬼の目を突くので鬼が逃げると言われ、魔除けとして玄関に飾る習慣があります。
ヒイラギは縁起がいいのか悪いのかというと、赤い実は付けないのでお正月には飾りませんが節分に魔除けとして重宝される縁起のいい庭木ということになります。
ヒイラギの花言葉
用心深さ
先見の明
お正月に赤い実が縁起がいいと言われる理由は、冬でも青々とした葉を絶やさず、鮮やかな赤い実を実らせることが富と繁栄を連想させるからです。お正月には松などの常緑樹と共に赤い実を飾って福を呼び込みましょう。
▼編集部のおすすめ
関連ワード
今月のおすすめコンテンツ
「お正月に飾りたい縁起のいい赤い実11種!|正月の花」の記事をみんなにも教えてあげよう♪