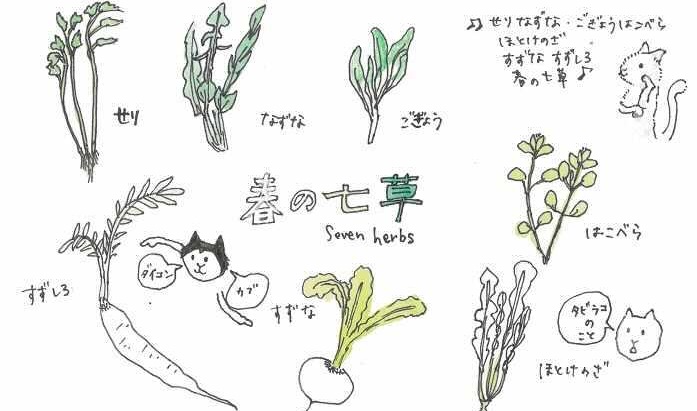お正月の花といえば?縁起のいい花、正月飾りに使われる植物一覧
更新
公開

お正月に花を飾る意味や理由、お正月の花とお正月飾りの違いをご存じでしょうか。お正月に飾りたい花の種類と、縁起がいいと好まれる理由を紹介します。日本の伝統を大切に、お正月にはきれいな花を飾って心豊かに過ごしましょう。
目次
- お正月に花を飾る意味
- お正月飾りとお正月の花の違いは?
- お正月に飾る縁起のいい花8種の意味を紹介
- お正月に飾る縁起のいい赤い実4種の意味を紹介
- お正月に飾る縁起のいい植物4種の意味を紹介
- お正月の花を飾る場所
お正月に花を飾る意味

お正月に花を飾る意味は、年神様とお客様を歓迎するためのおもてなしのためです。
お正月とは新しい年の神様をお迎えする、おめでたい行事です。家族揃って年神様と一緒に、新年の幸せと無病息災を祈ります。また、新年のご挨拶のための来客もあります。
お正月には、掃除の行き届いたきれいなお部屋に新鮮な花を飾り、年神様とお客様を歓迎しましょう。お正月の朝から目にも美しい花が部屋の中にあるだけで、幸福度も上がります。
お正月飾りとお正月の花の違いは?

![]()
お正月飾りとお正月の花の違いは、飾る目的です。お正月の花を飾る目的は、先にも書いた通り、年神様とお客様を歓迎するおもてなしのために飾ります。
お正月飾りの目的は、年神様を自宅にお招きするための目印です。そのため、前年の12月末までに家の外に飾ります。年神様は、門松やお正月飾りを目印に家々を訪れると言われています。
お正月飾りの片付け方とお正月の花の片付け方の違い

お正月飾りは、松の内(1/1~1/7、地方によっては1/15)が明けたら片付けるようにします。
近くに神社のどんど焼きと呼ばれる焚き上げに持って行きます。神社の方の話では、受付ている神社がないようであれば、白い紙に包み塩を振って処分してもよいそうです。
お正月の花はどんど焼きに持って行く必要はありません。自宅で処分しましょう。処分のタイミングも特に決まりはありません。生花ですから、花が萎れてきたら片付けるようにしましょう。その際には、短くハサミでカットして、紙に包んでから処分しましょう。せっかく新年を一緒に迎えた花です。丁寧に処分しましょう。
▼お正月飾りについて詳しくご紹介しています。
お正月に飾る縁起のいい花8種の意味を紹介
美しい花、香りの良い花、お正月に飾りたい縁起のいい花を紹介します。
梅

お正月と言えば梅、と言っても過言ではないくらい、お正月のイメージが定着している梅の花。梅がお正月に好まれるのは、まだ寒い早春から香りの良い花を咲かせるので、希望を連想させるからだそうです。他にも紅白の花を咲かせるので、縁起がいいとされています。
お正月が近づくと、枝に苔が生えた苔梅や、枝が捻られたように曲がった雲龍梅なども出回ります。
▼梅について詳しくご紹介しています。
蘭

蘭は昔から高嶺の花として、手の届きにくい高級品でした。お正月に蘭を飾るのは、お正月には高級な花を飾って繁栄を祈願することに由来しているようです。
お正月には特に香りの良い蘭を飾って、香りも楽しみたいものです。
▼蘭の育て方
菊

菊はお正月以外にも神仏のお供えに使用されるなど、神聖な花とされています。その昔、中国では菊を不老長寿の薬草としていました。それが日本に渡ってきて、長寿や若返り効果を祈願する縁起のいい花と言われるようになりました。
▼最近流通している菊についてご紹介しています。
葉牡丹(花キャベツ)

葉牡丹は冬の花が無くなる寂しい時期に、牡丹を思わせるような華やかな葉で、目を楽しませてくれる植物です。葉牡丹の葉の色を紅白に見立て、縁起物として扱います。他にも葉が幾重にも重なり合っていることから良いことが重なるとも言われています。
葉牡丹は鉢植えでも切り花でも出回ります。色が優しく、どんな花とも相性が良いのが特徴です。
▼大人気の葉牡丹の魅力!
福寿草

![]()
福寿草が縁起がいいと言われる理由は一目瞭然、その名前です。福と寿の字が名前に入っているので、とても縁起のいい花だと言われています。さらに花色の黄色が黄金を連想させることから、富をもたらす花として、古くからお正月に飾られてきました。
福寿草は本来、戸外で2月頃に開花する花ですが、お正月の頃になると鉢植えで流通するようになります。まだ寒い初春に、雪が溶け始めた地面から顔を出す福寿草の柔らかな黄色の花は、見ているだけで和むような明るさがあります。
▼福寿草の育て方
雪割草

![]()
雪割草は春を告げる花として、昔からお正月に好まれて飾られてきました。早春に小さく可憐な花を咲かせる雪割草の花色には、白の他に、ピンクや紫等があります。
福寿草と並んで春を告げる縁起のいい花とされています。
▼雪割草の育て方
水仙

水仙のなかでもニホンスイセンは、まだ寒い冬に香りの良い花を咲かせます。春そのもののようなすっきりとした芳香と、凛とした花姿があいまって、古くからお正月に飾る花として愛されてきました。
水仙の学名はNarcissus(ナルキッサス)。ギリシャ神話に登場する、水面に映る自分に恋をしてしまった美青年ナルシスの名前が由来です。中国でも水の仙人と書いて、水仙。その香りと美しい花姿によく似合うきれいな名前です。
▼水仙の育て方
蝋梅(ロウバイ)

蝋梅は、梅よりも早くに春を告げてくれる花です。カスタードクリームのような優しい黄色と蝋を刷いたような花びらの質感、さらにうっとりするくらいの甘い香りは、昔からお正月に飾る花として愛されてきました。
赤い実もそうですが、黄色という色も富や豊穣を表す色として、縁起がいいとされています。淡い黄色の花を咲かせる蝋梅も、花色と香りから縁起がいい花としてされてきたようです。
▼蝋梅の育て方
お正月に飾る縁起のいい赤い実4種の意味を紹介
お正月を迎える冬は色彩の少ない季節。冬に真赤に色付く実は豊かさの象徴であり、縁起がいいとされてきました。中でも特にお正月に好まれる縁起のいい赤い実4種を紹介します。
南天

南天が縁起がいいとされるのは、南天の名前の音と「難を転ずる」を掛けて、邪気を払うと考えらたことによります。さらに富を象徴する赤い実をたわわに付けることも縁起がいいと好まれた理由です。
▼南天の育て方
万両

![]()
万両は冬でも常緑で赤い実をつけること、さらに万両という名前も富や繁栄を表すようで縁起がいいということから、お正月の花として好まれるようになりました。
▼万両の育て方
千両

![]()
千両も同じく常緑で赤い実をつけること、千両という名前が富を表していることから、縁起が良いとされるようになりました。
千両には赤い実の他にオレンジや黄色の実もあります。万両に比べて草丈が高いので、大きな花瓶に生けるときに活躍します。
▼千両の育て方
万年青(オモト)

万年青は名前の通り、一年中グリーンの葉を絶やさないことから、縁起のいい植物とされてきました。さらに冬に真赤に色付く実は、子孫繁栄、富の象徴とも言われ、重宝されます。
▼万年青の育て方
お正月に飾る縁起のいい植物4種の意味を紹介

![]()
お正月はまだ寒い時期であるため、冬でも葉を落とさない常緑樹が珍重されてきました。中でも特に縁起がいいとされている植物4種を紹介します。
松

松は一年中、葉を絶やさない常緑樹であることから、不老不死や長寿を象徴するとされてきました。多くの植物が葉を落とす冬に葉を絶やさない松は神聖視され、魔除けの力もあると信じられてきました。クリスマスの時期に常緑樹を飾るのと同じ理由です。
竹

![]()
竹は真直ぐ上に伸び、さらに生長が早いことから、真直ぐな心と生命力の象徴と考えられてきました。竹はその生長の早さ、丈夫さ、しなやかさも相俟って、生活に密着した植物であり、神聖な植物でもあったようです。
ユズリハ

ユズリハは新しい葉が出てくる前に、場所を譲るように古い葉が落ちていくことから、子孫繁栄、代々家が続く、などの意味があるとされています。
実際のユズリハは、新しい葉が出てきても古い葉も枝に残っていることがほとんどです。それはそれで、新旧共存という解釈もできるのではないでしょうか。
裏白(ウラジロ)

ウラジロはシダ植物の仲間です。葉の表はグリーンで葉裏が白いことから、「後ろ暗い事がない」という意味を持ち縁起がいいと言われています。また、邪気を払うなどの意味もあると信じられてきました。
お正月の花を飾る場所

Adobe Stock
お正月の花を飾る場所は、玄関、リビング、床の間など、人が集まるところです。歓迎の意味を込めて、たくさんのお客様の目に触れる場所に飾るとよいでしょう。
トイレや洗面台に香りの良い花を飾るのも、お客様への素敵な心遣いです。
お正月の花は、年神様への歓迎の印であり、私たちが楽しむためのものでもあります。ここに紹介した花以外にもお正月に飾りたい花があれば、迷わず飾りましょう。新年にきれいな花を飾って、心豊かなお正月を楽しみしましょう。
▼編集部のおすすめ