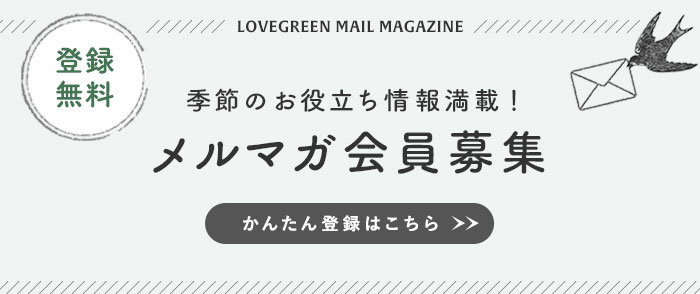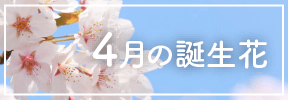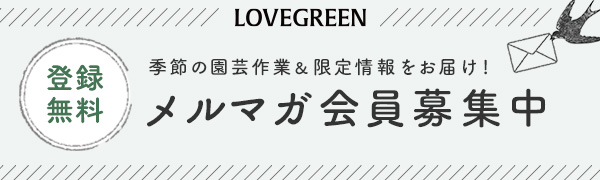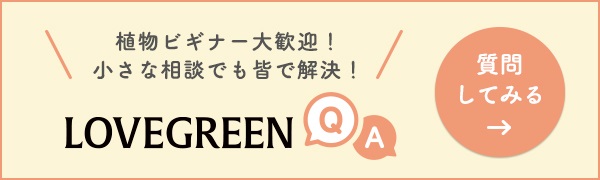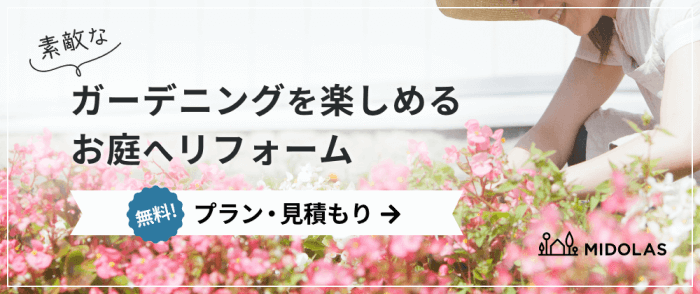100均でふきのとうの地下茎を購入!毎年収穫を目指す方法。
LOVEGREEN編集部
このライターの記事一覧

![]()
100円ショップの園芸グッズの品揃えは素晴らしいですね。いつも種類の多さに感動します。そんな100円ショップ園芸コーナーからまた一つ試してみたいものがありましたので購入してみました。この時期販売されている、アスパラ・みょうが・ふきのとう・たらの芽の株4種類です。
収穫の楽しみが2度訪れる「ふきのとう」についてご紹介します。早春のふきのとうもほろ苦くて美味しいですが、初夏から初秋まで楽しめるふきも楽しみですね。
目次
ふきのとうとは

日本原産の山菜で、春の訪れを知らせる「ふきのとう」と、梅雨時期から長く伸びた葉や葉柄(ようへい)を煮つけなどでいただく「ふき」と楽しみが2倍もある山菜です。
| 科・属 | キク科 フキ属 |
| 英名 | Giant Butterbur |
| 学名 | Petasites japonicus |
| 原産地 | 日本 |
| 出回り時期 | 3月~10月 |
| 育てやすさ | ★★★★★ |
半日陰を好み、湿気のある環境ならプランターでも十分管理できるようです。地下茎の植え付けは春と秋が主流です。今回は春から育てるふきのとうのプランター栽培をご紹介します。
ふきのとうのプランターの植え付け方

ふきのとうの地下茎
100均で購入したふきのとうです。ゴボウを短く切ったような小さい地下茎です。
地植えにして育てるとガーデニングのグランドカバーとして庭一面に広がりますが、今回はプランター栽培ですのでしっかり日頃のお手入れしながら育てましょう。
ふきのとう栽培の土の準備

特別な土を用意しなくても普通の野菜用の培養土で大丈夫。今回用意した土は、黒土・日向石(中粒)・もみ殻くん炭。
ふきのとうは比較的酸性土壌を好むので、石灰を入れる等の酸度調整をさほどしなくても十分に育ちます。肥料は有機肥料を原料にした顆粒状のものを用意しました。
ふきのとう栽培用のプランター準備と地下茎の植え付け
ふきのとうのプランターはある程度土の量が多く入る深型のものを用意しましょう。

鉢底にネットを敷いて、軽石を鉢底が隠れる程度に置きます。

ふきのとうの地下茎は横向きに置きに植えましょう。

ふきのとうの地下茎の覆土は5~10cmほど、最後にお水をしっかり与えたらふきのとうの地下茎の植え付けは完了です。
植え付け後、1年間のふきのとう栽培
ふきのとうを元気にプランターで育てるための秘訣は、「乾燥させない」「3年か4年に一回は、掘り起こし株を分けて移植する」この2点が重要です。続いて、植え付け後1年を通したふきのとうの育て方をご紹介します。
4~5月のふきのとう
日当たりが良く乾燥しやすいところはふきのとうの苦手な場所です。日陰の場所を選び、しっかり水を与えて管理しましょう。ふきのとうの可愛い芽が出てきます。
6~10月のふきのとう
今年は1年目ですのでそれほどたくさんは収穫できないと思いますが、フキの葉、葉柄(ようへい)の収穫時期です。
11~1月のふきのとう
フキの葉、葉柄(ようへい)の収穫も落ち着き、そろそろ休眠期の始まりです。ふきのとうも地上部が枯れて根の状態で冬を越す宿根草です。また2~3月に出てくるふきのとうを楽しみに、お礼肥を施しましょう。
2~3月のふきのとう

![]()
2~3月はほろ苦いふきのとうの収穫時期です。花が咲く前の蕾の状態の方が苦味が少ないので早めに収穫してください。ちなみに、ふきのとうの根は有毒なため、食さないように気を付けてください。
ふきのとうの収穫が終わった頃お礼肥を施し、梅雨以降のフキの葉、葉柄(ようへい)の収穫に備えましょう。
いかがでしたか?
プランターや畑で栽培する際は「直射日光が当たらない環境」、「湿気のある土壌を好むためしっかり水やり」この2点に注意すればとっても簡単に育てられます。
ふきのとうは日本の気候に合っているため、日本原産の山野に自生しているということが育てやすい最大のポイントです。自家製ふきのとうの天ぷら、自家製フキの味噌汁、煮物が今から楽しみですね!
▼編集部のおすすめ