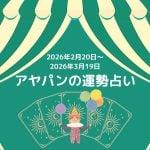ガマズミ|花の季節や特徴、種類、実の味と活用法
更新
公開

ガマズミについて、花の咲く季節や特徴、種類、実は食べられるのか、実の味と活用法、育て方、切り花でも楽しめる魅力など、詳しく紹介します。
目次
ガマズミとは? 基本情報

- 学名:Viburnum dilatatum
- 科名・属名:ガマズミ科ガマズミ属
- 分類:落葉低木
- 英名:Linden viburnum
- 花期:4月~6月
ガマズミは、ガマズミ科ガマズミ属の落葉低木。ガマズミという名前は、ガマズミ属全体を指す総称でもあり、ガマズミ Viburnum dilatatum という1つの品種を指す名前でもあります。
ガマズミは、春に真っ白な小花の集合体を枝の先に咲かせ、秋には小さな赤い実をぎっしりと丸い形に実らせます。寂しくなり始めた秋の山や森の中で、お日さまに照らされて宝石のように輝く実は、見ている人の心を奪います。いつまでも眺めていたくなるような美しさです。
ガマズミの花言葉
ガマズミの花言葉は「愛は死より強し」「結合」
ガマズミの花の特徴や咲く季節

コバノガマズミの花
ガマズミの花の特徴
ガマズミの花の最大の特徴は、小花が集合して一つの花のようなフォルムを成しているというところ。横に大きく枝を伸ばして、その先に白い小花を咲かせます。一つ一つの花は5~8mm程度、花びらは5枚に分かれていて、しべ類が飛び出すように付いています。その小花がたくさん集まって10cm程度の大きな集合花序を形作っています。白い小花が集まったできた花は、ふわっと軽やかで、見ているだけでほっとするような優しい雰囲気です。
ガマズミの花咲く季節
ガマズミの花が咲くのは、5月~6月です。早い年は4月の後半には咲き始めます。桜が終わり、藤の花の盛りも過ぎた頃が、ガマズミの花の見頃です。
ガマズミの実は食べられる? 味と活用法

ガマズミの実は食べられます。ただし、酸味が強く、生食には不向きです。
真赤に熟した宝石のような実は、見るからにおいしそうで、食べてみたくなります。実際に子供の頃、我慢できずに口に入れてみましたが、甘味はなく、酸味が強く、小さな種も入っているので飲み込むこともできず、すぐに吐き出してしまったように記憶しています。
酸味が強く、生食には不向きなガマズミの実ですが、食べてはいけないものではありません。活用法としては果実酒がおすすめ。よく洗ってからホワイトリカーに漬け込みます。作り方は、一般的な果実酒のレシピに従ってください。一緒に氷砂糖を入れて、飲みやすくすることをおすすめします。
こんなにある! ガマズミの種類
ガマズミ属にはたくさんの種類があります。ガマズミの仲間たちをご紹介します。
コバノガマズミ

- 学名:Viburnum erosum
- 科名・属名:ガマズミ科ガマズミ属
- 分類:落葉低木
- 花期:4月~6月
コバノガマズミは、花も葉も小ぶりでかわいらしいガマズミの仲間。枝や幹も華奢で柔らかな印象の木です。
ミヤマガマズミ

Adobe Stock
- 学名:Viburnum wrightii
- 科名・属名:ガマズミ科ガマズミ属
- 分類:落葉低木
- 花期:4月~6月
ミヤマガマズミは、ガマズミよりも花も実も少し大きめの近縁種です。高さも大きなものだと5mくらいになります。
ビバーナム・ティヌス(トキワガマズミ)

- 学名:Viburnum tinus
- 科名・属名:ガマズミ科ガマズミ属
- 分類:常緑低木
- 花期:4月~6月
ビバーナム・ティヌスは、トキワガマズミという別名でも知られている品種。トキワ(常盤)と名につくように、常緑のガマズミです。春には毬のような白い花を咲かせ、秋から冬には光沢のある黒い果実をつけます。切り花として人気の花材です。春先に「ガマズミ」の名前で花屋さんの店頭に並ぶピンク色のつぼみが付いた枝物は、このビバーナム・ティヌスです。
ビバーナム・コンパクタ

- 学名:Viburnum opulus ‘ Compactum ’
- 科名・属名:ガマズミ科ガマズミ属
- 分類:落葉低木
- 花期:4~6月
ビバーナム・コンパクタは、ヨウシュカンボクの園芸品種。葉がカエデに似た形をしています。春から初夏に白い花が咲いたあとに実る果実は、グリーンから徐々に赤く色づきます。夏にはグリーン、晩夏からは赤い実つきの切り花として人気があります。
オトコヨウゾメ

- 学名:Viburnum phlebotrichum
- 科名・属名:ガマズミ科ガマズミ属
- 分類:落葉低木
- 花期:4~6月
オトコヨウゾメは、春の白い小花と秋に赤く熟した果実が、ガマズミによく似ていて美しい樹木です。生長しても2~3m程度にしかならないので、庭木としても人気があります。株立ちのものをシンボルツリーとして植えると華奢で涼やかな印象になります。
オオカメノキ(ムシカリ)

- 学名:Viburnum furcatum
- 科名・属名:ガマズミ科ガマズミ属
- 分類:落葉低木
- 花期:4~6月
オオカメノキは、ガクアジサイのような花が特徴的なガマズミの仲間。葉が害虫の被害にあいやすいことから、「ムシカリ」の別名を持ち、広く知られています。
ガマズミの育て方

ガマズミは、本当に手間のかからないのが特徴の樹木です。細かい枝が出てきたら風通しを良くするために、少し枝を整理してあげましょう。夏など日差しが強く乾燥が続くような場合は、たっぷりとお水をあげてください。ガマズミは日本の山野に自生している植物です。山の中のような、落ち葉でふわふわの土壌が好きです。秋にガマズミの株周りに腐葉土を漉き込んでふわふわの土を作ってあげると、翌年の花付きが良くなります。
日当たり
ガマズミは日当たりが良い環境を好みます。山野に自生しているとは言っても、あまり日当たりが悪いと実付きが悪くなることがあります。ガマズミを育てる際には、日当たりの良い半日陰くらいの場所で管理してあげてください。
ガマズミの植え付け
ガマズミの植え付け及び植え替えは、真夏と真冬を避けて、秋の暖かいうちか春に行います。腐葉土をたっぷり入れたふかふかの土に植えてあげましょう。ガマズミは山野に自生しているような樹木です。落ち葉でふかふかの土が好きです。
ガマズミを鉢植えで管理している場合は、一回り大きい鉢に植え替えてあげてください。ガマズミに限らず植物は、いきなり大きな鉢に植え替えると、急激に根ばかりが生長して花が咲かない原因となります。
ガマズミの剪定
小さな剪定
ガマズミは植えっぱなしでほとんど剪定の必要はありません。樹形が乱れてきたと感じたら、適宜枝を整理するようにします。混み合った枝や陰に回ってしまっているような小さな枝の剪定は、気が付いたタイミングで行って問題ありません。
大きな剪定
大きく剪定を行うのであれば、花後早めに行いましょう。ガマズミは秋の結実後を待っていると、翌春の花芽を切ってしまうことになりかねません。
冬の剪定
ガマズミの樹形を整える剪定は、冬の落葉時に行います。この時大きく剪定することで、翌春の花芽を切ってしまうこともあります。あまり強剪定にならないように、込み入った枝を整理したり、邪魔になった枝を落とすような剪定にしておきましょう。
気をつけたい病害虫
ガマズミは非常に強健で手間のかからない素敵な樹木です。それでも稀に被害にあうこともあります。そんな時は早めに手入れを行って、被害を最小限に抑えてください。
カイガラムシ
ガマズミは日当たりや風通しが悪いと、カイガラムシが発生することがあります。まだ柔らかいうちでしたら、歯ブラシ等でこそぎ落としましょう。土に落ちたカイガラムシは、もう上がってきません。貝殻のように固くなってしまっていたら、根気よくスコップなどで削り落とすか、薬剤を散布してください。
うどんこ病
うどんこ病が発生してしまったガマズミの枝葉は整理しましょう。うどんこ病は土の中にウイルスがいることがあります。鉢植えであれば植え替えを行ってください。地植えの場合は、土にも薬剤を散布しましょう。
ハダニ
ハダニの原因は乾燥です。ガマズミの葉っぱが紅葉でもないのに赤銅色になり元気が無くなってきたら、葉の裏側を確認してください。小さなハダニがたくさん付いていることがあります。ハダニを発見したら、速やかに枝葉を落とし整理してください。そのあとにたっぷりとお水をあげます。あとは、乾燥させすぎないように注意して管理しましょう。葉裏に霧吹きで水をかけるのも有効です。
切り花でも楽しめるガマズミの魅力

ガマズミは、花瓶に生けて楽しむことができます。オオデマリや、ビバーナム・スノーボールの花が咲いたら、ちょっと切ってかざってみませんか。お部屋に爽やかな風を呼び込むような、インテリアのアクセントになります。
また花き市場では、早春にビバーナム・ティヌスのつぼみの付いた枝が「ガマズミ」という名で流通します。その実とも花とも違うつぼみの独特な質感は、他の花を引き立てる素敵なスパイスになります。秋~冬には実の付いた枝が流通します。ガマズミの真赤な実や、ビバーナム・ティヌスの光沢のある黒い実は、他の花と一緒に生けると独特の存在感を放ってくれます。
ガマズミは、春の花、夏のグリーンの葉、秋の実と、四季を通して楽しめる庭木です。ガマズミを育てて、飾って、もっと楽しんでみませんか。
▼編集部のおすすめ