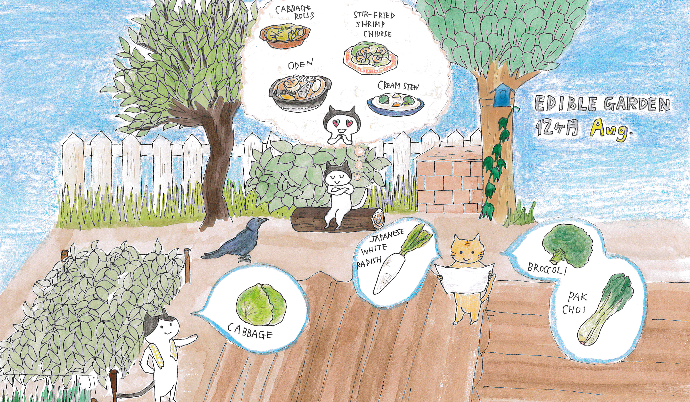自分で育てた野菜で年越料理ができる!秋から育てたい伝統野菜3選
更新
公開

今年の秋冬栽培は育てた野菜で、しかも古き良き日本の伝統を伝える自家製伝統野菜で年越料理を作ってみませんか?年末は今年一年を振り返りながら、家庭菜園で育てた伝統野菜を使ったおいしい野菜に舌鼓だなんて素適ですね。
こんなふうに家庭菜園に目標ができるとなんだかやる気が湧いてきます。秋から育てる年越料理におすすめな伝統野菜3選をご紹介します。
目次
プランター栽培もできるおすすめ伝統野菜3選
今回ご紹介する野菜は、畑だけでなくベランダ菜園でプランター栽培もできる野菜です。深さを必要とする野菜は高さのあるプランターや袋栽培で育てたり、土寄せをしっかりしてあげると元気に育ちます。
大根

秋冬野菜の定番「大根」は、おすすめ栽培リストから外せません。年越しそばの「大根おろし」、お正月料理の「なます」など、収穫したてのみずみずしい大根の甘みを楽しむことができます。
今は「大根」とひと言でいえども、品種が様々ありますので、畑での家庭菜園や、ベランダでのプランター栽培など、それぞれの状況に合わせた品種選びも可能です。
おすすめ伝統野菜~祝い大根
大根の品種で「祝い大根」というものがあります。祝い大根の収穫時の大きさは、直径2~4cm程、長さは15~20cm位の小ぶりの大根で、古くから奈良で作られてきた大根で「大和の伝統野菜」として大切に生産されています。主に関西でお雑煮などに使われていました。
小ぶりの大きさから、細かく切り分けることなく、丸い形のままで料理に使用できることから、「角が立たず、円満に過ごす」願いを込めて、お正月に食べられるのだそうです。
祝い大根の他にも、小ぶりのサイズのミニ大根や、紅芯大根といってカブのような形に表面が青首大根のような色なのですが、切ってみると中は鮮やかな紫赤色をしています。酢につけると鮮やかな赤に変わるため、お正月の晴れのお料理に最適の大根です。
・祝い大根の植え付け:9~10月
・祝い大根の収穫:11~1月
▼一般的な大根の育て方はコチラ
ニンジン

ニンジンは、一年を通して栽培することができる野菜です。一般的なニンジンの色はオレンジ色ですが、じつは赤、黄色、紫など様々な色合いの品種があります。この機会に、育てたことのない色のニンジンを育ててみてはいかがでしょうか。
また、ニンジンを自分で育てるメリットとして「ニンジンの葉」が収穫できるということです。通常ニンジンは、葉が切り取られ根の部分のみがお店で売られていますが、このニンジン以上に大きく生長した葉がとても美味しいのです。
ニンジンの葉の部分は、天ぷらにするとセリ科のもつ爽やかな風味、カリカリとした食感を味わうことができます。また、小さいうちは、そのままサラダとしてハーブのような感覚でとても美味しくいただけます。
おすすめ伝統野菜~金時にんじん
祝い大根同様に、関西のお正月に使われる野菜の一つ「金時にんじん」は東洋系の品種で、京にんじんとも呼ばれます。金時にんじんは春に種をまくと、とう立ちしやすい性質があるため7~9月上旬までには、種まきを終わらせたい品種です。
・金時にんじんの種まき:7月下旬~9月上旬
・金時にんじんの収穫:12~1月
▼一般的なニンジンの育て方はコチラ
ネギ類

ネギ類の中でもわけぎやアサツキなどは 秋に球根を植え付けておけばどんどん生長するため育てやすく、何度も収穫できることから家庭菜園の初心者の方におすすめです。
ネギ類には病原菌の拮抗微生物(病原菌を防ぐ微生物)が共生しています。この独特な臭気が害虫を遠ざけるため、コンパニオンプランツとして他の野菜と混植できることもおすすめのポイントです。
おすすめ伝統野菜~九条ねぎ
九条ネギは数あるネギ属の中でも主に京都で栽培される伝統野菜で、栽培の始まりは平安時代にまでさかのぼります。全国的に京野菜の代表格として知られています。九条ネギは一般的な長ネギよりも青い葉の部分が多い青ネギで、他のねぎと比べてぬめりが多いことが特徴です。
この九条ネギもプランターで手軽に育てることができる上に、3~4回繰り返し収穫できるとてもお得なネギなのです。九条ネギは種から育てるよりも、干しネギなどの苗を購入して植え付けたほうが、簡単に育てることができます。
九条ネギは「葉ネギ」タイプなので、土寄せをしないことで青い部分が多く育ちますが、土寄せをしたり、わらなどで光に当てないようにすると、九条ネギの白い部分を多く作ることができます。お好きな方法で育てる楽しみがあります。
・九条ネギの植え付け:8月下旬~9月上旬
・九条ネギの収穫:10月中旬~
▼一般的なネギの育て方はコチラ
秋冬野菜を育てるコツ
春夏栽培はまだ少し肌寒さが残る春から暑い夏の時期に野菜を育てますが、秋冬栽培は逆に残暑が残る8月下旬~9月初旬に栽培がスタートし、寒さの厳しい時期に育て終わります。では、秋冬栽培ではどんなことに注意すればよいのでしょうか。
秋冬栽培の種まきのコツ
今回おすすめした大根・ニンジンの種まきは、育てる地方・天気・気温によって収穫時期は変わります。時期をずらしながら種をまいてみると、年末やお正月に向けて収穫適期を迎えることができるでしょう。
秋冬栽培の植え付けのコツ
主な秋冬野菜の生育適温は、20℃前後がほとんどです。そのため、冬の厳寒期における野菜の生育は鈍り、追肥や水やりをしても植物が養分を吸収できない時期に入ります。
「秋冬野菜の植え付けが1週間遅れると、収穫は1か月遅れる」といっても過言ではありません。もし、収穫できたとしても、小ぶりな大きさになってしまいます。育てている野菜が、充分な日差しを浴び、生育に適した温度で一日も長く育ててあげましょう。
▼春夏栽培の抜き取りから秋冬栽培のための土のメンテの方法ならコチラ
秋冬栽培の害虫を防ぐコツ
8月下旬~9月上旬の秋冬野菜を植え付けから11月頃まで、じつは害虫といわれる虫たちも活発に活動する時期です。ちょっと目を離したすきに葉を丸ごと食害されたり、植え付けたばかりの苗の茎が食べられたりする被害に悩まされてしまします。植え付けた直後から寒冷紗などで苗を覆い、害虫の被害を防ぎましょう。
日本の伝統野菜はその土地に古くから栽培されている文化的にも守っていきたい野菜です。今回ご紹介した伝統野菜以外にも地方の素晴らしい伝統野菜があります。育てることがなかなかできない方でも、伝統野菜を味わうことはできます。旬の伝統野菜の味は濃厚で、食べ応えが格段に違います。栄養価も大変優れているのでお店で見かけたらぜひ手に入れて味わってみてください!
▼編集部のおすすめ