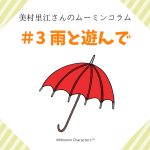ナスの育て方 〜お手入れ編〜
更新
公開

ナスは肥料もお水も大好きなので、お手入れしがいのある野菜の一つです。
日頃からお手入れをこまめにしていると、ナスはそれに答えてくれるように元気に育ってくれますよ♪
目次
ナスの病害虫チェック

ナスの葉の裏にハダニが発生してないか、新芽の先にアブラムシはいないかよく確認しましょう。
特にハダニは、乾燥すると発生しやすいため、葉水を与えることでかなり防ぐことができます。ニームや木酢液などを希釈してスプレーしてあげましょう。
スプレーすることで病害虫を防ぐだけでなく、ニームや木酢液は葉に栄養も与えることができます。まだ収穫期ではないこの時期は、追肥による栄養補給よりも葉からの栄養補給も有効といわれています。
スプレー後、希釈液が余ったら土にそのまま与えても肥料代わりとなります。
ナスの追肥

ナスはとても肥料を好むお野菜です。植え付けた2週間後から追肥を始めましょう。
肥料を施す位置は、葉が広がった先よりも少し先の方に施します。というのも、だいたい根の広がりというのは葉の広がりと同じくらいといわれています。そのため葉の先を目安に肥料を施します。
今回はプランターで育てているので、だいたいプランターの外側に追肥をしましょう。
ナスの水やりなど

肥料同様、ナスはお水を好む性質があります。日頃から乾燥させないように管理しましょう。通常、畑で栽培する際は雨のはね返りによる病害虫を防いだり、夏の乾燥を防ぐために敷きわらを敷きます。
春夏のプランター栽培は、バーク堆肥などを敷いて梅雨時期の雨のはね返り・乾燥を予防するといくぶんそれらを防ぐことができますので、お試しください。
▼編集部のおすすめ