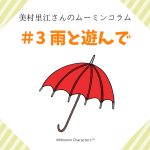ワスレナグサそっくり! ムラサキ科のかわいい草花5種
更新
公開

ワスレナグサは、春にかわいい水色の花が咲くムラサキ科の一年草。最近は、苗以外にも切り花としても流通しています。今回はワスレナグサに似た、かわいい小さな花を咲かせるムラサキ科の草花5種をご紹介します。
目次
ワスレナグサ

Myosotis
ワスレナグサは、3月~5月が開花時期のムラサキ科の一年草。原産地では多年草として扱われていますが、梅雨や猛暑に耐えられないことが多いため、日本では一年草として扱われています。一度植えると、こぼれ種でも育つほど性質は強健。最近は品種も多数流通し、水色の他、白やピンクもあります。草丈は、矮性種(丈が低い性質)や切り花にもできる草丈が高い品種もあります。
私が育てているワスレナグサは、「宿根ワスレナグサ」の名で販売されていた草丈の高い品種です。花壇に数株のワスレナグサを植えたところ、翌年以降あちこちに種がこぼれて、今では花壇、通路、他の花の鉢の上・・・など、びっくりするような所からも発芽するようになりました。
▼ワスレナグサの育て方
1.シノグロッサム

Cynoglossum amabile
シノグロッサムは、和名はシナワスレナグサ、英名はChinese forget-me-notとも言われています。ワスレナグサより少し後の春から初夏に開花し、草丈は30~50cmくらいです。花色は、水色の他、白、ピンクなどがあります。ワスレナグサと同じく高温多湿が苦手なので、日本では一年草として扱われています。環境に合えばこぼれ種でも増えるほど性質は強い草花です。
シノグロッサムとワスレナグサの見た目の違いは、①ワスレナグサより少し花が大きい、②花の色が単色(ワスレナグサは中心が黄色)、③葉色がワスレナグサは若緑色、シノグロッサムはシルバーグリーン色 です。
▼シノグロッサムの育て方
2.オンファロデス

Omphalodes
オンファロデスは、日本に自生する種類をはじめ、ヨーロッパやアジアにも分布するムラサキ科の草花で、種類によって多年草と一年草があります。春から初夏にワスレナグサに似た、青、白、青×白の複色の花が開花します。

オンファロデス・リニフォリア
園芸店で一番多く見かけるのは、オンファロデス・リニフォリア。4月~6月にかけて、無数の白い花が開花する一年草です。こぼれ種でも咲くほど性質は強く、花がらをまめに摘み取っていれば多少花期は伸びます。シルバーグリーンの葉も魅力的です。
このオンファロデスの名前の由来は、種の形がへそのような形からきています。真ん中がくぼんでちょっとユニークな形なので、機会があったら種をとってみてはいかがでしょうか。
▼オンファロデスの育て方
3.ブルンネラ

Brunnera
ブルンネラは、4月~5月に開花するムラサキ科の多年草。今回ご紹介する中では花自体はワスレナグサと一番似ていますが、葉はワスレナグサの葉とはまったく違うスペード形をしています。
草丈は、品種にもよりますが30~40cm。半日陰が好みなので、シェードガーデン向きの草花です。園芸品種が複数あり、水色の他、白花種もあります。斑の入り方に特徴があるものが多く、白、クリーム、黄色の斑の入り方が品種によって様々。花が終わった秋までは、カラーリーフとして楽しむことができます。
斑入り植物によくあることですが、強すぎる日差しだと葉焼けを起こします。東京のような場所では、高温多湿の梅雨から夏をいかに乗り切るかがポイントです。
▼ブルンネラの育て方
4.アンチューサ

Anchusa
別名アフリカワスレナグサのアンチューサは、品種によって一年草と多年草があります。花の色は水色から濃いめの青まであり、葉はちょっとざらついた触感をしています。草丈も矮性種から高性種まで品種によって様々です。
5月~7月くらいの初夏が開花時期。高温多湿に弱いため、多年草のアンチューサも梅雨や猛暑に耐えられるかが翌年開花するかのポイントです。
▼アンチューサの育て方
5.キュウリグサ

Trigonotis peduncularis
キュウリグサは、ムラサキ科の一年草。葉っぱをこすったりちぎったりすると、キュウリの香りがすることから名前がついたそうです。野草なので苗として出回ることはほとんどありませんが、いたるところで見かけます。4月頃、ワスレナグサよりもさらに小さな水色の花が開花します。開花までの花はくるんと丸まり、開花とともに上を向きます。極小の淡い水色の花は、見落としてしまうほど控えめな雰囲気ですが、性質は強くこぼれ種で増えていきます。
▼キュウリグサの植物図鑑