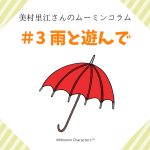甘く優しい金木犀(キンモクセイ)の香り。時期や特徴、効果について
更新
公開

金木犀は秋に香りの良い花を咲かせる庭木。基本情報から香りや花の時期、特徴、英名、名前の由来、別名など、詳しく紹介します。
目次
- 金木犀(キンモクセイ)とは?基本情報
- 金木犀(キンモクセイ)の時期
- 金木犀(キンモクセイ)の香り
- 金木犀(キンモクセイ)の名前の由来や別名は?
- 金木犀(キンモクセイ)の英語の名前
- 金木犀(キンモクセイ)の利用法
金木犀(キンモクセイ)とは?基本情報

- 学名:Osmanthus fragrans var. aurantiacus
Osmanthus fragrans Lour. var. aurantiacus Makino - 科名・属名:モクセイ科モクセイ属
- 分類:常緑高木
金木犀(キンモクセイ)の特徴
金木犀は、秋にオレンジ色の小花を枝いっぱいに咲かせる常緑高木。とても強く印象的な芳香が特徴で、香りに気がついて周囲を見渡すと花が咲いていたというくらいです。
葉は楕円形で光沢があり、椿のような厚みと硬さがあります。花は直径4~5mm程度と小さく、オレンジ色で4枚の花びらが合着したようなフォルムをしています。
名前にある犀は、動物のサイのことを指す漢字です。これは、幹をサイの肌に例えたことに由来するとされています。
金木犀(キンモクセイ)の時期

金木犀(キンモクセイ)の花が咲く時期
金木犀の花が咲く時期は、9月~10月。咲いている期間はわずか1週間程度です。
金木犀(キンモクセイ)の香る時期
金木犀が香る時期は、花が咲いている間の1週間程度です。香りを楽しめるのは、わずかな期間だけ。金木犀の香りに切なさを感じるという人が多いのは、この儚さゆえかもしれません。
また、開花してすぐに雨が降ってしまったり、強風や酷暑の戻りなどであっという間に散ってしまった年は、数日後に2回目の花を咲かせます。そんな年は香りを2度楽しめるので、ちょっと得をしたような気分になります。
金木犀(キンモクセイ)の香り

金木犀(キンモクセイ)の香りの特徴
金木犀の香りは、熟した果物を思わせるような甘さと、華やかさと爽やかさが入り混じったような優しい印象です。
学名 Osmanthus fragrans の属名 Osmanthus は、ギリシャ語の香り(osm)と花(anthos)に由来するとされています。さらに種小名のfragrans も香るという意味があるので、香りの良い花であることを強調するような学名であることがわかります。
ハッとするほど印象的なのに、甘ったるさやしつこさがないのが、多くの人から愛される金木犀の香りの特徴ではないでしょうか。
金木犀(キンモクセイ)の香りの成分と効果
金木犀の香りの主な成分は、ガンマデカラクトン(γ-デカラクトン)とリナロールです。ガンマデカラクトンは、果物などにも含まれる芳香のある成分。また、モンシロチョウなど一部の昆虫を寄せ付けない作用をしています。リナロールは、甘い香りを持つアルコール成分で、鎮静、抗不安などのリラックス効果があると言われています。他にも食欲を抑制する効果があるという実験結果も報告されているそうです。
金木犀(キンモクセイ)の香水は珍しい?
金木犀は中国の雲南地方が原産です。温暖な環境を好み、あまり寒いところでは育ちません。日本や中国よりも北に位置するヨーロッパではうまく育たなかったのでしょう。香水文化が盛んなヨーロッパで、金木犀の香水というものがあまり作られなかったのはこのためだという話を聞いたことがあります。
少し前までは珍しかった香水ですが、最近では秋になるとそこかしこから発売されます。定番のものから秋だけの限定品までさまざま。商品名に金木犀と付いているものから、オスマンサスと学名で名付けられているものまであります。お気に入りを探してみてはいかがでしょうか。
金木犀(キンモクセイ)の香りの不思議
金木犀は雌雄異株ですが、日本には雄株しか存在しません。花の香りは、花粉の媒介者である昆虫を引き寄せるためにあると言われていますが、雌株が存在しないので、昆虫を引き寄せる必要がありません。なぜ、必要がないのに強い香りを放つのかが不思議なところです。また、種から発芽して増えるということがないので、主に挿し木で増やされています。つまり日本中の金木犀はクローンであるというのもおもしろい話です。
あれだけの香りを放ちながら果実を作らない植物というのは、とても不思議な存在です。この先もっと研究が進んで、香りの不思議が解明されていくのが楽しみです。
金木犀(キンモクセイ)の名前の由来や別名は?

金木犀という名前の由来は、モクセイ属の樹木を木犀(もくせい)と呼ぶ中国の言葉に、花の色の特徴を合わせて名付けられたと言われています。名付け親は、植物学者の牧野富太郎博士です。
学名からわかる金木犀(キンモクセイ)の名前の由来
金木犀の出自については諸説あります。白花の銀木犀が先に存在していて、その変種としてオレンジ色の花を咲かせる金木犀が発見されたとされたという説、あるいは近縁種のウスギモクセイから作出されたという説などがあります。
学名にある Lour. は、ポルトガルの植物学者ルーレイロ(Loureiro)氏の略、さらに var. は変種のこと、aurantiacus はラテン語でオレンジ色や橙色という意味、最後に命名者である牧野富太郎博士の Makino が入っています。学名は、まず先にルーレイロ氏がモクセイ属を発見し、後に牧野富太郎博士が変種の金木犀を発見し名付けたということを示しています。
金木犀(キンモクセイ)の別名
金木犀にはいくつかの別名があります。香りが風に乗って遠くまで運ばれていくことから、九里香や千里香などと呼ばれていたこともあったそうです。時代や地域によって異なりますが、一里は約3.9kmなので、ちょっと大げさなようにも思えます。
中国ではモクセイ属の仲間をまとめて桂花と呼んでいます。さらに細かく区別するときは、金木犀を丹桂、銀木犀を銀桂、薄黄木犀を金桂と呼ぶそうです。金木犀のお茶は桂花茶という名前で流通しています。
金木犀(キンモクセイ)の英語の名前

金木犀の英語の名前は、Fragrant olive です。fragrant は香りが良いという意味。英名も学名と同じく、香りの良さに由来した名前でした。
Osmanthus(オスマンサス)とは?
最近では、学名の Osmanthus がそのまま英語の名前として使われています。金木犀の香水や精油など、Osmanthus(オスマンサス)という名前で流通しているのを見かけます。
金木犀(キンモクセイ)の利用法

金木犀の利用法は、何と言っても香りを楽しむことです。ポプリにしたり、お茶に入れたりと、少しでも長く楽しむ方法を紹介します。
モイストポプリの作り方
ポプリにして長く香りを楽しむ方法です。
香水の作り方
自分で作る香水。秋の花の香りを纏ってみませんか。
お茶の作り方
花をお茶とブレンドして楽しむ方法。食用にする場合は、必ず薬剤が散布されていないものを選びましょう。
シロップの作り方
花のシロップ漬けの作り方です。食用にする場合は、必ず薬剤が散布されていないものを選びましょう。
アロマウォーターの作り方
香りを蒸気にして楽しむ方法です。
秋のほんのわずかな時期しか漂わない金木犀の芳香を楽しんでください。
▼編集部のおすすめ