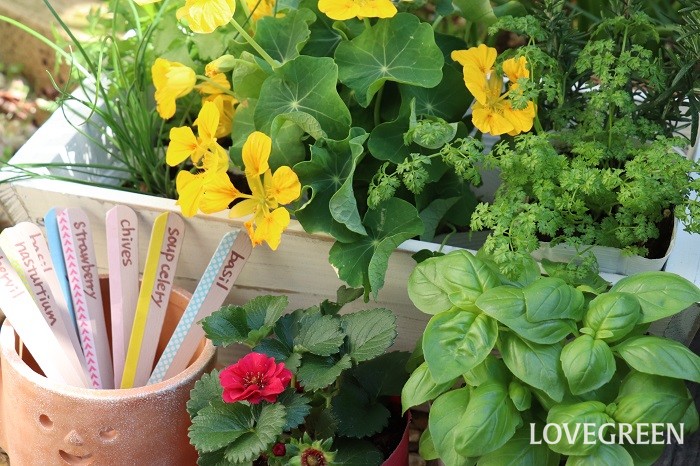ブロッコリーをベランダ菜園で収穫!育て方とプランター栽培のコツ
更新
公開

ご自宅のベランダで秋から冬にかけて家庭菜園を始めたい方に、とってもおすすめしたいのはブロッコリーです。
ブロッコリー栽培の良いところは、寒さに強く、半日陰でも十分育ち、ブロッコリーの頂花蕾(ちょうからい)を収穫した後も次々出てくる側花蕾(そくからい)やブロッコリーの葉っぱまでも美味しく食べることができるので本当におすすめです。今回はベランダ菜園でできる、秋冬シーズンのブロッコリーの育て方のコツをご紹介します。
目次
ブロッコリーの苗の植え付け

このような場所にプランターを置くのはNG
ベランダでブロッコリーを栽培する際に、そのベランダが南向きか北向きかということも、重要なポイントですが、一番大切なことは室外機の位置です。
ブロッコリーは風通しの良い環境を好みますが、不自然な強い風、しかも熱風は禁物です。ただでさえ、プランターという小さな器でブロッコリーを育てるため、土の乾燥が激しく、植物が弱りやすい環境を作ってしまいます。できるだけ室外機の風に当たらない環境でブロッコリーを育てるようにしましょう。
ブロッコリーの好む環境
ブロッコリーの生育適温は15~20℃。日当たりの良い場所を好みますが、半日陰の場所でもゆっくり生長することができます。病害虫を防ぐためにも、風通しの良い場所で育てましょう。
ブロッコリーのプランターの準備
ブロッコリーの根が大きく張ることができるように、プランターはある程度土の量が多く入るものを用意しましょう。
ブロッコリーも人間と同じで、器によって実る大きさも量も違います。ご自身のベランダの広さに合う、無理のないプランターを選ぶことで、自ずと収穫できる量も分かってきます。
ブロッコリーのプランター
高さ、幅、奥行き共に30cm以上の約28~50リットル以上のサイズがよく育つと思います。
ブロッコリーの土の準備
排水性を良くするため、鉢底石をプランターの底に敷きます。土は、野菜用の培養土で育てましょう。
ブロッコリーの植え付け時期
秋冬に育てるブロッコリーの植え付けで、大切なことは9月上旬には植え付けを済ませるということです。
「秋の苗の植え付けが1週間遅くなると、収穫は1か月遅くなる」と言っても過言ではありません。初期生育が良好な野菜は、実り多い収穫となります。
※主に関東温暖地
ブロッコリーの苗の選び方
ホームセンターや園芸店でたくさんのブロッコリーの苗の中から、生育が良好な苗を選ぶポイントをご紹介します。
葉の緑が濃く、厚みがある

目で葉の厚みを見極めましょう。実際にホームセンターや園芸店で、葉をやみくもに触るのはブロッコリーの苗もかわいそう。お店への配慮のある対応を心がけましょう。
節間がしまっている。
ヒョロヒョロと間延びしていない、しっかりした苗を選びましょう。
病害虫が付いていない。
鉢底に虫がいないか、葉の両面に虫に食べられた後がないか確認しましょう。
苗の先端に勢いがある
新芽の勢いは苗の生育の勢いを現します。元気の良い苗を選びましょう。
苗を植え付ける前に

植え付ける前に黄葉は取り除きましょう。
植え付け方
1. 苗に充分水分を与える。
植え付ける前のひと手間です。予めジョウロでしっかり苗に水を与えるか、バケツに水をはりその中に静かに苗を入れ、しっかり水を吸わせましょう。植え付けてしまった後に気づいた方は、最後に水をしっかり与えてください。

2. プランターに苗と同じくらいの穴を開け、苗を軽く手で押さえ、根鉢を崩さないように植え付けます。

3. 苗の周りを少し凹まして、苗にしっかり水が浸透するように植え付けてあげましょう。

4. お水をしっかりあげます。
植えたばかりの苗は、土に活着するまでに少し時間がかかります。その際、根が乾燥してしまわないためにも、植え付けから1週間位はしっかりと水を与えます。

5. まだ苗が小さく、寒冷紗に納まるうちは、出来るだけ寒冷紗の中で育てましょう。
秋冬野菜の成功の秘訣は、害虫から苗を守ることです。寒冷紗はとても心強いアイテムですね。
弱っているブロッコリーの苗の対処方法
・病害虫が付いている。
〜原因〜
風通しの悪いところ、密植状態で育てられた、もともと弱い苗だったことが考えられます。
〜対策〜
早速捕殺しましょう。まだ、初期の段階なので集中して取り除けば間に合います。
・苗の先端に勢いがない。
〜原因〜
水が足りない状態だったのかもしれません。
〜対策〜
水をしっかり吸わせてあげましょう。これでもち直さない場合は、苗自体が弱っていると考えられます。
ブロッコリーの日頃のお手入れ
植え付けたブロッコリーの苗のその後の生長過程を見ていきましょう。
ブロッコリーの生育(秋冬栽培)

植え付け時

植え付けから20日経過
随分と苗の主茎が太くなり、しっかりしてきました。

植え付けから1ヶ月経過
大きな葉が増えてきていますが、まだ頂花蕾(ちょうからい)は出来ていません。

植え付けから2ヶ月経過
頂花蕾(ちょうからい)が出てきました。

植え付けから3ヶ月経過
頂花蕾(ちょうからい)の他にも、小さなわき芽である側花蕾(そくからい)がたくさんできています。
ブロッコリーの追肥
ブロッコリーの本葉が7枚くらい出て来たら追肥をして土寄せをします。その後頂花蕾(ちょうからい)が出来たころから2週間に1度は追肥をしましょう。
肥料を施す位置は、葉が広がった先よりも少し先の方に施します。というのも、だいたい根の広がりというのは葉の広がりと同じくらいといわれています。そのため葉の先を目安に肥料を施します。今回はプランターで育てているので、だいたいプランターの外側に追肥をしましょう。
草勢が落ちているときなどは、様子をみて少し肥料を施してあげてもよいでしょう。
ブロッコリーの土寄せ

葉の大きさに比べ、茎が少し細いブロッコリー。追肥のタイミングで、株元へ軽く土寄せすることで、倒状を防ぎます。
冬の追肥
ほとんどの秋冬野菜の生育適温は15~20℃です。そのため、この温度を下回ると生育は鈍くなってきます。
つまり寒くなるこれからの季節、15℃を下回るようになると野菜の生長するスピードはどんどん遅くなるのに、春夏野菜の頃と変わらず肥料をどんどん与えては、使用されない肥料が土の中で溜まってしまうことになります。
また、春夏と違い秋冬は雨も少なく、与える水の量も少ないため肥料分が水で流れ出すことも少ないということになります。
気温が15℃を下回ったら、秋冬に育てるブロッコリーの肥料は控えた方がいいでしょう。
ブロッコリーの病害虫チェック

ブロッコリーの葉を食害するナメクジ
雨が降った次に日の朝は、ナメクジ捕獲のチャンスです。いつもはどんなに探しても、なかなか姿を見せてくれないナメクジですが、雨が降った後はとっても活動的になっています。ちょっと葉の裏を覗いてみると、まんまると太ったナメクジを見つけるかもしれません。
日常のお手入れとして、ニームや木酢液などを希釈してスプレーしてあげましょう。スプレーすることで病害虫を防ぐだけでなく、ニームや木酢液は葉に栄養も与えることができます。
スプレー後希釈液が余ったら、土にそのまま与えても肥料代わりとなります。
ブロッコリーの水やり
土の表面が乾燥したらたっぷりと水を与えましょう。湿度に弱い性質がありますので水の与えすぎは禁物です。
通常畑で栽培する際は、雨のはね返りによる病害虫を防いだり、夏の乾燥を防ぐためにマルチや敷きわらを敷きます。
秋冬のプランター栽培では、バーク堆肥などを敷いて冬の防寒対策、雨のはね返りや乾燥を予防するとよいでしょう。
ブロッコリーの病害虫について
ブロッコリーは葉も柔らかく甘いので、私たちも食べることができます。そのおいしさを知っていて、ねらっているのが害虫たち。一体どんな害虫に注意をすればよいのかご紹介します。
害虫
アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ナメクジなどに注意しましょう。
・アオムシはカブ、大根、チンゲンサイ、白菜、ブロッコリーなどのアブラナ科の野菜を好んで食害します。アブラナ科の野菜の葉の上のフンを見つけたら、葉の上、茎などにいるモンシロチョウの幼虫のアオムシを探して駆除しましょう。
ちなみに、同じアオムシの仲間のアゲハやキアゲハの幼虫は、セリ科のハーブや野菜、イタリアンパセリ、ニンジン等を好んで食害します。
・ヨトウムシは夜に活動するため日中葉の周りで捕獲するのは難しいですが、苗の周りの土1cmほどの深さのところにいるので土の中を探してみましょう。ヨトウムシの成虫は蛾なので、飛来し葉裏に産卵します。葉の裏もこまめにチェックすることで早期発見が可能になります。
病気
ブロッコリーは湿度に弱いことから黒腐病に注意しましょう。黒腐病は水が貯まるとかかりやすいので、プランター栽培は底に軽石を敷いて排水できるようにしましょう。
鳥害

ブロッコリーの害虫被害がおさまる頃は、その害虫を餌としていた鳥のエサが無くなる頃です。
主にヒヨドリが、ブロッコリーの葉を食べにやってきます。カリフラワーとブロッコリーと両方育てていたら必ずブロッコリーの葉を食べています。鳥も美味しさが分るんですね。寒さ除けにもなるので、寒冷紗をかけて鳥の被害を防ぎましょう。
ブロッコリーの収穫と保存方法
お店で売られているブロッコリーは、頂花蕾(ちょうからい)といってブロッコリーの花の蕾(つぼみ)の部分ですが、自分で育てているとそれ以外にも、側花蕾(そくからい)とブロッコリーの葉も収穫することができるので、さらにお得な野菜なんです!
頂花蕾(ちょうからい)の収穫

やっとブロッコリーの頂花蕾(ちょうからい)が大きくなりましたので収穫していきたいと思います。

ブロッコリーを収穫するときの注意する点は切り方です。
切り口が雨などで濡れ、そこから腐れてしまわないように、お日様に向かって斜めにカットします。そうすることで、切り口が早く乾き腐らずにすみます。
側花蕾(そくからい)とブロッコリーの葉の収穫

ブロッコリーは頂花蕾(ちょうからい)を収穫した後も、側花蕾(そくからい)といって、更にわき芽が出てきて、引き続き収穫することが出来ます。小さな側花蕾(そくからい)はお弁当に最適の大きさですね♪
ブロッコリーを抜き取る時に一気に葉を収穫しますが、側花蕾(そくからい)の生育状態をみながら、下の葉から順々に収穫することも可能です。
ブロッコリーの保存方法
ブロッコリーは花蕾(からい)、つまり花のつぼみなので、そのままにしておくと、花が咲き始め食味も落ちてきます。収穫したらできるだけ早めにお召し上がりください。
ブロッコリーの冷蔵保存
一般的にブロッコリーは、ビニール袋に入れ、冷蔵庫の野菜室に立てて保存します。5日ほどで使い切れないようでしたら、冷凍保存をおすすめします。
ブロッコリーの冷凍保存
お好みの大きさにカットしたら、軽く茹でて水気を切り、密封袋に入れ冷凍しましょう。
ブロッコリーの洗い方やレシピ、栄養について
スムージー人気も手伝って、最近ケールなどの葉野菜の人気がとても高まっています。
同じアブラナ科の野菜のブロッコリーの葉は、スジもあまり気にならず美味しく食べることができます。
同じアブラナ科の仲間であるカリフラワーは少しスジが目立ち、料理として使用するのは気になる方が多いかもしれませんね。
でも、どちらも生でかみしめてみると、甘味を感じてとっても美味しいんですよ♪
ブロッコリーの花蕾(からい)と葉のベーコン炒め

いつも食べるブロッコリーだけでなく、葉も一緒に調理しましょう!
〜材料〜
・ブロッコリーの花蕾(からい)と葉
・ベーコン
・塩コショウ
・他お好みの野菜(今回は赤カリフラワーを使用)
ブロッコリーの洗い方

ご自宅で育てたブロッコリーは、虫がついている可能性もあるのでしっかり洗いましょう。
収穫したブロッコリーを袋に入れて、塩また食用の重曹を入れます。その後水を入れ袋を閉じ、10分ほど時間を置きます。最後に袋の中でふり洗いした後、仕上げにしっかり水で洗い流しましょう。
こうすることで、万が一虫がいてもある程度取り除くことができます。
作り方

ブロッコリーの葉を適当な大きさに切る。
ブロッコリーの花蕾(からい)は、房ごとに切り分け、軽く下茹でして下さい。

材料を炒める。
オリーブオイルでベーコンを炒め、刻んだブロッコリーの葉と下茹でしたブロッコリー、カリフラワー(バイオレットクィーン)を加えて、塩コショウで味付けすれば出来上がり!
今夜のおかずの一品にいかがでしょうか?
ブロッコリーの栄養
ブロッコリーは緑黄色野菜でビタミンA、B1,B2,B6、C、E、K、食物繊維、葉酸、カロテン、カリウム、カルシウム、リン、鉄分を多く含みます。ビタミンCはレモンよりも多いとされています。良質のブロッコリーは鮮やかな緑色をしていて隙間なく花蕾がぎっしり詰まって咲き、茎に空洞がないものがおいしいです。
茎の側面の皮はとても食物繊維が多く、硬くて食べにくいので外皮は剥いてから調理することが望ましいといえます。葉や茎には多くの栄養分が含まれていますのでできるだけ丸ごと食べるようにしましょう。
食べ過ぎるブロッコリーのコリンという成分が体臭を悪化させるようです。
ブロッコリー収穫後の抜き取りについて
ブロッコリーは頂花蕾(ちょうからい)を収穫した後も、側花蕾(そくからい)や葉が順次収穫できるため、いつ抜き取ってよいものかなかなか判断がつかない野菜です。
ブロッコリーを抜き取る時期の判断
どう判断していいのか分からない方へ…
でも、育てているのはみなさんです。好きな時期に抜き取ることが一番だと思います。もし、ブロッコリーを抜き取っていいかどうか悩んでいるのなら、次のポイントに注意して、抜き取る時期を決めましょう。
2月中旬~下旬頃
・ブロッコリーが病害虫により、弱っているなら抜き取る。
・収穫量が落ち、苗に力が無くなっているなら抜き取る。
3月中旬~下旬頃
・まだまだブロッコリーの苗が元気な場合、育てる場所に余裕があるなら、そのまま抜き取らずに育てる(花が咲いたとしても菜の花と同じように食べることができる)。
場所に余裕がなく、3~4月から春夏野菜の栽培をスタートさせたいのならブロッコリーの苗を抜き取る。
ブロッコリーの抜き取り
さて、抜き取ることが決まったら、さっそく作業を始めましょう。
大きく生長したブロッコリーの苗を適当な大きさに分けて切っていきます。
これで、抜き取り完了ですが、ゴミ袋に入れて破棄する前に、必ず見て欲しいところがあります。
抜き取ったブロッコリーの苗の根をよく見てみると、太い根と細い根があります。どちらの根も表面に凸凹のない、きれいな根であれば、抜き取るだけで問題ありません。
根こぶ病の病原菌の除去
根こぶ病とは
アブラナ科植物にのみ発生する土壌病害で、病原体はネコブカビ類といわれています。根の表面に凸凹とこぶのようなものが作られるため、根の機能が低下して枯れていきます。
また、土の中で根こぶ病の病原体は休眠胞子の状態で4年以上生存するといわれていることから、排除することが難しい土壌病害です。なかなか排除することが難しい根こぶ病ですが、家庭でできる範囲処理しましょう。
土の消毒
①被害を受けた根の除去。
レーキや土ふるいで、被害を受けた苗の根を全て取り除きましょう。
②太陽熱で消毒(主に高温期)。
被害を受けた土を透明ビニール袋に入れ、水分を含ませ、封をして直射日光に2~3日ずつ両面に日を当てます。
寒ざらしで土壌改良
1~2月にかけて晴れた風のない暖かい日を選び、寒ざらしといって土をざっくりと荒おこしします。
プランターの土を掘り返し、1ヶ月ほど寒さに当て、土中の水分の凍結・解凍を繰り返すことで土が団粒化し、通気性の良い土に改良されます。同時に害虫・病原菌を除去することができます。
大根を植える
ダイコン類は根こぶ病の抵抗性が高く、感染しても発病することがありません。大根を根こぶ病の病原体のおとり作物として植え付けることで、土壌中の根こぶ病の発生確率を減少させることができます。
▼大根をおすすめする詳しい理由はコチラ
抜き取った後の作業

抜き取りが終了したら、春夏野菜に向けて準備を開始しましょう。
良い土の条件は、通気性、保水性、排水性この3つの条件が揃うことです。以下の手順で、良い土づくりを行いましょう。
1 プランター内の土をほぐす~通気性UP
▼土壌改良診断シートはコチラ
2 堆肥を入れる~保水性、排水性UP
3 石灰を入れる~酸度調整
4 元肥投入~栄養補給
これで準備は終了です。安心して次の野菜を植え付けられますね。
[post id=80542]
秋冬に育てるブロッコリーは寒さに強く、半日陰でもゆっくり育つ野菜です。もともと花の蕾(つぼみ)の部分を食べるため、育てていてもブロッコリーの頂花蕾(ちょうからい)がお花みたいでとても可愛いので、みなさんもぜひ育ててみてはいかがですか?
▼編集部のおすすめ