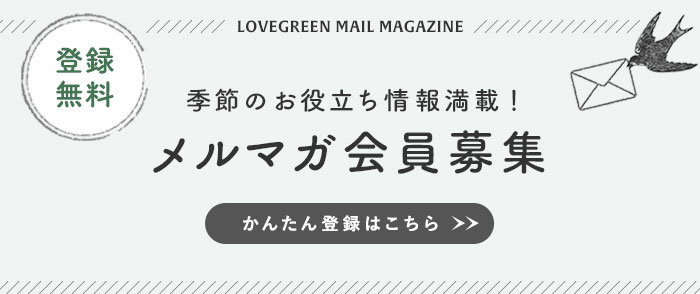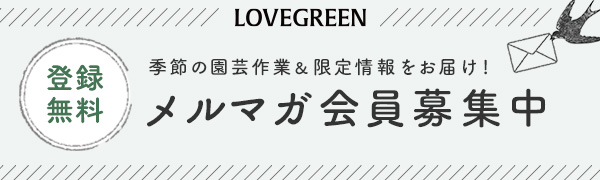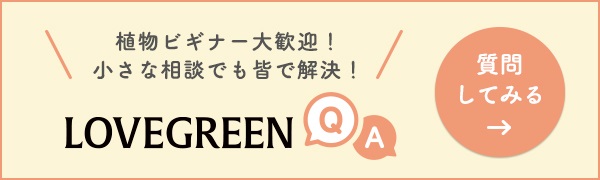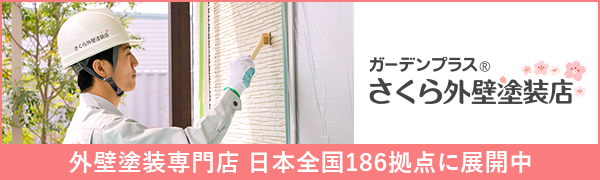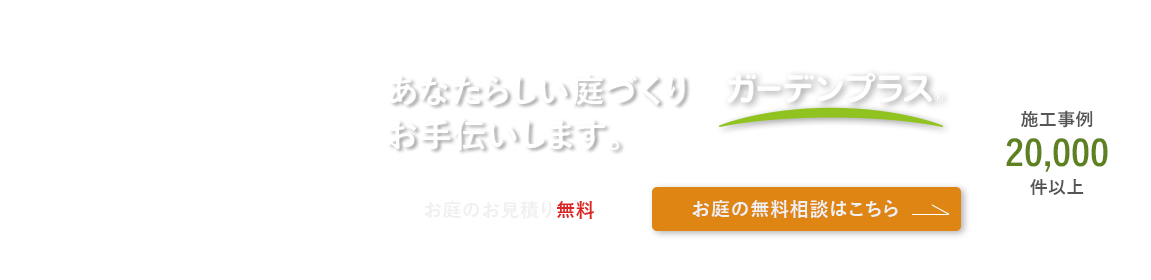11月が旬の野菜、果物、魚、花46種。五感全部で実りの秋を楽しむ
山田智美
このライターの記事一覧

11月に旬を迎える野菜、果物、魚、花を46種紹介します。さらに旬の食材を使ったレシピも。過ぎ行く秋を、五感全部を使って楽しみ尽くしましょう。
目次
11月とは?二十四節気や季語、行事、事柄

- 和名:霜月(しもつき)
- 英名:November
11月とは
11月は秋も深まり、冬に向けて寒さが増してくるころ。空気は乾燥し、薄手のコートが必要になります。風は冷たく、木々は紅葉し、枯葉を踏みしめる音を楽しみながらお散歩ができる時期。また、最後の秋の恵みを満喫できる時期でもあります。
11月に使われる季語
秋惜しむ(あきおしむ)
過ぎ行く秋を惜しむという意味。晩秋に使用される季語です。
蔦紅葉(つたもみじ)
秋に赤く紅葉した蔦の葉を指す言葉。夏は青蔦と言います。
帰り花
小春日和の日に春の花が返り咲くことを指す言葉。美しい秋の季語です。
時雨
初冬に降る通り雨。降ったかと思うと晴れ、晴れたかと思うとまた降り出すような雨のことを指します。
11月に迎える二十四節気
立冬(りっとう)
立冬は二十四節気の第19節目、毎年11月7日頃です。年によって1日程度前後します。また、11月7日から次の二十四節気の次の第20節、小雪までの15日間ぐらいを指します。
立冬はその年初めての冬の気配を感じ、冬に向けていよいよ寒くなってくるころです。
▼二十四節気の立冬についてはこちら
小雪(しょうせつ)
小雪は二十四節気の第20節目、毎年11月22日頃です。年によって1日程度前後します。また、11月22日から次の二十四節気の次の第21節、大雪までの15日間ぐらいを指します。
小雪は日が短く、空気は冷たくなり、雨が降っている間に雪に変わっていくころです。
▼二十四節気の小雪についてはこちら
11月の行事や事柄
文化の日
文化の日は国が定めた国民の祝日、毎年11月3日です。「自由と平和を愛し、文化をすすめる」日とされています。
勤労感謝の日
勤労感謝の日は国が定めた国民の祝日、毎年11月23日です。「勤労をたつとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう」とされています。年内最後の祝日になります。
七五三
七五三は年祝いの一つ。3歳、5歳、7歳の年にお祝いをします。11月15日に神社にお参りして子供の健康と成長を願うとされていますが、混みあうために写真撮影やお祝いなど、前倒しにする家庭も多くなっています。
酉の市
酉の市は毎年1月の酉の日に、鳳(おおとり)神社で行われるお祭りのこと。商売繫盛祈願の熊手の屋台がにぎやかに並びます。
えびす講
えびす講は、10月あるいは11月20日に行われる恵比寿様のお祭り。旧暦10月の神無月に全国の神々は出雲大社に集まります。このとき、留守番役として残るのが恵比寿様だと言われています。残っている恵比寿様に五穀豊穣などを祈願します。
収穫祭
収穫祭は農作物の収穫の時期に行われるお祭り。地域によって日付は異なりますが、概ね10月~11月の秋の時期に行われます。
紅葉狩り(もみじがり)
紅葉狩りは秋に紅葉した葉を眺めたり、拾ったりする遊び。紅葉がきれいな秋の行楽シーズンに行います。特に日付やするべきことがが決まっているわけではありません。日本の秋の美しさを楽しむ行事です。気持ちの良い秋晴れの日に紅葉狩りに行ってみるのはいかがでしょう。
11月が旬の野菜11種
シメジ

一年中流通しているシメジですが、天然のブナシメジやホンシメジの旬は秋です。香りが良いので炊き込ごはんやお吸い物、あえ物などにして楽しみます。
マイタケ(舞茸)

マイタケも一年中流通していますが、天然のものは秋が旬です。煮ても炒めても楽しめます。鍋料理にも活躍します。
食用菊
食用菊は名前の通り、食用の菊の花です。指でつまむようにして花びらだけを取り、酢を入れたお湯で茹で、お浸しにして食べます。花色は黄色や薄紫色があります。
チンゲンサイ

チンゲンサイは夏から冬にかけて収穫できる青菜。葉野菜が少なくなってくる秋から冬にかけて活躍します。
ネギ

ネギはヒガンバナ科の植物。一年中流通していますが、秋から冬のネギは甘味が強く、おいしいのが特徴。鍋料理にも欠かせない野菜です。
カブ

カブはアブラナ科の一年草。初夏と秋が旬の野菜です。カブは葉もおいしく食べられます。
サツマイモ

サツマイモは秋に土の中に実るヒルガオ科の野菜。子供のころに遠足でサツマイモ堀りを経験した方も多いのではないでしょうか。蒸したり焼いたりして楽しめます。
サトイモ(里芋)

サトイモは肥大した地下茎を食用にする野菜。ぬめりと歯ごたえが魅力です。煮物のほか、茹でておつまみにしたり、揚げたり炒めたりして楽しみます。
レンコン(蓮根)

レンコンは食用のハス(蓮)の肥大した地下茎です。加熱時間や調理方法でシャキシャキとした歯ごたえとほくほくとした食感の両方を楽しめるのも魅力です。煮たり炒めたりして楽しめます。
カボチャ

![]()
カボチャの収穫期は晩夏ですが、長く保存ができるので、野菜の少なくなる秋から冬に多く流通するようになりました。
ムカゴ

ムカゴはヤマノイモの仲間のつるに実ります。秋になるとつるの途中にムカゴが実っているのを見かけます。ごはんと一緒に炊くほか、揚げたり炒めたりして楽しめます。
11月が旬の果物(フルーツ)11種
ザクロ(柘榴、石榴)

ザクロはミソハギ科の落葉高木。秋に実る果実を食用にします。ザクロの果実は熟すと果皮が割れて、半透明で赤紫色をした宝石のような果肉が見える、とても美しい果物です。
アケビ

Adobe Stock
アケビはアケビ科のつる植物の果実。硬い果皮の内側に白いゼリー状の果肉が入っています。この甘い果肉を楽しみ、中の小さなタネは吐き出します。
キウイ

キウイはマタタビ科のつる植物。一年中流通していますが、日本では秋に収穫できます。果実は甘く瑞々しいのが特徴です。
栗(クリ)

栗は秋の味覚の代表のような果物です。加熱すると甘くほくほくとした食感を楽しめます。栗ご飯のほか、焼き栗や甘露煮など、楽しみ方がいっぱいです。
柿

秋にオレンジ色に色づく柿は日本の秋を象徴するような果物です。瑞々しく、独特の歯ごたえが魅力です。
ライム

ライムは明るいグリーンがきれいなミカン科の果物。果皮がグリーンの状態で収穫し、料理や飲み物の香りづけに使用します。
カボス

カボスは小ぶりな果実がかわいらしいミカン科の常緑低木。柑橘類の中では比較的早く収穫できる種類です。香りが良いので料理の香り付けや臭み消し、薬味など幅広く利用できます。
ダイダイ

ダイダイはミカン科の常緑高木。橙色の語源にもなっているように、きれいなオレンジ色の果実を実らせます。英名はビターオレンジ。マーマレードなどに加工して楽しみます。
ユズ

ユズは香りが良いのが特徴のミカン科の常緑高木。主に果皮や果汁を香りづけに使用します。強い香りで邪を払うとも言われています。
クコ

クコは秋に赤い果実を実らせる落葉低木。クコの実はビタミンB群やCを多く含み、ゴジベリーという別名で美容フードとして人気があります。
カリン

カリンは山野に自生する落葉高木。カリンの果実は生食はできませんが、香りが良いので、果実酒やシロップ漬けにして楽しみます。
11月が旬の魚(魚介)7種
秋鮭(アキザケ、アキジャケ)

秋に産卵のために川に戻ってきたサケを秋鮭と言います。産卵前なので身がしまっているのが特徴。塩焼きの他、煮たり焼いたりして楽しめます。
ニシン
秋から冬のニシンは身がしまり脂がのっていておいしいと言われています。塩焼きの他、ニシン鍋などにして楽しめます。
サンマ
サンマは日本の秋の味覚。近頃では漁獲量が減ってきていることでも話題になっています。それでも秋になると食べたくなる魚の一つ。ポピュラーな塩焼きの他、揚げたり蒸したりして楽しめます。
カレイ

秋のカレイは冬の産卵を控えているので、身がしまっていておいしいと言われています。カレイは煮魚のほか、揚げてもおいしくいただけます。
アンコウ

アンコウは歯ごたえのある白身がおいしい深海魚。お刺身や鍋料理が有名です。アンコウの肝を蒸したあん肝はお酒が止まらなくなる珍味です。
ズワイガニ
ズワイガニは漁期が決められている魚介。地域にもよりますが、11月~初春までです。国産のズワイガニは冬に楽しみたい味覚です。
カワハギ
淡白な白身がおいしいカワハギは冬が旬の魚です。肝醤油でいただく薄造りのお刺身は絶品です。
11月が旬の花や木17種
キク(菊)

菊の花の咲く季節は秋、9月~11月です。特に秋も深まり周囲の木々が紅葉し始めた頃、菊も美しく咲き誇ります。
リンドウ

リンドウは秋に青紫色の花を咲かせる多年草。花色は他にピンクや白などがあります。9月頃から咲き始め、秋も深まる11月頃まで花を楽しめます。
コスモス

コスモスは色のバリエーションが豊富なキク科の一年草。秋を代表するような花ですが、最近は夏から開花する品種も流通しています。
アメジストセージ

アメジストセージはシソ科の多年草。ベルベットのような質感の紫色の花が美しいセージの仲間です。
シュウメイギク

シュウメイギクは秋に白やピンクの花を咲かせる、キンポウゲ科の多年草。菊の仲間ではありません。風に揺れる楚々とした姿が美しい花です。
ススキ

ススキはイネ科の多年草。秋の七草にも数えられています。風に揺れ、金色に輝く花穂が美しい、風情ある草花です。
クランベリー

クランベリーはツツジ科の低木。果実は酸味が強く生食できないので、主に観賞用として育てられます。秋に赤く色づく果実がかわいらしい花木です。
カンボク

カンボクはガマズミの仲間の落葉低木。春に白い花を咲かせ、秋に真赤な果実を実らせます。宝石のような赤い果実は見るからにおいしそうですが、食用にはできません。
ナツハゼ

ナツハゼはツツジ科の落葉低木。秋に紅葉する葉と黒く色づく果実が美しい花木です。紅葉したナツハゼの葉はブルーベリーの葉を思わせます。黒く熟した果実は酸味が強く、食用にはなりません。
ガマズミ

ガマズミはレンプクソウ科の落葉低木。秋に宝石のような真赤な果実を実らせます。ガマズミの果実は酸味が強く生食できません。果実酒などにして楽しみます。秋の太陽を浴びて光るガマズミの果実は見とれるほどの美しさです。
ムラサキシキブ

ムラサキシキブはシソ科の落葉低木。春にピンク色の小さな花を咲かせ、秋に紫色の小さな果実を実らせます。紫色の果実は珍しいことと、日光を浴びて照り輝く様子が美しいので人気の花木です。果実は鳥が好んで食べますが、人間は食用にはしません。
ソヨゴ

ソヨゴは常緑の葉と冬の赤い実が特徴のモチノキ科の高木。光沢のあるグリーンの葉の間から見える真赤に色づいた小さな実がかわいらしい庭木です。
ツリバナ

ツリバナはニシキギ科の落葉低木。名前の通り、枝からぶら下げるように果実を実らせる姿が魅力です。
ハナミズキ

ハナミズキは春の花、夏のグリーン、秋の紅葉と赤い実と、四季を通して魅力のある花木です。秋の赤く紅葉した葉と真赤な実ははっと目を引く美しさです。
マユミ

マユミはニシキギ科の落葉低木。秋にピンク色の皮が割れて朱色のタネを見せる、とても美しい庭木です。
カラスウリ

カラスウリは日本の山野に自生するウリ科のつる性多年草です。カラスウリの種は大黒様のお腹のようで縁起がいいとか、打ち出の小槌のようだと言う理由から、お財布に入れておくと金運が上がると言われています。
ローゼル

ローゼルはアオイ科の多年草。ハイビスカスティーの原料にされています。秋に熟す赤い実がユニークな植物です。
11月が旬の食材レシピ2種
むかごのオリーブオイル揚げ
材料
- むかご 食べたいだけ
- オリーブオイル 適量
- 塩 適宜好みで
作り方
- むかごは洗って水気を切っておく
- フライパンにオリーブオイルをひたひた程度入れ、むかごを揚げるように炒める
- 3~4分炒めたら、かじってみて火が通っているようであれば塩をふって出来上がり
- おやつにもおつまみにもなる一品です。むかごとオリーブオイルの香ばしさを楽しめます。
かえしを使ったポン酢の作り方

材料
- しょうゆ 100ml
- 砂糖 20g
- みりん 20ml
- 柑橘類の果汁や酢 100ml
作り方
- しょうゆと砂糖を小鍋に入れて温めながら砂糖を溶かす
- 砂糖が溶けたらみりんを加え、沸騰させないように5分程度煮詰めてアルコールを飛ばしてかえしを作る(※ここで出来たかえしは出汁と混ぜてめんつゆにも使用出来ます)
- 火から下ろし、かえしの粗熱が冷めたら柑橘類の果汁を混ぜて清潔な容器に入れて保存する
かえしを果汁と混ぜるので、甘味のあるまろやかな味わいのポン酢です。
秋も終りに近づく11月は実りの季節。赤や黄色に色づいた葉を愛で、秋の実りを味覚で楽しみ、乾燥した風を浴びて、過ぎ行く秋を満喫しましょう。
▼編集部のおすすめ
関連ワード
今月のおすすめコンテンツ
「11月が旬の野菜、果物、魚、花46種。五感全部で実りの秋を楽しむ」の記事をみんなにも教えてあげよう♪