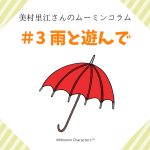リビングにおすすめの観葉植物、基本的な管理方法
更新
公開

みなさんにとってリビングはどんな場所ですか?家族団らんで楽しく過ごす場所であったり、のびのびとリラックスできる場所であったり。
リビングをさらに心地良い空間にしたい。そんなときにおすすめなのが観葉植物。観葉植物はインテリアとしてはもちろん、私たちの暮らしに癒しと潤いを与えてくれます。リビングに合った観葉植物を選んで飾ってみませんか?
リビングをより心地良い空間にしてくれる観葉植物と基本の管理方法をご紹介します。あなたのお家のリビングにぴったりな植物との出会いがあるかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。
目次
インテリアに映える。リビングにおすすめの観葉植物
エバーフレッシュ

エバーフレッシュはマメ科の観葉植物。ボリビア、ブラジルが原産の高木で、ネムノキによく似ていることから「アカサヤネムノキ」が和名です。

夜になると葉を閉じる「就眠運動」を行う植物でもあります。
人と同じく夜に寝て朝に起きる……という、なんだか一緒に生活しているような気持ちになりますね。

ひらひらと茂った小さな葉は、リビングの窓辺などに置くと、お日さまが入った時に素敵な影が楽しめておすすめです。
就眠運動を見れたり、シルエットを楽しめたりとエバーフレッシュは人気がありますが、枯らしてしまったという声も多い観葉植物でもあります。店頭の環境と家の環境とのギャップによって、枯れたり葉を落とすことも。
また、置いている場所の確認をしてみてください。エアコンなどの風が直接当たる場所や、日当たりや風通しの悪い場所は避けてください。
エバーフレッシュは基本的に生命力の強い植物なので、生育環境を整えて根気よく育ててあげると新芽を出し、馴染んでくれることでしょう。
▼エバーフレッシュの詳しい管理方法はこちら
パキラ

パキラは中南米原産のアオイ科の植物です。
高さ15センチほどの小さいものから大人の身長以上もある大きいものまで様々なサイズが出回っているので、デスクや棚の上などの小さなスペースからリビングのシンボルツリーになど、置き場や用途に合った大きさを選ぶことができます。
サーフボードのようなシルエットの葉は存在感があり、ライトグリーンで部屋を明るくしてくれます。どんなスタイルのリビングにも馴染みやすいです。
▼パキラの詳しい管理方法はこちら
ユッカ

ユッカは中央アメリカ原産の観葉植物です。別名「青年の木」とも呼ばれています。シャープな葉姿は、クールなスタイルのリビングやオフィスにもおすすめ。
スっと上に伸びるように生長するため、幅を取らずに飾ることができます。ユッカは乾燥に強い観葉植物ですが、葉水はお忘れなく。
▼ユッカの詳しい管理方法はこちら
ベゴニア

ベゴニアの最大の特徴と言えば、「日が入る場所ならば育てられる」ということ。ベゴニアは柔らかめの光を好むため、多少薄暗い環境でも育てることができます。 あまり日当たりが良くないリビングでも楽しむことができるんです。葉の柄や形も個性的で、さらに花を楽しめる種類もあります。初心者でも育てやすいのも人気の理由だと思います。
▼ベゴニアの詳しい管理方法はこちら
ガジュマル

沖縄に自生しているガジュマル。最大の特徴は、個体によって面白い形が楽しめる太い根です。丈夫で、育てやすく、初心者の方にもおすすめ。ユニークなフォルムをリビングでリラックスしながら観賞するのもいいですね。写真は手で持てるサイズですが、大きいサイズのガジュマルも流通しています。

シンプルなお部屋には柄物の鉢に植えてみたり、和風のお部屋にはモダンな陶器鉢に植えて盆栽仕立てにしてみたり。基本的にどんなテイストのリビングにも馴染みやすい観葉植物です。
▼ガジュマルの詳しい管理方法はこちら
ビカクシダ

独特な葉の形と容姿が人気の観葉植物ビカクシダ。コウモリランとも呼ばれます。高温多湿に強く、耐陰性もあり、初心者の方でも育てやすい植物です。

飾り方次第でどんなテイストのリビングにも合わせられるビカクシダ。ポスターや写真などを貼っている壁に、板付けに仕立てたビカクシダを掛けるとより雰囲気のある空間に。
ハンギングや板付けにした飾り方は、個性的な葉の形をより楽しむことができ、ビカクシダの魅力を引き出すことができます。
▼ビカクシダの詳しい管理方法はこちら
サンスベリア

空気清浄効果もあるともいわれるサンスベリア。家族団らんで過ごすことの多いリビングにはぴったりの観葉植物ですね。肉厚の葉が上にすらりと伸びる独特なフォルムもインテリアグリーンとしてよく映えます。日光を好むので、リビングでは日当たりの良い明るい窓辺などに置くとよいでしょう。葉水は季節問わず1日一回がベストです。

低温に弱く季節によって水やりのタイミングを変える必要があるサンスベリア。生長期の春~秋は土の表面が乾燥してから2~3日後にたっぷりと。気温が10℃前後を切る冬は土が完全に乾燥してから水やりをしましょう。
▼サンスベリアの詳しい管理方法はこちら
シェフレラ(カポック)

育てやすく人気の定番観葉植物シェフレラは、中国南部~台湾が原産の観葉植物。カポックとは本来パンヤノキのことを指しますが、シェフレラ・アルボリコラの葉がパンヤノキに似ていることからカポックという流通名がついています。
シェフレラは耐陰性があります。そのため、少し暗めの場所でも育てることはできますが、日光が当たった方が健やかに育つのでなるべく日光が当たる場所に置いてください。

シェフレラは斑入りの品種もあります。リビングのちょっとした棚、お部屋の本棚などに雑貨と一緒に飾っても素敵。
▼シェフレラの詳しい管理方法はこちら
フィカスベンジャミンバロック

くるくるとカールした葉がキュートな観葉植物ベンジャミン・バロック。
ゴムの木の仲間フィカス・ベンジャミンの園芸品種で、葉が内側にくるくると丸まっているのが特徴です。テレビ台の横、棚の上、床など……。リビングの一角に置くだけでお部屋の印象がかなり変わります。

水切れを起こすと葉がどんどん落ちてしまうため、水やりの管理をしっかり行いましょう。また、分枝しやすい品種でもあるので、樹形が崩れてきたら定期的に剪定をしてやるとよいでしょう。
▼ベンジャミンバロックの詳しい管理方法はこちら
フィカス・ウンベラータ

大きなハート形の葉が特徴のフィカス・ウンベラータ。リビングのシンボルツリーとしても人気が高い観葉植物です。置き場所はレースのカーテン越しに日光が入ってくる明るい窓辺などがおすすめ。

フィカス・ウンベラータは寒さに当たると葉を落とすことがありますが暖かくなってくれば、また芽を出すようになりますので安心してください。
幅広で葉脈がしっかり見える葉は観察しごたえがあるので、毎日の葉水する時間が楽しみになりますね。リビングというリラックスできる空間に、さらなる癒しをもたらしてくれる観葉植物です。
▼フィカス・ウンベラータの詳しい管理方法はこちら
フィカス・ベンガレンシス

ゴムの木の仲間フィカス・ベンガレンシス。観葉植物でポピュラーなゴムの木の中でも、フィカス・ウンベラータと並ぶほど大人気の観葉植物です。たまご型の形の葉が丸く柔らかい雰囲気を演出してくれます。フィカスウンベラータ同様、お部屋のシンボルツリーにぴったり。

大型のものはもちろん、小~中型のものも雑貨と一緒に飾ったり、棚の上に飾りやすいのでおすすめ。ぱりっとした葉には光沢があり、インテリアグリーンとしてリビングで存在感を放ちます。
▼フィカス・ベンガレンシスの詳しい管理方法はこちら
モンステラ

大人気の王道観葉植物モンステラ。切れ込みが入った葉が特徴です。
海外のリゾート風のリビングやアジアンテイストのリビングにしたいときに取り入れたいインテリアグリーンです。雑貨や少し派手な柄物のラグとも相性抜群。一緒に飾ってコディネートしやすいのもポイントです。

また、小さい株を買ってもすぐに大きく育つほど生長が早く、育てやすい観葉植物でもあります。株分けして増やせるので、リビングが緑であふれていくのも楽しみのひとつになるかもしれません。
▼モンステラの詳しい管理方法はこちら
アイビー

室内インテリアグリーンとして人気のつる性観葉植物アイビー。耐陰性もあるため北向きのお部屋でも育てやすい丈夫な観葉植物です。

アイビーは葉の形も模様も種類が豊富なので、リビングの雰囲気に合わせて選べる楽しみがあります。
下に垂れ下がるように生長していく特性を活かして窓辺に吊るして飾るとお部屋のアクセントにもなり、おすすめ。

もちろん、棚や卓上に置いてつるが生長していく様子を楽しむのも素敵。
▼アイビーの詳しい管理方法はこちら
観葉植物の基本的な管理方法
置き場所
明るさ
観葉植物の種類によって必要とする光の量は異なってくるので、種類に合わせて置き場所や光の入り具合を調整するようにしましょう。リビングという一部屋のなかでも日が入る明るい場所から、あまり光が入らない場所まで明るさは様々です。
種類にもよりますが、直射日光は葉焼けの原因になることも。そんなときはレースのカーテンで遮光して、柔らかな光を当てるようにするとよいでしょう。
また、時間によって部屋に光が差し込む場所も変わります。
日光浴をさせたい時、もしくは強い西日を避けたい時など……。そんな時は無理のない範囲で植物の場所を変えてやるのがベストです。
また、日当たりがイマイチなお部屋でも、「耐陰性」という日陰でも比較的育つ性質を持った観葉植物を選ぶとよいでしょう。その場合1週間に1~2回明るい場所に置くようにバランスをとると、植物がより元気になります。
▼日当たりがイマイチなお部屋に!耐陰性があるといわれる植物
風通し
植物を育てる上で大切な要素として「風通し」があります。日光、水やりと違って間違ったら枯れるということは少ないものの、暑い日の水やりをした後などは水が蒸れて根腐れの原因になったり、植物にとって良くない状況になってしまいます。風通しを良くすることで病害虫の予防にもなります。
風通しの良い窓辺に置いたり、こまめに部屋の空気を入れ替えたりしましょう。風通しの良さは植物にとってはもちろん、人にとっても心地よいはず。無理のない範囲で風通しを意識して植物とのより良い暮らしを楽しみましょう。サーキュレーターを使って空気を循環させるのも◎
▼風通しの良さについて
水やり

水やりは「土が乾いたらたっぷりと」が原則です。
表面の土や鉢底の土を触ってみて完全に乾いている状態が水やりのとき。内側まで乾いているかが分かりにくく不安な場合、割りばしなどを土に挿してみて、抜いた時の状態を観察して水やりの判断をしてみてもいいですね。土に挿して抜いた時に土が付いてきたり、割り箸が湿っているようならばまだ水分はあります。
土が完全に乾いていたら水は「鉢の底から水が出るまで」たっぷりと与えます。水が鉢底から出る=鉢全体に水がいきわたっているということ。さらっと水やりしただけでは、根がある部分まで水がいきわたらず、水やりしたとは言い切れません。
植物に合わせた水やりを
「乾いたらたっぷりと」が基本ですが、たまに乾燥が大好きで乾いてから数日は水をやらない植物や、水が大好きで乾いたら枯れてしまうので乾く前に水やりが必要な植物もあります。育てている観葉植物の種類を調べて適した管理をしてください。
葉にも水を与える「葉水」

植物によっては葉にも水やりが必要なものもあります。葉に霧吹きを使って水を吹きかけ「葉水(はみず)」をしましょう。過度な乾燥は害虫の発生の原因になります。葉水をし適度な湿度を保つことは害虫の予防になります。根からあまり水を吸わない観葉植物やエアプランツ(ティランジア)なども葉水で必要な水分を補えます。
リビングにぴったりの観葉植物は見つかりましたか?
植物はそれぞれ合う環境が違います。枯れてしまうと自分には植物を育てるのは向いてないと思ってしまうこともあるかもしれません。でも他の種類なら育つということもあるので、めげずに挑戦してみましょう。いつか環境に合う種類も見つかるはずです。
リビングに観葉植物を取り入れて、植物と過ごす空間の心地良さをぜひ体感してみてください。
LOVEGREEN STOREでもいろいろな観葉植物をお取り扱い中です!
▼編集部のおすすめ