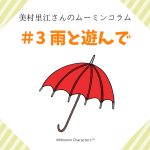日当たりの悪いお部屋に向いてる観葉植物25選!上手に育てるコツとは?
更新
公開

![]()
観葉植物を部屋に取り入れたいけど、日当たりが悪いから育てられない。そう思っている方も多いのではないでしょうか。基本的に観葉植物は日当たりの良い場所を好みますが、中には多少日当たりが悪くても育つ観葉植物があります。今回は日当たりの悪い部屋で観葉植物を育てるポイントと耐陰性のある観葉植物をご紹介します。
目次
観葉植物の耐陰性

観葉植物の耐陰性とは日照が少ない日陰のような場所でも生長する性質のことで、耐陰性が(強い/弱い・高い/低い・ある/ない)と言った表現をします。一般的に熱帯雨林など日陰~半日陰のような環境に分布している観葉植物は耐陰性が高いとされています。また、本来は直射日光の当たるような場所に生えている植物でも日本の日差しがきつく、半日陰のような場所でないと葉焼けを起こしてしまうような観葉植物も耐陰性があるものとして扱われます。
観葉植物の多くは耐陰性があるため日陰でも枯れずに生長することができます。ただし、枯れはしなくとも徒長する場合が多いです。そのため、まずは出来るだけ観葉植物を徒長させずに育てる方法をご紹介します。
日当たりの悪い部屋で観葉植物を徒長させずに育てる方法
日当たりの悪い部屋というのにもいくつか種類があると思います。大雑把に分けるとこの3つではないでしょうか。
-
- 朝(夕方)の2~3時間だけ直射日光が入ってくる
- ベランダ(庭)にだけ直射日光が差し込む
- 直射日光が一切入ってこない
1.朝(夕方)の2~3時間だけ直射日光が入ってくる
この場合は耐陰性の高い観葉植物であれば生長することができます。出来るだけ窓際の日当たりの良い場所に置き、風通しを良くさせましょう。サーキュレーターなどで弱い風が当たるようにするとなお良いです。
週に2~3回程度外に出して日光浴をさせても良いです。室内の日陰よりも、室外の日陰の方が明るいため日照不足を少しだけですが緩和できるでしょう。
2.ベランダにだけ直射日光が差し込む
ベランダ(または庭)にだけ直射日光が差し込む場合は、常に室内に置いておくのは避けましょう。週の2~3日を目安に観葉植物を屋外に出して日光浴させると良いです。室内に入れる時も出来るだけ窓際の明るい場所に置くようにしましょう。
3.直射日光が一切入ってこない
直射日光が一切入ってこない場合は、観葉植物が日光不足で枯れたり徒長するおそれがあります。そのため照明などを使用して光合成の補助をする必要があります。
植物専用の育成ライトが販売されていますが、耐陰性の高い観葉植物であれば普通のLEDや昼光色の電球でも大丈夫です。
▼肥料と虫対策のおすすめアイテム

環境を整えるだけでなく、植物には栄養(肥料)や、虫対策のための殺虫剤も必要です。
オススメなのは、効果とデザインを両立した観葉植物のケアシリーズ「MY PLANTS」。使いやすくお洒落な肥料と殺虫剤3アイテムが、観葉植物をよりスマートに楽しむアシストをしてくれます。
①葉や土にシュッとかけるだけのスプレー肥料
「 MY PLANTS すばやく元気を届けるミスト」
②土の上に置くだけで長く丈夫に育てるタブレット肥料
「 MY PLANTS 長く丈夫に育てるタブレット」
③観葉植物に発生する虫を退治する殺虫スプレー
「 MY PLANTS 虫からやさしく守るミスト」
日陰にも耐える、耐陰性のある観葉植物たち
定番の観葉植物でも日当たりの悪いお部屋にぴったりの種類はたくさん
アマゾンなどの熱帯雨林に生えている観葉植物はもともと日陰のような場所に生えているため耐陰性が高く、比較的暗めの室内でも育てやすいです。
ポトス

ポトスはサトイモ科の観葉植物です。室内の明るい場所を好みますが、耐陰性が強いためある程度の日陰のような場所でも育てることが出来ます。また、ポトスはつる性の観葉植物で支柱などで上へ伸びるように誘引すると葉が大きくなり、下垂するように育てると葉が小さいまま伸びていきます。
水やりは土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出る位たっぷりと水やりをしましょう。水やりのときに霧吹きなどで葉水を一緒に行うとハダニなどの害虫予防になります。
ポトスは水耕栽培も出来るため、伸びすぎた茎を剪定して水耕栽培にするのも良いでしょう。水耕栽培を数株作り、部屋の色々な場所に置いてどこが一番ポトスに合っているのかを探すのも面白いです。
ホヤ

ホヤは、キョウチクトウ科の常緑つる性低木で、別名「サクララン」とも呼ばれています。
日光を好みますが、真夏の直射日光で葉が傷むことがあるので明るい日陰が安心です。ある程度の日陰には耐えられます。耐陰性は強いですが、日によく当てることでが花付きはよくなります。花付きにこだわらなければ、観葉植物と割り切って日陰でも十分育ちます。
テーブルヤシ

テーブルヤシは、ヤシ科・カマエドレア属の観葉植物です。一般的にテーブルにおけるほどちいさいことからテーブルヤシと名づけられました。
夏場は南国のヤシの雰囲気を出してくれます。ヤシという名前がついているので日光に強いと思われがちですが、自生地では明るい日陰のような場所に生えているため直射日光や強い日差しは苦手です。水はけがよい状態にして明るい日陰で育てましょう。
水やりは夏の生育期には用土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。冬は土の表面が乾燥してから2~3日経ってから水をたっぷり与えます。
モンステラ

モンステラはサトイモ科に分類される熱帯アメリカ原産の観葉植物です。
大きな葉に切れ込みが入る姿は非常に人気があります。また、品種もいくつかあり、大型になるものや小型のもの、モンステラ・デュビアといった一見モンステラに見えない品種もあります直射日光が苦手で、半日陰のような場所を好みます。生長も早く強健なため、初心者の方にもおすすめです。
葉が広く大きい為ホコリが溜まりやすいです。そのため葉水をするときに濡らしたティッシュペーパーやハンディモップなどで葉に溜まったホコリを掃除してください。
アグラオネマ

熱帯アジアに分布しているサトイモ科の観葉植物で、約50種あると言われています。斑が入る葉は非常に美しく、観賞価値の高い品種です。
耐陰性が強く、明るい室内ならば育てる事が出来ます。耐寒性(寒さに強い性質)が低く、冬場は室内の暖かい場所に置きます。しかし、エアコンなどの風が直接当たると枯れてしまうので、当たらないように注意します。
葉水を行うと葉が健康的に育つので、定期的に霧吹きなどで葉水を行ってください。
ガジュマル

ガジュマルは沖縄などにも自生しているフィカス属の観葉植物で日光を好みますが、強健で多少の耐陰性はあります。日が入りにくい場所でも、できるだけ明るい窓際に近いところが向いているかと思います。水やりは表面の土が乾いたらたっぷり水を与えます。
成長期には霧吹き等で空気中の湿度も上げて葉水を与えるとよいでしょう。葉水をあげることで害虫の被害を予防できます。
オキシカルジューム(ヒメカズラ)

ヒメカズラは直射日光は苦手な観葉植物です。耐陰性が強く、半日陰のような場所で育てることができます。乾燥は苦手な植物なので、霧吹きで葉水を定期的に行って空中湿度を高めてください。
ツルが伸びてきたら支柱などに誘引するか、ハンギングにするとよいでしょう。
シェフレラ(カポック)

暑さや寒さにも強く、日当たりを好みます。環境に対する高い順応性も持っていますので、日当たりの悪い窓際や半日陰でも育ちます。たまに窓際に置いて日光浴させてあげましょう。小さいサイズから育てると幹の形の変化を楽しめます。
水やりは土の表面が乾いてきたらたっぷり与えます。とくに生育期間である春から秋にかけては多めに与えます。冬は乾かし気味に管理します。茎が軟らかくて弱いため、上に伸びていくうちに自重で曲がってしまうため、支柱で支えましょう。
葉に斑が入っているホンコンカポックという品種もあります。カポックは品種がとても多いので、お気に入りの種類を見つけてみて下さい。
アジアンタム

アジアンタムはイノモトソウ(ワラビ)科の観葉植物です。小さな葉がとても爽やかですよね。直射日光が苦手なため、避けて管理しましょう。室内の明るめの場所なら育つので半日陰が向いています。
シダの仲間なので多湿を好み、乾燥は苦手です。霧吹きなどで頻繁にお水を上げてください。葉水をたくさん与えましょう。
夏場は気温が高く、土が乾きやすいので朝晩あげてもいいと思います。一度、水不足が起きると葉が縮んでしまい回復が難しいです。こまめな水やりが重要です。
シンゴニウム

シンゴニウムは強い直射日光に当てると葉焼けしてしまいます。耐陰性があるため日当たりの悪い窓際でも育てられます。寒さには弱く、10℃以下になる場合は暖かい場所で管理しましょう。
春~秋の成長期は土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。高温多湿を好むため、こまめに葉水を与えてもよいでしょう。日が当たる方向へ伸びていきやすいので、定期的に鉢を回転させてバランスよく日を当ててあげましょう。
ツデー(タマシダ)

直射日光に当たると葉焼けをします。耐陰性が強く、日陰~半日陰が好ましいです。屋外の場合は日陰で管理しましょう。乾燥が苦手で、水分が不足していると葉がパリパリになりパラパラと落ちます。水が切れないようにするのがキレイに育てるポイントです。光沢のあるグリーンはひとつあるだけでも空間をぱっと明るい印象に変えてくれます。浴室にもグリーンが欲しい時はオススメの植物です。
また、葉に斑が入った斑入りタマシダなどもあり、こちらは通常種とはまた違った美しさがあります。斑入りですが、通常種と同じく強健なため、育てやすいシダ植物と言えます。
アスプレニウム

アスプレニウムは常緑多年性の着生シダの仲間です。明るい日陰を好みます。耐陰性がありますので、暗めのお部屋でも育てられます。観葉植物はいい運気を出すといわれていますので、運気の入り口である玄関に置いてみるのもいいかもしれません。
水やりは鉢土の表面が乾いたらたっぷりと与えます。春~秋にかけては毎日、冬は2、3日に1回行いましょう。冬に水をやり過ぎると、根腐れを起す可能性があります。空中湿度を好みますので、水やりの際には、葉水も行いましょう。日本にも沖縄を始めとした温暖な地域にオオタニワタリという大型のアスプレニウムが自生しています。
また、葉が波打っていて美しい姿をしているアスプレニウム・エメラルドウェーブという品種は園芸店などでも売られており、メジャーなアスプレニウムの品種です。
セラギネラ

セラギネラはイワヒバ科に分類されるシダ植物の一種です。日光を好みますが直射日光は葉焼けの原因になることがあります。耐陰性があり、室内の暗い場所でも枯れることはありませんが、日光不足になると葉の色が悪くなります。たまに窓際において優しい光に当ててあげましょう。
湿度も高めを好むので、霧吹きなどで葉水を定期的に行い空中湿度を高めに維持すると調子が良いです。
フィカス・アルテシマ

ゴムの木は正式名称をフィカス・アルテシマ(アルテシーマ)と言います。強健で育てやすいため初心者の方におすすめです。耐陰性があるため、明るい室内で育てる事が出来ますが、ある程度の日光を当てた方が株が引き締まったかっこいい姿になります。
オリヅルラン

オリヅルランは、ある程度の耐陰性があります。日当たり良いところを好み、真夏以外はできるだけ日光に当てるといいです。しかし、日当たりが悪いお部屋の場合は窓際に置いて出来るだけ日が当たるようにしてください。オリヅルランは、ランナーというツルようなものを伸ばして子株を付けます。子株の形が折り鶴に似ていることが、名前の由来だそうです。
英名はスパイダープラント(Spider plant)といい、草の姿がクモに似ていることが由来の一つのようです。ランナーが伸びてきたら吊るしてアレンジすることもできます。オリヅルランはNASAが選んだシックハウス症候群にも有効で空気清浄効果があるそうです。
子供にも安全とされている観葉植物の一つでもあります。引越しや新築の新居で発症するケースもあるそうです。
オリヅルランは子株を水耕栽培することも出来るので、増えたオリヅルランは捨てずに水耕栽培してみてはいかがでしょうか?
シュロチク

シュロチク(棕櫚竹)は葉の形がシュロ(棕櫚)の葉に似ていることから名づけられたとされています。直射日光には弱いものの、寒さ暑さには非常に強いので、明るい日陰に置いておけば常に新鮮なグリーンを目にすることができます。その育てやすさから、観葉植物を育てるのが苦手だという方人もおすすめです。
コウモリラン(ビカクシダ)

葉の形がコウモリに似ていることからコウモリランと呼ばれていますが、蘭の仲間ではなくシダの仲間になります。
日光を好みますが、夏の直射日光には弱いです。日陰すぎると調子を崩すため、半日陰や窓際がいいかと思います。苔玉にしたり板付けにしたりと環境や状況に合わせてアレンジして育てることができます。
品種も多く、愛好家も多いです。
クッカバラ

クッカバラはサトイモ科フィロデンドロン属の植物です。明るい場所を好みますが耐陰性があるため明るい日陰のような場所で大丈夫です。耐寒性もあり、育てやすいです。生育期にはとてもよく育つので、成長が楽しめます。水やりは、土が乾いてからたっぷりと与えます。水のあげすぎは根腐れしますので気を付けましょう。湿度があると気根が出てきてどんどん成長するので、邪魔な場合は剪定してしまいましょう。
気根をうまく生かした盆栽仕立てなどは非常に画になりそうですね。
クサソテツ

クサソテツは名前にソテツと入っていますが実際はシダの仲間です。
そのため直射日光が苦手で、半日陰から日陰の湿気のあるところを好みます。湿気を好むので、浴室にはおすすめです。トイレにもグリーンを取り入れたい場合は、利用してみても良いと思います。ただし、窓がなく締めきってしまう空間の場合は蒸れてしまうことがあるので、避けた方がよさそうです。
ザミアフォーリア

明るい場所を好みますが、日が当たりすぎると葉焼けしてしまいます。レースのカーテン越しくらいの明るい日陰程度の光のほうが葉のツヤもよく育ちます。ある程度の日陰にも耐えられます。
まっすぐ育ち葉も上に向かって生えています。観葉植物の中でもよりいい運気を運んできてくれそうです。寒さにはあまり強くはありません。10℃で生育が止まり、休眠し、5℃以下になると枯れてしまう恐れがあります。気温が下がってきたら暖かい場所で管理しましょう。
水やりは、土の表面が乾いてからたっぷりと与えます。やや乾燥気味に育てます。冬場は暖房で暖かい部屋の場合は通常の水やりでよいですが、そうでない場合は月1、2回程度で様子をみて与えましょう。
花咲く観葉植物、ベゴニアは日当たりの悪いお部屋でも活躍
最近、観葉植物として注目されているベゴニア。花が咲く楽しみもあります。
柔らかめの光を好むため、多少薄暗い環境でも育てることができ、日当たりの悪い場所でも育てやすいです。また、水やり頻度も少なくて済むので初心者さんにもおすすめです。
モロッコ

モロッコは葉がアースカラーでナチュラルなインテリアにマッチするベゴニア。ベゴニアの中でもより耐陰性があります。乾燥にも強いので、水やりのタイミングがわかりにくいと感じている初心者さんにもおすすめです。
ニューファッション

黒っぽい葉は、光の当たり方で青くなります。その姿は、隠れた宝石を探すよう。
流れ星

生産者花郷園オリジナル品種の「流れ星」を購入できる場所はごくわずか。水玉模様の葉はそこにあるだけで絵画のよう。流れ星は花を咲かせる時、ハート型の雄花が咲いては散ってを6回繰り返し、最後のフィナーレで雌花が咲き、その期間は約2ヶ月。
ひとみ

ちょっぴり日が当たりにくいようなお部屋でも生長してくれるので、瓶に入れてテラリウムにしてテレビ台の横や棚に飾ってみるのもよいかも◎
ドレゲイ

コンパクトに育てることができ、葉は紅葉のようなフォルムで涼しげな印象もあります。数多いベゴニアの種類の中でも、まだ数が少ないのが球根性。球根性ベゴニアと言っても、球根ではなく球根のように育っていくと基部(根元)が太っていき、水分を蓄えていきますので、他のベゴニアより水やりは少なくても大丈夫です。
気になった観葉植物はありましたか?それぞれの観葉植物の性質をみて置く環境や管理に気をかけてあげてくださいね。
▼編集部のおすすめ