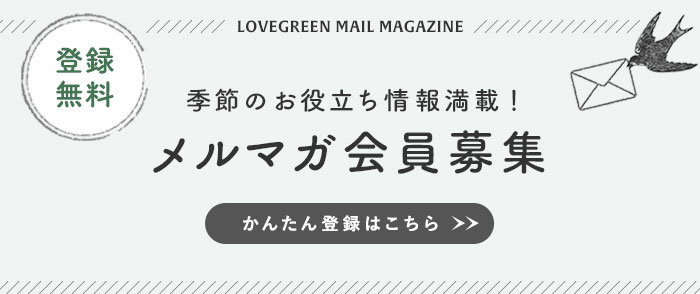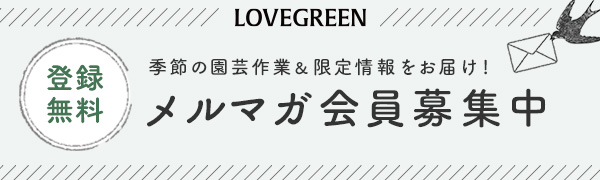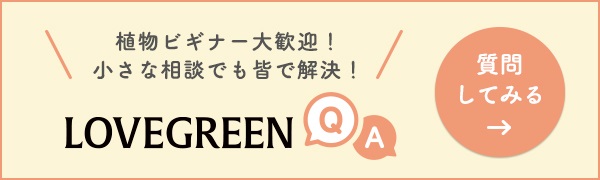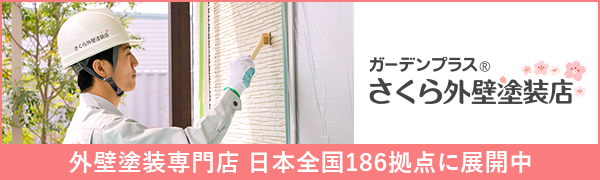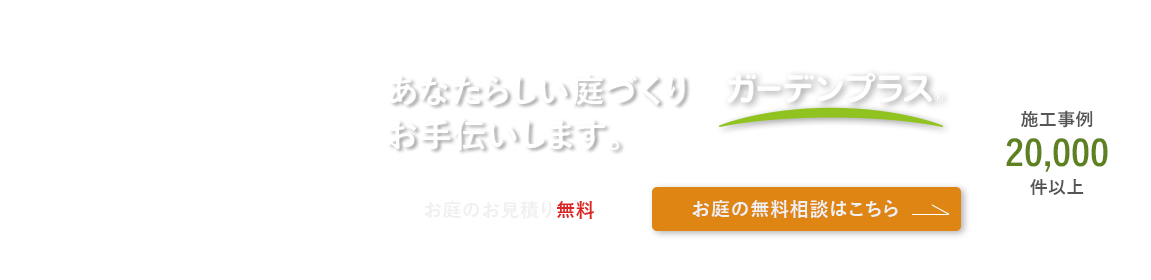観葉植物とは?初心者向けの定番から個性派まで。人気の種類と基本の育て方
LOVEGREEN編集部
このライターの記事一覧

日々過ごす空間に、彩りをプラスしてくれる観葉植物。ライフスタイルの変化に合わせて、観葉植物に出会った人も多いのではないでしょうか。
たくさんある観葉植物の中から定番人気をはじめ、ちょっと個性的なものまでおすすめの種類を集めました。初心者の方向けの基本的な育て方や、よくある事例なども一緒に紹介します。
目次
- 観葉植物とは
- <シンボルツリーにおすすめの種類>大きめの観葉植物
- <シェルフや窓辺にも置きやすい種類>中型の観葉植物
- <いろんな場所に置きやすい>小さめの観葉植物
- 観葉植物:ハンギングに向いている種類
- 観葉植物の基本的な育て方
- 観葉植物が枯れそうなときの対処法
- 観葉植物を上手く育てるポイント
観葉植物とは
観葉植物とは葉や草姿などを鑑賞する目的で育てられている植物のことを指します。
主に熱帯・亜熱帯地方が原産のものが多いですが、日本に自生している種類もあります。見た目や花の観賞価値が高い場合は観葉植物として流通しています。主に室内に飾ることが多いですが冬以外は屋外で育てることも可能な種類も多くあります。ホームセンター、園芸店の他にインテリアショップなどでも取扱があります。
土を使わない手軽な観葉植物シリーズ「&Green」
初めての観葉植物は「育てられるか不安」「育てやすい植物が分からない」など分からないことだらけ。そんな不安をすべて解消してくれるのが、今年誕生した観葉植物の新ブランド「&Green(アンド・グリーン)」です。土に代わる素材「パフカル」を使って水だけで育てることができ、お好みの観葉植物が3種セットで自宅に届く新しいグリーンブランドです。
<シンボルツリーにおすすめの種類>大きめの観葉植物
観葉植物は亜熱帯~熱帯に分布している植物がほとんどです。そのため生長すると1.5mを超えて大型になる観葉植物が多くあります。小さいサイズを購入しても、いずれは大きく生長します。(写真は中鉢くらいのサイズです)
サイズが大きい分、存在感を放ちます。購入する時は置く場所の広さを確認することをお忘れなく。
フィカス・ベンガレンシス

なめらかな幹に濃いグリーンの葉が広がるフィカス・ベンガレンシス。シンプルな見た目は様々なスタイルの部屋に馴染むことからインテリアグリーンとして常に人気があります。定番なだけあって、育て方も難しいことがないので、観葉植物を初めて育てる方にもおすすめの種類です。
シェフレラ(カポック)

インドアグリーンの定番種、シェフレラ(カポック)は中国南部~台湾が原産の観葉植物です。カポックとは本来パンヤノキのことを指しますが、シェフレラ・アルボリコラの葉がパンヤノキに似ていることからカポックという流通名がついています。斑入り品種のホンコンカポックやドワーフなど複数の品種が作られています。
観葉植物の中でも特に丈夫で育てやすいので、入門種としても最適です。暖かい地域であれば屋外越冬可能で、ビルの2階程度の高さまで育っているものもあります。
シェフレラ・アンガスティフォリア

シェフレラ属に分類されているアンガスティフォリアは、フィリピン原産の観葉植物です。木としての性質があるため高く生長します。斑入りの品種なども流通しており、カポックなどと比べて葉が細く繊細な印象です。性質はカポック同様に育てやすく、観葉植物ビギナーの方にもおすすめです。
樹高が高くなった場合は買ったときと同じぐらいの高さまで切り戻しをして問題ありません。本来は屋外の日当たりの良い場所を好む植物なので、なるべく日当たりの良い場所に置いてあげると徒長を防ぐことができます。
ツピタンサス(シェフレラ・ピュックレリ)

ツピタンサスはアンガスティフォリアと同じシェフレラ属に分類されている観葉植物。かつてはツピタンサス属に分類されていたため現在も旧属名のツピタンサスの名で流通しています。幅が広めな楕円形をした葉をしており、シェフレラ属の中でも大きな観葉植物です。樹形を曲げたりして育てられているものもあるため、自分の好きな樹形のツピタンサスを探してみては。
ある程度の大きさまで育ったツピタンサスは幹から脇芽を多く出すようになります。そのまま育てても良いですが、見た目が悪くようであれば脇芽を摘んでしまっても大丈夫です。
パキラ

日陰、乾燥に強くタフな性質のパキラ。100円ショップや雑貨屋などでも小苗が売られていることがあり、入手しやすく育てやすい初心者にぴったりな観葉植物です。パキラの原産はブラジルで、樹高が10m以上になる高木に分類されます。日本で観葉植物として鉢で育てている分にはそこまでの大きさにはなりませんが、数mの高さにはなります。ただしこれは環境を整え上手く育てた場合ですので、一般的な環境であればいきなり大きくなることはないでしょう。
徒長をすると葉の茎が長く伸びてだらしのない見た目になるため日当たりの良い場所に置くようにしましょう。
ゴムの木

観葉植物として流通するゴムの木はその名の通り天然ゴムの材料となる樹液を有している高木で、一般的にインドゴムノキをゴムの木と呼んでいます。熱帯地方原産でフィカス・ウンベラータやフィカス・ベンジャミンなど多くの種類があります。中でも斑入りのゴムの木(フィカス・ティネケ)はとても美しく、観賞価値が非常に高い観葉植物です。直射日光に近い強めの日差しを好むため、部屋に置く場合は窓際などのなるべく明るい場所か定期的に外に出して日光浴をさせるとよいでしょう。
フィカス・ウンベラータ

ハート形に見える葉が特徴のウンベラータは熱帯アフリカが原産です。ゴムの木に比べると葉が薄く、幅広で葉脈がしっかりと見えます。ライトグリーンの葉色で空間を明るくしてくれるのも良いところ。寒さに当たると葉を落とすことがあります。問題なく育っている場合、気温が上がれば再び芽を出すようになります。
フィカス・ベンジャミン・バロック

観葉植物の中でも特に変わった葉をしているベンジャミン・バロック。個性的な見た目ですが、ゴムの木の仲間です。フィカス・ベンジャミンの園芸品種で、葉が内側にくるくると丸まっているのが特徴です。他の観葉植物では中々見ることができない変わった見た目で人気があります。
くるくるとした葉がついて可愛らしいベンジャミン・バロックですが、水切れを起こすと葉がどんどん落ちてしまうため水やりの管理をしっかり行いましょう。他のフィカスに比べて分枝をしやすい傾向にあるため樹形が崩れてきたら剪定をして整えるとよいでしょう。
ガジュマル

これぞ、定番の観葉植物!1.5mも超えるの?となるガジュマル。自生地のガジュマルは20mほどにもなるほど大きく生長する植物なんです。ただし、私たちが鉢で育てている場合はそこまで大きくはならないのでご安心を。
丈夫な性質ですが、寒さにはやや弱め。春〜秋は屋外で管理しても大丈夫ですが冬には室内へ取り込むように。
ガジュマルは沖縄にも自生しており、太い根が特徴です。生長すると気根という根を出すようになります。育てやすく暖かい地域であれば屋外越冬が可能です。また、鹿児島県沖永良部島には樹齢100年を超えるガジュマルが生えており、観光スポットとしても人気です。盆栽仕立てにしたり苔玉にしたりと、アレンジも楽しめます。
ヘテロパナックス・フレグランス

観葉植物として最近見かけるようになったヘテロパナックスはインド半島~中国南部が原産の観葉植物。
ガジュマルに似た根をしていますがガジュマルよりも薄い幅広な葉で茎が細いです。また、ガジュマルよりも水を求める傾向があるように感じます。夏は水切れをしないように受け皿に水を張り、鉢を置いて底面給水できるようにしておいてもよいでしょう。日当たりが悪いと徒長しやすいため日当たりの良い場所に置くように。流通するのは少し珍しい種類になるため見かけたときはチェックしてみてくださいね。
エバーフレッシュ

エバーフレッシュはミクロフィラと同じマメ科の観葉植物です。ボリビア、ブラジルが原産の高木で、ネムノキに非常によく似ており、和名はアカサヤネムノキと言います。また、エバーフレッシュもミクロフィラと同じく人気が高いものの枯らす人が多い観葉植物です。これはエアコンなどの風が直接に置いていたり、風通しの悪い場所に置くことが原因であることが多いのですが、買ってきた環境と家の環境とのギャップによって葉を落とす場合があります。その場合、エバーフレッシュは基本的に生命力の強い植物であるため根気よく生育環境を整えて育てているとまた新葉が展開してきます。
また、和名にネムノキとあるとおり夜になると葉を閉じる就眠運動を行います。
コルディリネ・チョコレートクイーン

観葉植物としてだけでなく、お祝い品としても選ばれるコルディリネの仲間のチョコレートクイーンは、こげ茶色や緑、クリーム色などがマーブルに混ざり合う観賞価値の高い葉をしています。ドラセナ・チョコレートクイーンの名で流通することがありますが、チョコレートクイーンは地下に多肉質な根を作るというコルディリネ属の特徴を有しているため、正確にはコルディリネ・チョコレートクイーンになります。性質は丈夫で寒さに気を付ければ育てやすい観葉植物です。
モンステラ

観葉植物の中で定番中の定番であるモンステラ。実は20~40種類あると言われており、奥が深い観葉植物でもあります。よく流通しているモンステラはモンステラ・デシリオーサなどですが、ヒメモンステラと呼ばれるポトス程度の大きさの小さなモンステラもあります。また、斑入りのモンステラは非常に美しく、斑入りの観葉植物の中でも人気があります。性質は強健で耐陰性があるため、日当たりの悪い室内でも育てられます。とは言え、あまりに暗いと徒長し間延びした姿になります。なるべく日当たりの良い場所で育てましょう。
クワズイモ

根茎が芋のようになるクワズイモは、モンステラと同じく定番の観葉植物です。60cm程度の大きさの葉を展開することもあるようで、絵本の中に出てくる葉っぱの傘を再現することができるでしょう。また寒さに強く、暖かい地域であれば屋外越冬が可能なため観葉植物を冬に枯らすことが多い人はクワズイモがおすすめです。
アンスリウム

観葉植物として一般的に流通しているアンスリウムはアンスリウム・アンドレアナムなどの仏炎苞が赤く染まるものがほとんどですが、チョコレート色に染まるものや葉がビロードのような質感をしているものなど多種多様です。アンスリウムは冬の間に調子を崩す場合が多く、なるべく暖かい室内の日当たりの良い場所で管理します。
オーガスタ

観葉植物の中でも特に大きくなるオーガスタはオレンジ色の花を咲かせる極楽鳥花の仲間で、本種は白い花を咲かせ、現地だと10m近くにもなります。ストレリチア・ニコライがオーガスタの名称で流通していることがほとんどですが、本来オーガスタはストレリチア・アルバと呼ばれるものを指します。オーガスタは日光を好むので日当たりの良い場所に置くほうが綺麗な樹形を保てます。外で育てて必要な時だけ室内に入れるのも◎
テーブルヤシ

観葉植物として人気のあるテーブルヤシは中南米原産の小型のヤシです。他のヤシと比べて草丈が2~3m程度なので観葉植物として扱われています。日本でよく流通しているのは3~4号鉢に植わっている小苗で、数株まとめて植えられていることもあります。また、生長が遅いため扱いやすいのも人気の理由の一つです。
テーブルヤシはヤシですが直射日光は苦手で、明るい日陰程度の光が当たる場所を好みます。他の観葉植物同様にレースカーテン越しの窓際などに置くとよいでしょう。葉に埃が溜まりやすいので葉水をこまめに行うか掃除用のモップなどで定期的に埃を掃除してください。
アスパラガス・セタケウス

アスパラガスは野菜のイメージが強いと思いますが、こちらは食用のアスパラガスとは別物で、観賞用。葉に見えている部分は葉柄という葉と茎を繋げている部分が変化したもので、仮葉と呼ばれています。
日当たりの良い場所を好みますが、真夏の直射日光は葉焼けを起こす可能性があるのため、レースカーテン越し程度の柔らかい日差しが当たるようにしましょう。
環境が合うと意外と大きくなるので、形が崩れてきたら適宜剪定して整えてください。
アスプレニウム

観葉植物を育てたいけど日当たりの良い部屋が無いという人に人気のあるアスプレニウムは、アスプレニウム属に分類されるシダ植物の総称です。シマオオタニワタリやアスプレニウム・エメラルドウェーブなどが観葉植物としてよく流通しています。シマオオタニワタリは大型の観葉植物で、自生地では1.5mほどになります。耐陰性がありますがあまりにも暗いと徒長するのでレースカーテン越しの窓辺や明るい日陰程度の場所がよいでしょう。
<シェルフや窓辺にも置きやすい種類>中型の観葉植物
ベゴニア・流れ星

観葉植物の中でもじわじわと人気が上昇しているベゴニア。個性的な葉が特徴的です。水玉模様の葉はそこにあるだけで絵画のようなベゴニアの流れ星。流れ星は花を咲かせる時、ハート型の雄花が咲いては散ってを6回繰り返し、最後のフィナーレで雌花が咲きます。その期間は約2ヶ月。
ベゴニア・アルボピクタ

グングン生長するベゴニアのアルポピクタ。葉の生長がわかりやすく、笹の葉ベゴニアと遊び心ある呼び名もあり、涼しげに揺れる葉に癒されたり、七夕の時に短冊を飾っておうち七夕なんてのも良いかも。

花は珍しいカラーのライムグリーンの花を咲かせます。
アロカシア・アマゾニカ

観葉植物として定番のモンステラと同じサトイモ科に分類されるアロカシア・アマゾニカは、東南アジアが原産の交雑種で濃い緑色の葉に走る白く太い葉脈が魅力的です。葉裏は光沢のある紫色をしており男性からの人気も高い観葉植物です。育てやすく比較的安価で入手できるためサトイモ系の観葉植物を育ててみたい方におすすめです。夏場は水はけの良い土に受け皿などを使用して腰水で管理するとよいでしょう。花はサトイモ科特有の仏炎苞と肉穂花序を持った花になります。
アンスリウム・クラリネルビウム

アンスリウムと言えば真っ赤な仏焔苞をもった花が特徴的ですが、アンスリウム・クラリネルビウムは緑色の非常に控えめな花を咲かせます。注目してほしいのはハート型の葉。マットな質感の濃いグリーンに模様が映えます。強い日光は必要ありませんが、日の当たる窓辺や、レースのカーテン越し程度の明るい日陰に置くと葉がきれいに育ちます。
フィロデンドロン・セローム

セロームは直立性のフィロデンドロンで、切れ込みが入った大きい葉と突起の生えた幹が魅力。また、幹の途中から気根を出す場合があります。樹液にはシュウ酸カルシウムが含まれているため、口に入らないよう要注意。
置き場所は直射日光の入る窓辺など明るく風通しの良い場所が適しています。育てているうちに株がひょろっと間延びしてきたら日光が足りないか、水やりが多すぎるサイン。日当たりの良いところに移動させるか、水やりの頻度を見直すとよいでしょう。
トゲナシハナキリン

トゲナシハナキリンはユーフォルビア(トウダイグサ科)の低木で、名前の通りハナキリンによく似ていますが、分類的にはハナキリン(Euphorbia milii)と別種です。トゲナシハナキリンは艶のある丸い葉と赤い花が特徴で、ハナキリンと比べるとどこか和の雰囲気をまとっています。トゲが無いため管理しやすく、寒さや乾燥にも強いため温暖な地域であれば屋外で越冬させることができます。トゲナシハンキリンを増やす時は、適当な枝を切って水に小一時間さらして白い樹液を抜いてから挿し木にするとよいでしょう。
<いろんな場所に置きやすい>小さめの観葉植物
ソフォラ・ミクロフィラ

観葉植物の中でも繊細な枝振りをしており、小さな丸い葉を茂らせるソフォラ・ミクロフィラは可愛らしい見た目で人気が高いです。リトルベイビー(ソフォラ・プロテスタータ)に非常によく似ていますが、花の色と形状が異なります。人気が高い一方で枯らす人が非常に多く、育てるのが難しい観葉植物と言われています。原因としては蒸れによる根腐れが原因でないかと思われます。
水を好む一方で蒸れと乾燥に弱く、根腐れをするとすぐに葉を落として枯れてしまいます。コツとしては初夏~秋頃までは屋外の半日陰の場所で受け皿を使って腰水で管理すると真夏でも上手く育っています。育つと比較的大きくなる観葉植物です。
アジアンタム

観葉植物として根強い人気のあるアジアンタムは小さい葉が愛らしいですが、管理にコツが必要で夏場に水切れを起こしてしまい葉をカリカリにさせてしまうケースが多いです。そのため、受け皿などに水を張り、底からも水を吸い上げれるようにし、水切れと乾燥を防ぐようにしましょう。地上部の葉が枯れ込んでしまっても、切り戻して湿度を高めに維持すれば新葉が出てくる場合があります。
ベゴニア・キャサリンメイヤー

ベゴニアのキャサリンメイヤーは春〜秋ごろとクリスマスの時期に咲かせます。葉も小さく小型品種です。柊に似た葉をしていて寒さにも強いので、冬はミニクリスマスツリーとして飾ってみてもいいかも。
ベゴニア・ドレゲイ

ベゴニアの中でもまだ数が少ないのが球根性のドレゲイ。球根性ベゴニアと言っても、球根ではなく球根のように育っていくと基部(根元)が太っていき、水分を蓄えていくので、他のベゴニアより水やりは少なくても大丈夫です。コンパクトに育てることができ、葉は紅葉のようなフォルム。
ベゴニア・ベニゴ

ベゴニアが人気の理由の一つが葉の模様や葉の色合い。ベニゴはピンクのドット模様が特徴です。コンパクトなのでちょとしたスペースに飾って楽しめます。
コーヒーの木

観葉植物として出回っているコーヒーの木はその名の通り実がコーヒーの原料となる植物の総称で、農地で栽培されているコーヒーの木もほぼ同じものになります。ある程度の大きさと育成環境が揃えば白い花を咲かして、開花後にコーヒーチェリーと呼ばれる赤い実を実らせます。葉に光沢があり、いかにも観葉植物という見た目をしています。
フィットニア

観葉植物としてだけでなく寄せ植えの材料としても使用されるフィットニアは、葉模様からアミメグサという和名が付けられています。品種改良が盛んで数多くの園芸品種が生まれています。また、アクアリウム店などで水草として販売されていることもあるようですが、フィットニアは水中ではうまく呼吸が行えず、長期間の栽培は難しいです。湿度を好む観葉植物ですが強健なためある程度の乾燥ならば耐えることができます。ただし、葉が小さい分乾燥によるダメージが大きくなってしまうことがあるため、できるだけ小まめに水やりをするとよいでしょう。
ピレア

観葉植物の中でも非常に種類の多いピレアは世界の温帯~亜熱帯に分布しています。最もよく見かけるものはフィットニアに似たような葉模様をしているものや、ピレア・グラウカと呼ばれている種類ですが、他にピレア・ペペロミオイデスやピレア・グロボーサなど見た目が全く違うものもあります。そのため、各種に応じた育て方をする必要がありますが、フィットニア同様基本的には強健なので、水切れを起こさないように注意しながら水やりを行いましょう。
サンスベリア

肉厚の葉が上にすらりと伸びる独特なフォルムが人気の観葉植物、サンスベリア。日光を好む植物なので日当たりの良い明るい窓辺などに置くようにします。
丈夫な性質ではありますが、寒さには弱いです。冬は水やりのタイミングを変える必要があります。生長期の春~秋は土の表面が乾燥してから2~3日後にたっぷりと水やりしてください。気温が10℃前後を切る冬は土が完全に乾燥してから水やりをしましょう。
ホヤ・カルノーサ

原産地では樹木の幹や岩に張り付き育つホヤ。
厚い葉がほんのりピンク色に色づいたホヤ・カルノーサは、桜色の花を咲かせます。室内ではレースのカーテン越し程度の日光が当たる場所で管理しましょう。室外で育てる場合は半日陰で。
ペペロミア・アングラータ

ペペロミアは品種が多く個性的な葉の模様や色、草姿まで魅力たっぷりの観葉植物です。
ペペロミア・アングラータは、多肉質で縞模様が可愛らしい葉を持つ品種。葉や茎が多肉質で水分を貯めているので、水のやりすぎに注意します。土の表面が乾いてから数日後に水やりするのがベスト。
乾燥には強いのですが多湿を好むので葉にこまめに霧吹きで葉水をしましょう。管理場所で適しているのは明るい日陰。室内であれば窓際のレースカーテン越しで育てましょう。
フィカス・プミラ

枝から気根を伸ばし、這うように生長するフィカス・プミラ。アーチ状に這わせたり、寄せ植えのアクセントにも使われたりします。ぐんぐん伸びるのでハンギングにしても楽しめる観葉植物です。耐陰性があるため、日当たりの悪い日陰でも育てることができます。
ティランジア(エアープランツ)

ティランジア(エアープランツ)は土のいらない植物として知られています。中南米原産で樹皮や岩壁などに根を張って生えており、日本で育てるときもインテリアバークやコルクなどに着生させて育てます。ティランジア(エアープランツ)を育てるのに便利なスタンドもあるので、それを使ってもよいでしょう。
草丈数cmの極小サイズからメーター級の大型種まで多くの種類がありますが、ホームセンターや園芸店で販売されているティランジアは小型のものが多いです。
ワイヤープランツ

ワイヤープランツは小さなグリーンの葉が可愛らしい、匍匐性常緑小低木です。ワイヤープランツという名前の通り、細いワイヤー(針金)の様な茎が特徴的です、耐寒性が非常に強い植物です。
観葉植物:ハンギングに向いている種類
ビカクシダ

ビカクシダは東南アジア、オセアニア、アフリカ・マダガスカル、南アメリカに分布している中~大型のシダで、18種類の原種があります。いずれも樹木に根を張っている着生植物で、日本ではコルクやヘゴ板、焼き板などに着生させて観葉植物として親しまれています。胞子をつける胞子葉と泥除けや着生の役割を持つ貯水葉があり、種類によってそれぞれの見た目が変わってきます。
ネフロレピス・ツデー

葉が長く伸びるユニークでな観葉植物のネフロレピス・ツデー。シダの仲間なので、少し日当たりが悪くても生長してくれるので、部屋の状況によって選んでみてください。日光が強すぎると葉が焼けてしまいます。南向きの窓や日当たりの良い窓辺はレースカーテン越しにするなどが適しています。
ポトス

観葉植物の中で最も育てやすいポトスは、つる性の観葉植物です。初心者でも育てやすく、新しい魅力的な品種も開発されているのでベテランの園芸家も楽しめる植物です。つる性の観葉植物なのでハンギング仕立てにして育てることもできます。その場合、葉はあまり大きくならず小さいまま生長しますが、ヘゴ棒などを使用して上へ行くように育てるとモンステラのような大きさの葉をつけるようになります。ソロモン諸島が原産ですが、沖縄や東南アジアに帰化している例があります。
フレボディウム・アウレウム(ブルースター)

マットな質感の葉が珍しいフレボディウム・アウレウム。葉が青みがかていることもありブルースターという名の観葉植物でも流通しています。シダ植物ではありますが乾燥にも強く、生育旺盛な植物です。
ビロードカズラ

ビロードカズラはフィロデンドロンの一種で、コロンビア原産の観葉植物です。ビロードカズラはその名の通り葉がビロードのような美しい光沢感を持っており、キラキラとしている美しいフィロデンドロンです。ポトス同様に上へ行くように仕立てると葉が巨大化しますが、ハンギングなどで下垂させるように仕立てると葉が小さいまま生長していきます。
開いたばかりの葉は透明感のあるオレンジ色で、時間が経つにつれ深い緑色へと変わっていきます。
アイビー

観葉植物や寄せ植えにも利用されるアイビーは、建築物の外壁などに生えていることも多いつる性の観葉植物です。性質も強健で霜が降りなければ屋外越冬が可能でどんどん増えていきます。
また、直射日光にも日陰にも耐えることができるため非常に育てやすい観葉植物です。葉模様の違う数種類のアイビーをまとめてハンギングにしても素敵です。
ヒメモンステラ

独特な葉の形が特徴的で、モンステラよりも葉が小さいヒメモンステラ。高温多湿に強く、日陰にも耐えれる性質なので日光が入る室内で育てることができます。飾る時、エアコンなどの風が直接当たると葉が傷んでしまうので、直接当たらない場所に置いてください。
大きくなって形が崩れてきたら剪定して整えるとよいでしょう。ヒメモンステラの切った枝は水につけておくと水栽培することができます。
オリヅルラン

オリヅルランは強健で初心者にも育てやすい観葉植物です。葉に斑が入っているものが一般的で、ランナーという細い枝を伸ばしてその先に子株を付けます。春から夏にかけては小さな白い花を咲かせます。室内では常緑の植物ですが、屋外で管理している場合は冬に地上部の葉をすべて枯らして休眠することがあります。気温が高くなるにつれて徐々に休眠から目覚めていきます。
ネペンテス

ネペンテスは昆虫を捕食することに特化した食虫植物です。ウツボカズラとも呼ばれます。ネペンテスの特徴である、捕虫葉と呼ばれるツボ状の葉の中には液体が入っており、蜜などで誘い込んだ虫を捕虫葉の中に落とし込んで消化して養分にします。
東南アジアなど気温と湿度が高い環境が原産ということもあり、日本の冬の寒さには弱いです。越冬させる場合は暖かい場所で管理してください。
ティランジア・ウスネオイデス

変わった見た目をしているティランジア・ウスネオイデス。葉が細いものや太いものなど、タイプは様々。ウスネオイデスは非常に人気のあるティランジ(エアープランツ)ですが、残念ながら枯らしてしまう人が多い観葉植物のひとつでもあります。形状から内側から蒸れやすいため、たっぷりと水やりした後は風通しの良い場所に掛けてしっかりと乾かしましょう。
観葉植物の基本的な育て方
観葉植物を育てる時のポイントは「日当たり」と「水」「風」の3つです。どれも重要ではありますが、置き場所は観葉植物の状態にダイレクトに関わってきます。
「日当たり」と「風通し」

観葉植物の置き場所を決める時は日当たりと風通しの2つをポイントにして決めるようにしましょう。
耐陰性の高い観葉植物は、日陰など日当たりが多少悪くても育てることはできます。そう、あくまでも「育てることはできる」ということで必ずしも「健やかに育つ」わけではありません。

長い間、日陰や暗い場所で育てていると徒長(間延びして弱々しい株になること)することがあります。弱ると病害虫への抵抗力も下がったり、葉色も悪くなります。健やかに育てるためにも、できるだけ明るい場所で管理するようにします。
一番理想的なのは午前中いっぱい日光が入ってくる窓辺です。もし部屋に日光があまり入ってこないという場合は、週に数回外に出して日光に当てるでもOK。庭にもあまり日光が入らないという場合でも室内に置きっぱなしにするよりはよいでしょう。
風通しが悪い環境も蒸れや病害虫の発生の原因になります。空気が動かない淀んだ場所だと観葉植物自体の調子も崩れてきてしまい、それに起因して病害虫が発生する可能性があります。そのため、リビングや寝室などある程度の広さがあり、人が出入りする環境に置くとよいでしょう。こまめに換気をして、新鮮な風に当てたり、サーキュレーターを使ったりして空気を循環させてください。
水やり

観葉植物の種類によって変わってきますが、基本的には土の表面が乾燥したら鉢底穴から水が流れ出る位たっぷりと水やりをします。これは土の中に溜まっている古い水や汚れなどを押し出して、土の中をクリーンな状態に保つためです。また、気温が低くなると休眠する観葉植物も、室内など常に暖かい場所であれば冬でも休眠をしないで生長を続ける場合があるので、その時は生長期と同じように管理するようにしましょう。
乾燥予防に霧吹きをする「葉水」

土に水やりをするだけではなく、葉にも水やりをしましょう。乾燥しすぎるとハダニが発生する原因になります。ハダニが発生すると葉に斑点やまだら模様が現れ、表面がカサカサした感じになります。症状が進行すると枝の付け根部分などに白い糸をがつきます。ハダニの発生を防ぐためにもこまめに葉水をして湿度を保ってください。
▼ハダニについてもっと詳しく
観葉植物が枯れそうなときの対処法
観葉植物は調子が悪くなってくると葉や茎などにさまざまな症状を出す場合があります。そういった症状が出てきた場合はできるだけ早く対処するようにしましょう。
比較的新しい葉が黄色い

通常は緑色をしている観葉植物の葉が黄色くなってきたら肥料不足の可能性があります。健康的な株は古い葉の葉緑素などを分解してエネルギーとして吸収していますが、比較的新しい葉が黄色くなってきている場合は注意が必要です。対処法としては液体肥料を規定の1/2~1/3程度で希釈して水やりと一緒に与えてください。間隔としては1週間に1回程度です。
置き肥ではなく液体肥料を与える理由としては、液体肥料の方が即効性があり早く観葉植物に作用するためです。また、いきなり濃い濃度の肥料を与えてしまうと肥料焼けをしてしまうことがあるため、はじめは薄くし徐々に濃くしていくとよいでしょう。
葉が茶色くなっている

梅雨明けや真夏など暑い時期に起こりやすいのが葉焼けです。葉焼けは火傷のようなもので、日光が当たり過ぎて葉の表面が熱くなると起こります。葉焼けは一度なってしまうとその部分は再生することが無く、大部分が葉焼けをすると枯れる原因にもなるので注意しましょう。徐々に日光に慣らすか、寒冷紗や遮光ネット、レースカーテンなどをして直射日光を遮るようにするとよいでしょう。
水やりをしているのに葉が枯れていく

観葉植物に水やりをしっかりやっていても葉が萎れたり枯れてきたりする場合は、根詰まりや根腐れの可能性があります。根詰まりは根の勢いが良く、鉢の中でパンパンになってしまっている状態です。葉が枯れてくる観葉植物で画像の様に鉢底から根が出てきている場合は根詰まりをしている可能性が高いので植え替えをしましょう。
また、根腐れはその名の通り根が腐ってしまっている状態で、夏の暑さによる蒸れや水やりのしすぎなどが原因として挙げられます。根腐れをした観葉植物は、根腐れしている部分を取り除き、殺菌剤を散布して綺麗な土に植え替えます。
観葉植物の葉がベタベタしている

観葉植物の葉がベタベタしている時はカイガラムシが発生している場合が多いです。葉や幹にカイガラムシが付いていないか確認してみましょう。
ベタベタの成分はカイガラムシが出した排泄物で、放置しておくとスス病などの原因となります。

カイガラムシを取り除き、シャワーなどで洗い流しましょう。ジョウロなどの弱い水流ではなく、ちょっと強め位の水流で洗い流すときれいになります。
観葉植物を上手に育てるためのポイント

観葉植物を育て始めたばかりの人は、毎日観葉植物を観察してみましょう。
葉を手で触ってみたり、幹を指で優しく押して張り具合を確かめてもよいでしょう。とにかく毎日観察して、ちょっとした違いに気づけるようにしておくと観葉植物が病気になったときに早めに対処することができるようになります。
ただし、毎日見ていると目が慣れてしまい逆に気付きにくくなる場合があるので、週に1回などのペースで写真を撮って記録を残しておくと見返したときに変化が分かりやすいです。
観葉植物を育てることは最初のうちは難しいかもしれませんが、臨機応変な対応ができるとさらに植物をよく育てることができると思います。この辺はとにかく慣れという部分があるので、まずはその観葉植物について知ることと、観葉植物を育てることを楽しいと感じることが重要です。
あまり難しく考えず、気に入った観葉植物があればまずは育ててみましょう!
▼関連記事
関連ワード
今月のおすすめコンテンツ
「観葉植物とは?初心者向けの定番から個性派まで。人気の種類と基本の育て方」の記事をみんなにも教えてあげよう♪