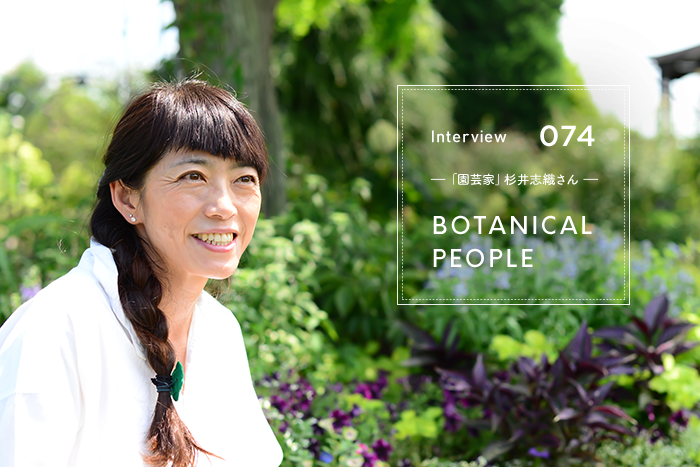初夏の寄せ植え|おすすめの花、作り方と管理のコツ
更新
公開

初夏(5月の初めから6月の初め頃)は、夏に向かって少しずつ気温が上昇していく季節。「初夏の寄せ植え」の作り方のコツやおすすめの草花、管理ポイントなどを紹介します。
目次
初夏の寄せ植えの作り方のコツ
5月になると植物たちは勢いよく生長し、花も次々に咲き誇ります。時に夏を感じるように暑い日もあったり、それでも朝夕は涼しくすごしやすい季節です。園芸店の花苗コーナーは、一年中で一番苗の種類が豊富で華やかなとき。花苗を選ぶのも楽しいですね。
初夏の寄せ植えに使う苗選び
テーマを決める
「紫陽花(アジサイ)など、初夏ならではの植物をメインにする」「収穫して楽しむハーブを寄せ植えする」「初夏から秋まで長い期間花が咲く植物を組み合わせる」など、テーマを決めると選びやすいです。
▼河野自然園の井上まゆ美さんに教わった山紫陽花(ヤマアジサイ)を使った寄せ植えはこちら
▼ハーブを使った寄せ植えはこちら
▼初夏から秋まで長い期間楽しめる寄せ植えはこちら
植物が好む環境をそろえる
苗を組み合わせるときは、植物が好む環境(日なたや日陰、水の具合など)をそろえることが大切です。
乾燥気味の環境を好む植物と、少し湿った状態を好む植物を一緒に植えると、どちらかが好ましくない状態になってしまいます。日なたを好む植物を日陰で育てると花が咲かなくなり、日陰を好む植物を日なたで育てると葉焼けをおこして葉色が悪くなったりしてしまうので注意が必要です。
初夏は雨上がりなどに蒸しやすい季節でもあるので、「色とりどりのカラーリーフだけで作る寄せ植え」も育てやすく涼し気でおすすめです。
▼カラーリーフで作る爽やかな育てるリースはこちら
▼涼し気なシェードガーデンをイメージした寄せ植えはこちら
初夏の寄せ植えにおすすめの草花
初夏の寄せ植えに使いたい代表的な草花を紹介します。
ペチュニア

ペチュニアは、ナス科の非耐寒性一年草(多年草)。春から秋まで長い期間咲き続けます。
▼ペチュニアの詳しい育て方
サフィニア

サフィニアは、ナス科の非耐寒性一年草(多年草)。サフィニアはペチュニアの改良品種。ペチュニアの長期間咲き続ける良さを引き継ぎ、雨に弱い弱点を改良してより育てやすくなっています。
▼サフィニアの詳しい育て方
カリブラコア

カリブラコアは、ナス科の非耐寒性一年草(多年草)。ペチュニアの近縁種。ペチュニアより花が小さ目で繊細です。花期は5月~10月頃。ペチュニアと同じく長雨に当たると花が傷みやすいので、雨が続く時は屋根のある場所に移動すると美しく保てます。
▼カリブラコアの詳しい育て方
ラベンダー

ラベンダーは、シソ科の耐寒性(半耐寒性)常緑低木。ラベンダーは非常に種類が多く、香りが強いもの、丈夫で花壇の観賞に向くものなど様々です。耐寒性や耐暑性もそれぞれ異なります。
▼ラベンダーの詳しい育て方
フランネルフラワー

フランネルフラワーは、セリ科の非耐寒性多年草。春~初夏、秋に開花します。花や葉が柔らかい毛織物のようにふわふわしていて、暑さ寒さに弱く、高温多湿の環境が苦手です。春から初夏(梅雨前)がより美しく咲くように思います。
▼フランネルフラワーの詳しい育て方
山紫陽花(ヤマアジサイ)

山紫陽花は、アジサイ科の耐寒性落葉低木。花期は5月~7月頃。日本の各地で古くから自生している野生種の紫陽花で、小さめの花房と小ぶりな葉が繊細な印象です。
▼山紫陽花(ヤマアジサイ)の詳し育て方
八重咲きインパチェンス

八重咲きインパチェンスは、ツリフネソウ科の非耐寒性多年草。花期は5月~10月頃です。半日陰で美しく花が咲くのでシェードガーデンにぴったりです。
▼八重咲きインパチェンスの詳しい育て方
バラ咲きベゴニア

バラ咲きベゴニアは、シュウカイドウ科の非耐寒性多年草。春から秋まで可愛い花がどんどん咲きます。真夏の直射日光と過度な多湿は苦手で、風通しの良い半日陰を好みます。
▼バラ咲きベゴニアの詳しい育て方
ユーフォルビア・ダイアモンドフロスト

ユーフォルビア・ダイアモンドフロストは、トウダイグサ科の非耐寒性低木。4月~11月頃に白い繊細な小花を咲かせます。花に見える部分は苞(ほう)と呼ばれる花のすぐ下の葉で、本当の花は苞の中心部にもっと小さく咲いています。
▼ユーフォルビア・ダイアモンドフロストの詳しい育て方
シュガーバイン

シュガーバインは、ブドウ科の半耐寒性多年草。みずみずしい茎をつる状に伸ばし、可愛い葉をつけます。室内の明るい場所で育てることもできますが、暖かい季節は屋外の半日陰で寄せ植えに使うこともできます。
▼シュガーバインの詳しい育て方
▼「5月~6月の寄せ植えにおすすめの草花」もっと詳しくはこちら
初夏の寄せ植えのデザイン例
アンティーク風の鳥かごを使った寄せ植え
おしゃれなアンティーク風の鳥かごは、一つあるとその場の雰囲気が素敵な空間に変わります。
▼鳥かごを使った寄せ植えの作り方はこちら
ラベンダーを使った寄せ植え
ラベンダーは主に初夏を中心に咲きます。初夏ならではの植物を使って季節感を味わうのもおすすめです。
▼ラベンダーを使った寄せ植えの作り方はこちら
ペチュニアを使った寄せ植え
ペチュニアは、春から秋まで長い期間花を咲かせます。花色が豊富で華やかなものから、大人っぽいアンティーク風のものまであるので、お気に入りのペチュニアがきっとみつかります。
▼大人色のペチュニアを使った寄せ植えはこちら
サフィニアを使った寄せ植え
サフィニアは、ペチュニアの改良品種。雨に弱い弱点が改良されているので育てやすくおすすめです。
▼4色のサフィニアを使った寄せ植えはこちら
ナスタチウムを使った寄せ植え
ナスタチウムは春から秋に花を咲かせますが、厳しい夏や夏を乗り越えた秋よりも、春~初夏の花がより美しいです。
▼渋谷園芸の樺澤智江さんに教わった、ナスタチウムを使った寄せ植えはこちら
初夏の寄せ植えの管理ポイント

置く場所
寄せ植えは、屋外の風通しの良い日なた~半日陰に置きます。暑さが厳しくなってきたら、ギラギラと直射日光が当たる場所よりも半日陰や明るい日陰の方が状態良く育ちます。雨に弱い草花は、長雨に当たらない軒下やベランダなど、屋根のある場所が好ましいです。
水やり・肥料
株元の土の乾き具合を確認して水切れしないように水やりします。雨に当たった日は、水やりはお休みしましょう。真夏の水やりは、高温多湿を避けるため、早朝や夕方以降の涼しい時間帯に行います。
ペチュニアやサフィニア、インパチェンスやベゴニアなど、花期が長いものは肥料が必要です。植え付けるときに肥料入りの培養土を使った場合は、1カ月後から液肥や固形肥料を与えましょう。
花がら取り
咲き終わった花(花がら)や古い葉は、見た目も悪く病害虫の発生の原因となるので早めに取り除きます。花がらを取ることで、次の花が咲きやすくなります。
花後の管理
初夏に作る寄せ植えは、夏を上手に越すことができたら秋まで楽しめます。茂りすぎたら全体のバランスを見て切り戻すときれいな寄せ植えがキープできます。
秋が深まって寒くなってくると、寒さに弱い多年草は屋外では冬越しできません。一年草扱いとする場合は、寒さに強い植物に植え替えます。寒さに弱い多年草を翌年も咲かせるのであれば、春まで室内の明るい窓辺に取り込んで管理しましょう。
初夏(5月の初めから6月の初め頃)は、梅雨に近づくとジメジメし始めますが、5月の初め頃は晴れるとカラっとして人も植物も過ごしやすい季節です。植物は勢いよく生長し、花も次々に咲き誇ります。苗売り場には春の植物に加え、ペチュニアなどの初夏から秋まで楽しめる花が並んでカラフルににぎわいます。お気に入りの草花を見つけて、ぜひテーマを決めて寄せ植えを作って楽しんでみてくださいね。
▼編集部のおすすめ