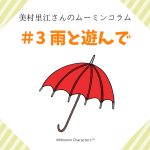縁起のいい植物42種。理由や風習、海外の言い伝えも
更新
公開

縁起のいい植物を42種類紹介します。それぞれの伝承や由来を交えているので理由もわかります。贈り物やガーデニング、インテリアの参考にしてください。
目次
- 縁起のいい植物とは?日本の風習
- 縁起のいい植物|お庭におすすめ14種
- 縁起のいい植物|玄関におすすめ5種
- 縁起のいい植物|観葉植物おすすめ5種
- 縁起のいい植物|花おすすめ9種
- 縁起のいい植物|海外おすすめ9種
縁起のいい植物とは?日本の風習

縁起のいい植物とは、昔から魔除けや幸せを呼ぶ、金運が上がる、邪気を払うなどと信じられ、愛されてきた植物のこと。縁起がいいと言われる理由は神話、伝承、花言葉など様々です。
私たち日本人の生活の中で、植物は古来より身近な存在でした。お正月に縁起木として松などの常緑樹を飾ったり、端午の節句にはショウブ湯に入り、重陽の節句には菊を愛でる風習があります。また、引っ越し祝いには幸福を祈願して植物を贈り合うような習慣もあります。縁起のいい植物は今でも私たちの生活の中に息づいています。
縁起のいい植物|お庭におすすめ14種
ヨモギ

ヨモギは日本古来の薬草。全草に芳香があります。ヨモギの香りには邪気を払ったり、魔除けの効果があるとして、古来より好まれてきました。今でも端午の節句には菖蒲湯にヨモギを入れたり、ヨモギ餅を食べる習慣が残っています。
ショウブ

![]()
ショウブはショウブ科の多年草。花が咲くショウブとは別物です。ショウブは葉にも根にも芳香があることから邪気を払う力があると信じられ、端午の節句にショウブ湯に入る習慣ができました。
ムベ

ムベはアケビ科の常緑のつる植物。秋に果実を実らせます。ムベの葉は幼木のころは3枚、生長するにしたがって5枚、7枚と増えていくので、七五三の縁起木と言われています。
カラスウリ

カラスウリはウリ科のつる植物。秋にオレンジ色に熟す果実は、割ると中に数粒のタネが入っています。カラスウリのタネはそのフォルムが大黒様のお腹を連想させるとか、打ち出の小づちに似ているという理由から、お財布に入れておくと金運が上がると言われています。また、ラスウリの種を麻袋に入れて誰にも知られないように床下に隠しておくと、お金持ちになれるという言い伝えもあります。
南天(ナンテン)

南天はメギ科の常緑低木。秋から冬に真赤な果実を実らせます。南天はその名前から「難を転ずる」とされ、昔から縁起のいい木として好まれ、お正月飾りなどに使用されます。
万両(マンリョウ)

万両はサクラソウ科の常緑低木。晩秋から冬に真赤な果実を実らせます。万両という名前がお金を連想させるということから、富を招き寄せる、金運が上がるなどと言われ、縁起のいい木として好まれてきました。
千両(センリョウ)

千両はセンリョウ科の常緑低木。晩秋から冬に赤や黄、オレンジ色の果実を実らせます。千両は万両と同じく名前がお金を連想させるということから、富を招き寄せる、金運が上がるなどと言われ、縁起のいい木として好まれてきました。
クロガネモチ

クロガネモチは秋から冬の間、真赤な実を付ける常緑高木。名前が「苦労のない金持ち」を連想させるとして、縁起のいい庭木として人気があります。
松

松はマツ科の常緑高木。冬でも緑を絶やさない常緑樹であることから、長寿を象徴する木とされてきました。また、神様が宿っていると信じられ、古来より神聖視されてきた樹木です。お正月には玄関に松を飾る習慣があります。
竹

![]()
竹はイネ科の多年草。真直ぐ上に伸び、さらに生長が早いことから、真っすぐな心と生命力の象徴と考えられてきました。今でもお正月の飾りつけや祭事に使用されます。
ユズリハ

ユズリハは新しい葉が出てくる前に、場所を譲るように古い葉が落ちていくことから、子孫繁栄、代々家が続く、などの意味があるとされています。
裏白(ウラジロ)

ウラジロはシダ植物の仲間です。葉の表はグリーンで葉裏が白いことから、「後ろ暗い事がない」という意味を持ち縁起がいいと言われています。また、邪気を払うなどの意味もあると信じられてきました。鏡餅の飾る際に利用されます。
梅

梅はバラ科の落葉高木。まだ寒い早春から香りの良い花を咲かせるので、希望を連想させることから縁起のいい木として好まれてきました。他にも紅白の花を咲かせることから縁起がいいとされています。お正月の花に好まれます。
桃

![]()
桃はバラ科の落葉高木。桃は昔の中国では霊力のある木とされていました。日本でも桃の果実がお尻を連想させるということから、安産、多産の象徴としてひな祭りに飾られたという説もあります。また、黄泉の国でイザナギノミコトを救った木だとも言われています。
縁起のいい植物|玄関におすすめ5種
オモト(万年青)

オモトはユリ科の多年草。万年青という和名の通り、一年中グリーンの葉を絶やさないことから、縁起のいい植物とされてきました。さらに冬に真赤に色付く実は、子孫繁栄、富の象徴とも言われています。引っ越し祝いや玄関に飾る植物として好まれます。
サンスベリア

サンスベリアはキジカクシ科の観葉植物。空気清浄能力が高く、さらには金運をアップさせる開運植物として売られることもあります。引っ越し祝いや玄関に飾る植物として好まれます。
ローズマリー

ローズマリーはシソ科の常緑低木。全草に爽やかな芳香があります。この香りには魔除けや浄化作用があると信じられ、ヨーロッパでは浄化のハーブとして好まれてきました。屋外で育てる植物なので、玄関周辺に植えると香りが良く、見た目にも美しいハーブです。
アジサイ

アジサイはアジサイ科の落葉低木。「一家団欒」という花言葉を持っています。また、アジサイを玄関に植えておくとお金が貯まるという言い伝えがあります。
オリーブ

オリーブはモクセイ科の常緑高木。地中海地方原産の植物で乾燥と風に強く、シンボルツリーとしても人気です。旧約聖書に出てくるノアの箱舟伝説で、洪水が引いた後に鳩がオリーブの枝を咥えて来たことから、平和を象徴する木とされています。
縁起のいい植物|観葉植物おすすめ5種
パキラ

パキラはアオイ科の観葉植物。手のひらのようなフォルムの大きな葉が印象的です。「快活」「勝利」という花言葉から幸運を象徴する木とされ、開店祝いや引っ越し祝いに好まれます。
ガジュマル

ガジュマルはクワ科の常緑高木。沖縄ではキジムナーという精霊が住む霊木とされています。また、「多幸の木」とも言われ、幸福を象徴する木として贈り物やインテリアとして好まれます。
ユッカ

![]()
ユッカはリュウゼツラン科の観葉植物。別名を「青年の木」と言い、その生長の早さから縁起のいい観葉植物として人気があります。
幸福の木(ドラセナ・マッサンゲアナ)

![]()
幸福の木はキジカクシ科の観葉植物。ユッカと同じく生長が早いことから縁起のいい観葉植物として人気があります。また、その名前から贈り物にも好まれます。
金のなる木

金のなる木はベンケイソウ科の観葉植物。新芽が開く前に五円玉を通していくと木にお金がなっているように見えることから「金のなる木」と呼ばれるようになりました。金運が上がる植物として人気があります。
ベビーティアーズ

ベビーティアーズはイラクサ科の多年草。地中海地方原産の小さな葉がかわいらしい植物です。花期には葉よりもさらに小さな白い花を咲かせます。この花を見つけられたら幸せになれるという言い伝えを持つ植物です。
縁起のいい植物|花おすすめ9種
福寿草

福寿草はキンポウゲ科の多年草。早春に明るい黄色の花を咲かせます。福寿草という名前は縁起がいいとされ、お正月の花や贈り物に好まれます。
アイリス

アイリスはアヤメ科の多年草。花言葉は「恋のメッセージ」「吉報」。アイリスはギリシャ神話に登場するヘラの侍女。古代ギリシャではアイリスが女性の霊魂を虹の橋を渡って天国へ連れて行くとされ、女性が亡くなるとアイリスを捧げたとか。古代エジプトではアイリスの3枚の花びらを「信仰」「知恵」「勇気」の象徴としていました。
藤(フジ)

藤はマメ科のつる性落葉高木。昔から日本人に好まれてきた花です。薄紫色の優美な藤の花は女性の美しさに例えられ、身分の高い女性を象徴する花でした。また、藤色は高貴な身分の人しか身に着けられない色だったこともあるほどです。
スズラン

スズランはキジカクシ科の多年草。春に香りの良い白い花を咲かせます。「幸せが再び訪れる」という花言葉が有名で、贈り物に好まれます。フランスでは5月1日を「スズランの日」といい、この日にスズランを贈ると、贈った人も贈られた人も幸せになれるという習慣があります。
ボタン

ボタンはボタン科の落葉低木。昔の中国ではその優美な花姿から「花の神にして百花の王」と言われ、高貴な花として城中で育てられていたそうです。邪気を払う、縁起のいい花とされています。
蓮(ハス)

蓮はハス科の水生植物。泥の中から上がってきた茎の先に大輪の美しい花を咲かせることから、「不浄の花」「清らかさの象徴」と言われ、仏教では神聖視されてきました。仏像を安置する蓮華座も蓮の花です。
フジバカマ

フジバカマはキク科の多年草。フジバカマは葉に桜餅を思わせるような芳香があるのが特徴です。この香りには邪気を払う力があると信じられ、貴族が乾燥させた葉を着物に忍ばせたり、蘭のように高貴な花とされていたと言います。
蘭(ラン)

蘭はラン科の多年草。昔から高嶺の花として、手の届きにくい高級品でした。お正月に蘭を飾るのは、お正月には高級な花を飾って繁栄を祈願することに由来しているようです。特に胡蝶蘭は「幸福が飛んでくる」という花言葉から贈り物に好まれます。
菊(キク)

菊はキク科の植物。お正月の花、仏事、祭事に欠かせない花です。その昔、中国では菊を不老長寿の薬草としていました。それが日本に渡ってきて、長寿や若返り効果を祈願する縁起のいい花と言われるようになったと言います。今でも重陽の節句に菊を飾ったり、菊酒を飲んで楽しんだりします。
縁起のいい植物|海外おすすめ9種
アマランサス

アマランサスはヒユ科の一年草。ヨーロッパにはアマランサスの花で作ったリースを身につけると姿が見えなくなるという伝承があるそうです。また、昔のギリシャでは不老不死の象徴とされ、お墓にアマランサスの花をまく習慣があったとも言われています。
ヤドリギ

ヤドリギはヤドリギ科の常緑半寄生植物。冬、落葉樹たちが葉を落とし、あたりが真白な雪景色になった頃、ヤドリギのグリーンは輝きます。冬の間も緑を絶やさないヤドリギは、生命力と永遠の命を象徴する植物でした。今でもクリスマスにヤドリギの枝を飾る習慣があります。
セイヨウニワトコ(エルダーフラワー)

セイヨウニワトコはスイカズラ科の落葉高木。昔からヨーロッパでは万病に効くとされ、珍重されてきました。生長が早いことから、「精霊が住む木」と考えられ、不死の象徴ともされてきたそうです。エルダーフラワーの花を煎じてお茶にしたり、秋に熟す実でシロップを作ったりと、今でも利用されています。
アーモンド

アーモンドはバラ科の落葉高木。桜が咲く頃に枝いっぱいにピンク色の花を咲かせます。その昔ヨーロッパでは聖なる木とされ、宝物を探すときなどはアーモンドの枝で占ったと言います。また、「不滅の愛」や「幸せな結婚」を象徴する木ともされてきました。
マートル(ギンバイカ)

マートルはフトモモ科の常緑低木。古来より神聖視されてきた木で女神アフロディーテの神木とされ、花嫁たちはマートルの葉で衣装を飾り付けたそうです。また、「権威」と「名誉」の象徴とされ、昔のアテネの裁判官はマートルを身に着けたと言われています。
月桂樹

月桂樹はクスノキ科の常緑高木。月桂樹は花や葉に芳香を持つことから、ヨーロッパでは魔除けや浄化の力を持つ木とされ、昔から神聖視されてきました。またアポロンが好んだことから葉で編んだ月桂冠は勝者に贈られる象徴ともなりました。
セイヨウボダイジュ(リンデン)

セイヨウボダイジュは昔からヨーロッパで霊力を持つ神聖な木と信じられてきました。裁判や誓いを立てる儀式、結婚式などがこの木の下で行われたと言われています。
ブドウ

ブドウはブドウ科の落葉つる性木本。歴史の古い果実で多くの伝承があります。昔から、豊穣、祝祭の象徴として扱われてきました。また、モーゼの約束の地を象徴する植物ともされています。
柳
柳はヤナギ科の落葉樹。春に一斉に芽吹く様子が生命力の強さを感じさせるとして中国では邪気を払う霊木として神聖視されてきました。柳の枝を玄関に飾ったり、旅立つ人に持たせたそうです。
好みの縁起のいい植物は見つかりましたか。植物にまつわる伝承とともにご紹介しました。何かの参考になれば幸いです。
▼編集部のおすすめ