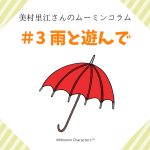10月が旬の野菜、果物、魚、花44種。秋の恵みを五感で味わう
更新
公開

10月に旬を迎える野菜、魚、果物、花を44種。ほかにも旬の食材を使ったレシピや季語、行事など、どんな時期かについても紹介します。
目次
10月とは?二十四節気や季語、行事、事柄

- 和名:神無月(かんなづき)
- 英名:October
10月とは
10月は本格的な秋が始まるころ。朝夕の風は冷え込み、日中との気温差から羽織るものが必要になってきます。夏草は急に勢いを失い、風の中に秋の香りを感じるようになります。湿気が少なく、からりとした晴天が多い月でもあります。
10月に使われる季語
秋高し(あきたかし)
秋になり空気が澄んで、空が高く感じられるようになることを指す季語です。
稲雀(いなすずめ)
稲が実ったころ雀が群れをなして稲をついばみにやってくることを指します。
薄紅葉(うすもみじ)
真赤に紅葉する前の、薄っすらと赤や黄色に葉の色が変わり始めた、紅葉の始まりのころを表現する言葉です。
10月に迎える二十四節気
寒露(かんろ)
寒露は二十四節気の第17節目、毎年10月8日ごろです。年によって1日程度前後します。また、10月8日から次の二十四節気の次の第18節、霜降までの15日間ぐらいを指します。寒露は朝晩の空気が冷え込むようになり、草花に冷たい露がつくころです。
霜降(そうこう)
霜降は二十四節気の第18節目、毎年10月23日ごろです。年によって1日程度前後します。また、10月23日から次の二十四節気の次の第19節、立冬までの15日間ぐらいを指します。霜降は夜はずいぶんと冷え込むようになり、霜が降りるころです。
10月の行事や事柄
衣替え
秋の衣替えは10月1日。必ずこの日とは決められているわけではありませんが、夏服から冬服へと制服や衣類を整理する目安とされている日です。
スポーツの日
国が定めた国民の祝日の一つ。毎年10月の第2月曜と決まっています。
「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」日とされています。
十三夜
十三夜は旧暦の9月13日ごろ。新月から数えて13日目の月を眺め、その年の収穫に感謝する日です。特に祝日ではありません。
9月のお月見が十五夜(満月)を愛でるのに対して、10月は十三夜なので満月になる少し前の月を眺めます。
ハロウィン
ハロウィンは毎年10月31日。特に祝日ではありません。元はケルト民族の収穫祭だったものがキリスト教と結びついて現在の形になりました。この日は悪霊にいたずらをされないように仮装をしたり、秋の収穫を祝ってご馳走を食べたりします。
10月が旬の野菜12種
新米

何と言っても秋は新米の季節。取れたてのお米は水分が多くおいしいとされています。
新そば
その年収穫した実で作ったそばを新そばと言います。新そばは10月下旬ごろから11月にかけて出回ります。食べ逃したくない秋の味覚です。
マツタケ(松茸)
マツタケは香りが良いことで有名なキノコ。日本でもっとも高級なキノコの一つです。炊き込みご飯や土瓶蒸し、お吸い物などにして楽しみます。
シメジ

一年中流通しているシメジですが、天然のブナシメジやホンシメジの旬は秋です。香りが良いので、炊き込ごはんやお吸い物、あえ物などにして楽しみます。
マイタケ(舞茸)

マイタケも一年中流通していますが、天然のものは秋が旬です。煮ても炒めても楽しめます。鍋料理にも活躍します。
食用菊
食用菊は名前の通り、食用の菊の花です。指でつまむようにして花びらだけを取り、酢を入れたお湯で茹で、お浸しにして食べます。花色は黄色や薄紫色があります。
チンゲンサイ

チンゲンサイは夏から冬にかけて収穫できる青菜。葉野菜が少なくなってくる秋から冬にかけて活躍します。
ナス

ナスはナス科の野菜です。一年中出回っていますが旬は夏から秋です。油と相性が良く、揚げたり炒めたりする調理方法が人気です。
サトイモ(里芋)

サトイモは肥大した地下茎を食用にする野菜。ぬめりと歯ごたえが魅力です。煮物のほか、茹でておつまみにしたり、揚げたり炒めたりして楽しみます。
レンコン(蓮根)

レンコンは食用のハス(蓮)の肥大した地下茎です。加熱時間や調理方法でシャキシャキとした歯ごたえとほくほくとした食感の両方を楽しめるのも魅力です。煮たり炒めたりして楽しめます。
カボチャ

カボチャの収穫期は晩夏ですが、長く保存ができるので野菜の少なくなる秋から冬に多く流通するようになりました。特に10月はハロウィンにちなんでカボチャ料理が盛んに作られます。
ムカゴ

ムカゴはヤマイモの仲間のつるに実ります。秋になるとつるの途中にムカゴが実っているのを見かけます。ごはんと一緒に炊くほか、揚げたり炒めたりして楽しめます。
10月が旬の果物(フルーツ)7種
ブドウ

ブドウはつる性の果樹。旬は品種によって違いはありますが、晩夏から秋です。甘く水分の多い果実が魅力の果物です。
イチジク(無花果)

イチジクはゴム科の落葉低木。晩夏から秋にかけて旬を迎える果物です。花を咲かせずに結実するのが特徴です。甘くねっとりとした果肉が特徴です。
ザクロ(柘榴、石榴)

ザクロはミソハギ科の落葉高木。秋に実る果実を食用にします。ザクロの果実は熟すと果皮が割れて、半透明で赤紫色をした宝石のような果肉が見える、とても美しい果物です。
アケビ
アケビはアケビ科のつる植物の果実。硬い果皮の内側に白いゼリー状の果肉が入っています。この甘い果肉を楽しみ、中の小さなタネは吐き出します。
キウイ

キウイはマタタビ科のつる植物。一年中流通していますが、日本では秋に収穫できます。果実は甘く瑞々しいのが特徴です。
栗(クリ)

栗は秋の味覚の代表のような果物です。加熱すると甘くほくほくとした食感を楽しめます。栗ご飯のほか、焼き栗や甘露煮など、楽しみ方がいっぱいです。
柿

秋にオレンジ色に色づく柿は日本の秋を象徴するような果物です。瑞々しく、独特の歯ごたえが魅力です。
10月が旬の魚(魚介)7種
サンマ
日本の秋を代表するようなサンマの旬は9月~10月です。塩焼きのほか、煮たり揚げたりして楽しめます。
タチウオ(太刀魚)
長く平たい姿が特徴のタチウオ。夏から秋にかけての産卵期が脂が乗っておいしい時期だと言われています。淡白な味わいの魚で、シンプルに塩焼きのほか、煮たり揚げたりして楽しめます。
秋鮭(アキザケ、アキジャケ)

秋に産卵のために川に戻ってきたサケを秋鮭と言います。産卵前なので身がしまっているのが特徴。塩焼きのほか、煮たり焼いたりして楽しめます。
サバ
サバは秋から冬が旬の魚。秋のサバは脂がのっておいしいと言われています。焼き魚、煮魚、フライなどさまざまな調理法で楽しめます。
ニシン
秋のニシンは身がしまり脂がのっていておいしいと言われています。塩焼きのほか、ニシン鍋などにして楽しめます。
カレイ
秋のカレイは冬の産卵を控えているので、身がしまっていておいしいと言われています。カレイは煮魚のほか、揚げてもおいしくいただけます。
スルメイカ
一年中流通しているスルメイカですが、夏から秋にかけてが旬。夏イカ、秋イカという呼び名もあるくらいです。特に秋イカは夏の間に成長しているので、脂が乗って肝までおいしいと言われています。
10月が旬の花や木18種
キク(菊)

菊の花の咲く季節は秋、9月~11月です。特に秋も深まり周囲の木々が紅葉し始めたころ、菊も美しく咲き誇ります。
オミナエシ

オミナエシ(女郎花)は黄色い小花を集合させたような花を咲かせるスイカズラ科の多年草。秋の七草の一つです。独特の香りが苦手と言う人も多いようですが、群生する姿が美しい花です。
リンドウ

リンドウは秋に青紫色の花を咲かせる多年草。花色はほかに、ピンクや白などがあります。9月ごろから咲き始め、秋も深まる11月ごろまで花を楽しめます。
コスモス

コスモスは色のバリエーションが豊富なキク科の一年草。秋を代表するような花ですが、最近は夏から開花する品種も流通しています。
アメジストセージ

アメジストセージはシソ科の多年草。ベルベットのような質感の紫色の花が美しいセージの仲間です。
スカビオサ(マツムシソウ)

スカビオサ(マツムシソウ)は和名をマツムシソウと呼ばれる、淡い紫色がきれいな多年草。春と秋に開花します。
ツリフネソウ

ツリフネソウは夏から秋に咲く、ツリフネソウ科の一年草。ふっくらとした花のフォルムとピンク色が鮮やかな花です。
シュウメイギク

シュウメイギクは秋に白やピンクの花を咲かせる、キンポウゲ科の多年草。菊の仲間ではありません。風に揺れる楚々とした姿が美しい花です。
トリカブト

トリカブトはキンポウゲ科の多年草。有毒植物として有名です。花色は紫のほかに白などがあります。独特のフォルムの花が美しく、切り花としても人気があります。
ススキ

ススキはイネ科の多年草。秋の七草にも数えられています。風に揺れ、金色に輝く花穂が美しい、風情ある草花です。
パンパスグラス

パンパスグラスは、イネ科の多年草。夏の終わりから秋に、真直ぐに伸びた茎の先に魔女の箒のような穂を咲かせます。草丈3mくらいまで生長する品種から1m程度の矮性種もあります。
クランベリー

クランベリーはツツジ科の低木。果実は酸味が強く生食できないので、主に観賞用として育てられます。9月~10月にかけて赤く色づく果実がかわいらしい花木です。
金木犀(キンモクセイ)

金木犀(キンモクセイ)は香りが良いことで人気のあるモクセイ科の花木です。秋に一斉に開花し、甘い香りを周囲に漂わせたかと思うと、数日で散ってしまう儚い花です。
カンボク

カンボクはガマズミの仲間の落葉低木。春に白い花を咲かせ、秋に真赤な果実を実らせます。宝石のような赤い果実は見るからにおいしそうですが、食用にはできません。
ナツハゼ

ナツハゼはツツジ科の落葉低木。秋に紅葉する葉と黒く色づく果実が美しい花木です。紅葉したナツハゼの葉はブルーベリーの葉を思わせます。黒く熟した果実は酸味が強く、食用にはなりません。
ガマズミ

ガマズミはレンプクソウ科の落葉低木。秋に宝石のような真赤な果実を実らせます。ガマズミの果実は酸味が強く生食できません。果実酒などにして楽しみます。秋の太陽を浴びて光るガマズミの果実は見とれるほどの美しさです。
ヤマボウシ

ヤマボウシはミズキ科の落葉あるいは常緑高木。春に白い花を咲かせ、秋にオレンジ色に近い赤い果実を実らせます。
ムラサキシキブ

ムラサキシキブはシソ科の落葉低木。春にピンク色の小さな花を咲かせ、秋に紫色の小さな果実を実らせます。紫色の果実は珍しいことと、日光を浴びて照り輝く様子が美しいので人気の花木です。果実は鳥が好んで食べますが、人間は食用にはしません。
10月が旬の食材レシピ2種
手羽中と栗の煮物
材料
- 手羽中 10本くらい
- むき栗 5~6個
- 鷹の爪 1本
- 酒 大さじ2
- しょうゆ 大さじ2
- みりん
- 水 大さじ3
作り方
- 鍋で手羽中を弱火から中火で焼く
- 両面に焼き色が付いたら手羽中を取り出し、余計な油を拭き取る
- 鍋にすべての材料を入れて15分から20分程度中火で煮込む
- 煮汁がとろりと煮詰まったら出来上がり
酒、しょうゆ、みりんは1:1:1を基本として、好みで調整してください。ニンニクを加えてもおいしく仕上がります。
きのこごはん
材料
- 米 2カップ
- 好きなきのこ 150~200gくらい(ざっくり1パック程度で問題なし)
- かつお節 適宜
- しょうゆ 大さじ1
- 塩 一つまみ
- 酒 大さじ1
作り方
- 米は洗って十分に吸水させておく
- きのこは洗って石づきを取り、食べやすいサイズに切る
- 炊飯器にすべての材料を入れて、水を目盛りまで入れたら全体をざっくり混ぜる
- 炊飯器のスイッチを入れる
- 炊き上がったら全体をざっくり混ぜて出来上がり
かつお節をそのまま入れて炊くことで、出汁を取る手間を省きました。きのことかつお節から出汁が出るのでしっかりとした味の炊き込みご飯が出来上がります。ごはんにかつお節が混じるのが気になる方は、だしパックなどの小袋にかつお節を入れておくとよいでしょう。
10月は空気がひんやりし始め、体で秋を感じるころです。金木犀の花が香り、紅葉が始まり、木々の果実も色づき、視覚や嗅覚でも季節を楽しむことができます。冬の到来前の恵みの季節を五感を使って満喫してください。
▼編集部のおすすめ