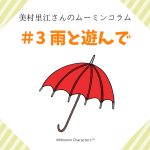春に咲く紫の花16選!ガーデニング、ブーケ、アレンジメントに
更新
公開

春は花が咲き乱れる季節。庭木から道端の雑草まで、色とりどりの花を咲かせます。その中でも紫色の春の花を集めてみました。
紫色の花、薄紫色の花、青紫色の花、一口に紫色の花と言ってもいろんな種類があります。お庭に植えたり、ブーケやアレンジメントにして楽しめる、紫色の春の花たちをご紹介します。
目次
- 春の紫色の花|スミレ
- 春の紫色の花|パンジー、ビオラ
- 春の紫色の花|スイートピー(宿根スイートピー)
- 春の紫色の花|アネモネ
- 春の紫色の花|ルピナス
- 春の紫色の花|ムスカリ
- 春の紫色の花|ヒヤシンス
- 春の紫色の花|チューリップ
- 春の紫色の花|スカビオサ
- 春の紫色の花|クレマチス
- 春の紫色の花|ラベンダー
- 春の紫色の花|イカリソウ
- 春の紫色の花|シラネアオイ
- 春の紫色の花|ライラック
- 春の紫色の花|ハーデンベルギア
- 春の紫色の花|藤(フジ)
春の紫色の花|スミレ

- 植物名:スミレ(菫)
- 科名:スミレ科
- 分類:多年草
- 花期:3~5月
女性の名前にも使われる「スミレ(菫)」。名前だけでも可憐な響きのスミレ(菫)の花は、古今東西人気の衰えることのない花です。スミレ色という色の名前はこの可憐な紫色の花から付けられた名前です。
直径2~3㎝の小さな紫色や薄紫色の花にそうっと顔を近づけると、ほのかに芳香がするのもスミレ(菫)の魅力の一つです。
▼可憐なスミレの不思議な仕組みや魅力はこちらをごらんください。
▼スミレ(菫)の詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|パンジー、ビオラ

- 植物名:パンジー、ビオラ
- 科名:スミレ科
- 分類:一年草
- 花期:10~4月
パンジー、ビオラは秋から春まで咲き続ける一年草。花の少ない季節に庭先を明るく彩ってくれる、冬の庭の強い味方です。
濃い紫色から薄紫色、ブルーがかった紫色など、パンジー、ビオラは様々な紫色の花を咲かせます。紫色の他に白やピンク、黄色、複色、何とも言えないアンティークカラーの花や、フリルのような花びらの品種まであるのですから、パンジー、ビオラだけで庭をいっぱいにしたくなるくらいです。
庭に植えて楽しむ他、切り花としても人気があります。
▼パンジーの詳しい育て方はこちら
▼ビオラの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|スイートピー(宿根スイートピー)

- 植物名:スイートピー
- 科名:マメ科
- 分類:一年草、多年草
- 花期:4~6月
春を代表する花の一つ、スイートピー。スイートピーにも紫色の花を咲かせる品種があります。ラベンダーのような青味がかった紫色から夜を思わせるような暗く濃い紫色まで。紫色のスイートピーにもたくさんの種類があります。薄紫色の花を咲かせる宿根スイートピーも人気があります。
スイートピーは、すっとした茎に連なるように香りのよい花を咲かせます。スイートピーだけを両手いっぱいに抱え込みたくなるような、花の中に顔をうずめたくなるような、そんな幸せな気持ちにしてくれる花です。
▼スイートピーの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|アネモネ

- 植物名:アネモネ
- 科名:キンポウゲ科
- 分類:多年草
- 花期:2~5月
アネモネは春に咲く球根花です。紫の他に白やピンク、赤など、色数も豊富。大きな花芯の周りに放射状に花びらを広げます。
アネモネという花の名前はギリシャ神話に登場する少女に由来します。西風の神ゼピュロスに見初められたアネモネという少女に、ゼピュロスの妻が嫉妬をして彼女を花に変えてしまったと言われています。
アネモネの花びらは蝋細工のような独特の材質感をしています。散り際には透けるように色褪せていく様子も美しい花です。アネモネの花が咲いたら、花びらが散っていく最後の姿まで楽しみましょう。
▼アネモネの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|ルピナス

- 植物名:ルピナス(ノボリフジ)
- 科名:マメ科
- 分類:一、二年草
- 花期:4~6月
小さな豆の花をキュッと集めたように咲く姿が可愛らしい、ルピナスの花。春から初夏にかけて開花します。藤の花を逆さにしたような花のフォルムから、「ノボリフジ」という和名もあります。
ルピナスの中にもいろんな種類があり、草丈1mくらいのものから、30~40㎝程度のルピナス・ピクシーデライトまで様々です。ルピナス・ピクシーデライトは花が小さく可愛らしいので、ガーデニングの他に切り花としても人気があります。
▼ルピナス・ピクシーデライトの育て方について詳しくはこちら
▼ルピナスの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|ムスカリ

- 植物名:ムスカリ
- 科名:キジカクシ科
- 分類:多年草
- 花期:3~5月
ブドウを逆さにしたような小さな紫色の花が可愛いムスカリ。ムスカリの花は初春、梅が咲くころから咲き始めます。顔を近づけるとふわりと甘い香りがするのも特徴です。紫色の花のほかに白やピンクの花を咲かせる種類もあります。
ムスカリは地植えにすると、分球してよく増える球根植物です。草丈は10㎝程度と小さく派手な花ではありませんが、群生している姿は見ごたえがあります。ムスカリの球根は鉢植えでも鉢のなかでどんどん分球して増えていくので、数年に1度は植え替えるようにしましょう。
▼ムスカリの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|ヒヤシンス

- 植物名:ヒヤシンス
- 科名:ユリ科
- 分類:多年草
- 花期:3~4月
春を代表する球根花の一つ、ヒヤシンス。子供の頃に水耕栽培でヒヤシンスを育てたことがある方も多いのではないでしょうか。ヒヤシンスは香りがよいことでも有名です。庭植えでも水耕栽培でもよく育ちます。
ヒヤシンスは色の種類が豊富な花です。紫色のヒヤシンスだけでも、群青のような濃い紫から赤紫、ピンクに近い紫、淡い紫色など何色もあります。
切り花でも多く流通しています。お部屋の中にヒヤシンスを飾って、香りまで満喫しませんか。
▼切り花のヒヤシンスを飾って長く楽しむコツはこちら
▼ヒヤシンスの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|チューリップ

- 植物名:チューリップ
- 科名:ユリ科
- 分類:多年草
- 花期:3~5月
「春と言えばチューリップ!」というくらい春には欠かせない花、チューリップ。フルーツキャンディのようなポップなカラーバリエーションが魅力です。そんな可愛らしいチューリップにも紫色の花を咲かせる種類があります。淡い紫色や黒のような濃い紫色など、紫色だけでも何種類かがあります。
紫色のチューリップはお庭でも花束やアレンジメントでも全体の雰囲気をぐっと引き締めるような役割をしてくれます。
▼チューリップの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|スカビオサ

- 植物名:スカビオサ(マツムシソウ)
- 科名:マツムシソウ科
- 分類:多年草
- 花期:3~5月、四季咲き
春に薄紫色の可愛らしい花を咲かせるスカビオサは、切り花でも庭植えでも人気の花です。淡い紫色の直径3~4㎝くらいの花を咲かせます。
湿気や蒸れに弱いので、庭植えにするなら風通しの良い場所が向いています。桜が終わって梅雨に入る前くらいまで優しい紫色の花をゆらゆらと風にそよがせるように咲き続けます。
切り花のスカビオサも人気で、ほぼ通年流通しています。切り花のスカビオサは野花のような可憐な雰囲気があり、ブーケやアレンジメントに入れると、全体の雰囲気を繊細で優しくしてくれます。
▼スカビオサの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|クレマチス

- 植物名:クレマチス
- 科名:キンポウゲ科
- 分類:多年草
- 花期:3~5月、9~10月、四季咲き
クレマチスは春に美しい紫色の花を咲かせます。クレマチスには木立性といってつるにならない種類もありますが、多くはつる性です。春、庭先のフェンスやトレリスに大きく絡みつきたわわに花を咲かせるクレマチスの姿は、通りを行く人の足を止めるほどに見事です。
クレマチスには何百種という品種があり、大輪の花を咲かせるもの、小さなベル型の花を咲かせるものなどがあります。
クレマチスは切り花で楽しむこともできます。アレンジメントやブーケではそのつるを活かして大きく絡ませるように使用すると、大人っぽい雰囲気を演出できます。
▼クレマチスの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|ラベンダー

- 植物名:ラベンダー
- 科名:シソ科
- 分類:多年草
- 花期:5~7月
ラベンダーは甘い香りが有名なハーブです。ラベンダー色という色の名前があるように、青味がかった薄紫色の花を咲かせます。
ラベンダーはすっと伸びた細い茎の先に穂のように小花を集合させて咲かせます。庭植えにすると茂みのように大きくなるので、存在感があります。
ラベンダーにはイングリッシュラベンダーとフレンチラベンダーがあり、芳香で有名なのはイングリッシュラベンダーです。
▼ラベンダーの楽しみ方はこちら
▼ラベンダーの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|イカリソウ

- 植物名:イカリソウ
- 科名:メギ科
- 分類:多年草
- 花期:4~5月
イカリソウは日本の山野にひっそりと自生している山野草です。春に白やピンク、紫色の特徴的なフォルムの花を咲かせます。その独特な花の形を船の錨に見立ててイカリソウと名付けられたと言われています。
イカリソウは直射日光が苦手で、落葉樹の足元や、明るい森の中などに自生しています。鉢植えや切り花でも流通しています。
▼イカリソウの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|シラネアオイ

- 植物名:シラネアオイ(白根葵)
- 科名:キンポウゲ科
- 分類:多年草
- 花期:4~5月
シラネアオイが咲くのは春、直射日光が当たらないような山野の中です。青味がかった薄紫色の花びらを大きく広げるように咲きます。クリスマスローズと同じキンポウゲ科に属すように、シラネアオイの花はクリスマスローズの花に少し似ています。
夏の暑さに弱く、主に関東以東の寒冷地を好みます。自宅でシラネアオイ育てるのなら、風通しと湿気に注意が必要です。
▼シラネアオイの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|ライラック

- 植物名:ライラック
- 科名:モクセイ科
- 分類:落葉小高木
- 花期:4~6月
紫色の小花が可愛いライラックは、切り花でも庭木でも人気の花です。ライラックの花はソメイヨシノが咲くころに咲き始めます。ライラックは、花びらが4枚の小花を枝の先に集合させるようにたわわに咲かせます。
ライラックにはかすかに芳香があり、花も香りも楽しめるのも特徴です。
▼ライラックの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|ハーデンベルギア

- 植物名:ハーデンベルギア
- 科名:マメ科
- 分類:常緑つる性植物
- 花期:3~5月
ハーデンベルギアは春に鮮やかな紫色の花を咲かせるつる植物です。「花は知ってるけど名前がわからない」という方も多いかもしれません。関東より暖冬な地域であれば常緑です。庭植えにすると年々大きくなります。
艶のある濃いグリーンのと春に咲く鮮やかな紫色の花のコントラストが美しい植物です。
▼ハーデンベルギアの詳しい育て方はこちら
春の紫色の花|藤(フジ)

- 植物名:藤(フジ)
- 科名:マメ科
- 分類:落葉つる性木本
- 花期:4~5月
藤(フジ)は日本の春を代表するマメ科のつる植物です。春、ソメイヨシノが終わった頃に薄紫色の花を下げるように咲かせます。花にはわずかな芳香があるので、藤棚の下にいると優しい香りを楽しめます。
「藤色」の語源はこの藤(フジ)の淡い紫色の花からきています。歌舞伎や日本舞踊で有名な「藤娘」もこの藤(フジ)が由来です。庭園や公園などにも藤棚があるように、藤(フジ)は古来より愛されてきた春の象徴のような花です。
▼藤(フジ)の詳しい育て方はこちら
▼編集部のおすすめ