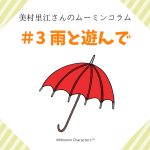春の花20選|春に咲く草花、樹木、球根の花
更新
公開

春は花咲き乱れる季節。今まで気にならなかった花が気になったり、名前を知りたくなったりしませんか。春に咲く花を草花、木に咲く花、球根植物まで、ずらりとご紹介します。
目次
春の花|草花7選
1.菜の花(ナノハナ)

3月頃に黄色い花を咲かせる菜の花。耐寒性が強く、空き地などでも育っているほどの強さ。一面の菜の花畑は、黄色い花が春の訪れを感じさせてくれます。
アブラナ科の黄色い花を一般的に菜の花といいますが、菜の花と呼ばれるもののなかには観賞用、菜種油の原料となるナタネ、食用の菜花などがあり、品種がそれぞれ異なります。
野菜として使用する場合は、開花する前のつぼみの状態で収穫するほうが苦味が少なく、柔らかいため美味しく食べることができます。採り遅れて花が咲いてしまっても、黄色い菜の花は観賞用としても十分楽しむことができます。
2.ネモフィラ

ネモフィラは、鮮やかな青色の花、可憐な斑点の黒花、水玉模様の白花など、愛らしい花が特徴の春に咲く一年草です。乾燥や寒さに強いことから、初心者向けの丈夫な花でもあります。切れ込みの入った葉っぱがこんもりと生い茂る姿は、花に負けず劣らず魅力的です。プランター、ハンギング、露地への直まきなど多様な条件で栽培でき、横に広がる性質を持つためグランドカバーとしても人気があります。
最近、国営ひたち海浜公園をはじめとした公共施設などの広いスペースに植栽されて有名になったことから、ご存知の方も多い草花ではないでしょうか。ネモフィラは種まきや移植など、育て方のポイントを知れば、初心者でも簡単に育てることができる草花です。
ネモフィラといえば青い花のイメージがありますが、白と黒のシックな色合いの品種も出回っています。
3.ポピー

ポピー(学名Papaver)は、野生種をはじめ、たくさんの園芸種がある草花です。種類によって、一年草と多年草のものがあります。園芸植物としてのほか、春の切り花としても親しまれています。種類によって開花時期も違い、切り花として流通しているアイスランドポピーは3月~4月、ヒナゲシの別名があるシャーレーポピーは初夏が開花時期です。
赤、オレンジ、黄色、白……華やかで元気な雰囲気に対して、花びらは薄紙のような繊細さがあり、春から初夏にはメディアでもポピーの花畑が度々紹介されています。
カリフォルニアポピーという名前で呼ばれる花菱草は、分類的にはポピーとは別種です。
4.芝桜(シバザクラ)

芝桜(シバザクラ)はハナシノブ科の匍匐性の常緑多年草。草丈は5~15cm程度と低く、地面を這うように横へ横へと伸びていき、うまくいけば直径50cm程まで生長します。花壇の縁に植えるとこぼれるように咲き広がる姿が見事です。
芝桜(シバザクラ)は日当たりさえ良ければどんどん花を咲かせてくれる、とても育てやすい植物。ガーデニング初心者さんにもおすすめです。
名前の由来は、桜を思わせるような花と芝のように地面に広がることから。名前の通り芝桜(シバザクラ)の花は、白やピンク、花びらは5枚と、なるほど桜のようです。
5.ルピナス

ルピナスは、秋に種をまき、翌年または翌々年の春に花を楽しむ一、二年草です。花の色は赤、ピンク、オレンジ、黄、青、白など様々。冷涼で乾燥した気候を好むので、蒸し暑い日本ではほんとんどが一年草になります。冷涼な北海道ではルピナスの群生が観光名所となっている街もあります。品種によっては1m以上に育つこともあり、空に向かって長い花穂に鈴なりの花をつけます。フジに似た花が上向きにつくことから、「ノボリフジ」「サカサフジ」の別名もあります。また、葉の形がうちわに似ているので「ハウチワマメ(葉団扇豆)」と呼ばれることも。マメ科の植物なので、花の後は枝豆によく似たさやが育ちます。
6.オオアラセイトウ(ムラサキハナナ)

紫色の小さな花を咲かせ、風に吹かれて揺れる姿が美しい植物です。「ムラサキハナナ」「ハナダイコン」「ショカツサイ」などいろいろな名前で呼ばれます。花色には多少の濃淡があります。
7.ワスレナグサ(勿忘草・忘れな草)

ワスレナグサはムラサキ科の一年草、こぼれ種でどんどん増える強い植物です。原産地では多年草として分類されますが、暑さと過湿を嫌うので夏越しできないことから、日本では一年草として分類されています。
ひとつひとつの花は米粒サイズの小さな花ですが、4月~6月、無数にブルーの小花が開花している光景はとても素敵です。最近は、ブルーの他、ピンクや白もあります。また、花丈も高性のものが出てきて、切り花としても出回りがあります。
1株で植えてもかわいらしいワスレナグサですが、まとめて植栽すると開花時は地面一面がブルーの花畑になり、見事な光景になります。
春に咲く樹木5選
8.ミモザ

「ミモザ」はギンヨウアカシアやフサアカシアなど、黄色い房状の花を咲かせるマメ科アカシア属の総称です。本来の「ミモザ(mimosa)」はオジギソウの学名ですが、黄色の房状の花が咲くアカシアの仲間の呼び名として使われています。日本で一番多く見かけるのが、シルバーグリーンの細かな葉のギンヨウアカシアです。ガーデニングのほか、切り花としても人気で、春の花屋さんではミモザの枝ものをよく見かけます。
9.マグノリア

マグノリアとは、モクレン属の総称です。種類によって春に咲くものと初夏~夏が開花時期のものがあります。
春に咲くマグノリアは、コブシ、シデコブシ、ハクモクレン、モクレンなどがあります。いずれも桜より大輪のため、満開時はとても華やかです。香りが良いのも特徴のひとつです。
10.桃(モモ)

バラ科サクラ属の落葉中高木で観賞樹として花が改良されたモモがハナモモです。渡来は古く弥生時代といわれています。中国では禍を避け福を招く縁起の良い木と考えられています。日本で観賞花木として栽培されるようになったのは江戸時代で、現在栽培される園芸品種の多くも江戸時代に作出されました。樹形には立性、枝垂れ、ほうき立ちがあり、場所に適した品種を選ぶことができます。実の成るモモよりも花が美しく、花期が梅と桜の間で、桃の節句のころには切り花としても流通しています。
11.桜(サクラ)

桜はバラ科サクラ属の総称です。
日本の春の花代表である桜は種類が多く、自生している種類だけでも15種類位あります。園芸用に品種改良された桜は300品種以上もあります。一般家庭の庭、公共施設の公園、街路にも植えられている樹木です。早咲き種は2月くらいから、それに続くように3月から4月にかけて多くの種類が次々と咲き続けます。
花色は白から薄桃色、濃い桃色、薄黄色まであります。咲きかたも一重のものから八重咲まで多様です。さくらんぼが実るセイヨウミザクラも桜の一種です。
春のお花見シーズンに華やかに咲くのはソメイヨシノという品種です。このソメイヨシノは若木でも花を咲かせる特徴があり、戦後日本中に植えられ、今では桜の代名詞のようになっています。
12.ハナミズキ

桜(ソメイヨシノ)が開花し終わったころに花を咲かせるハナミズキ(花水木)。北米原産でアメリカを代表する花のひとつで、春から初夏に白やピンクの美しい花を咲かせ、別名「アメリカヤマボウシ」と呼ばれています。花の見ごろは4月から5月にかけてです。全国各地に分布し、極端に冬の気温が低い寒冷地以外なら栽培可能です。寿命は桜と同じく80年程度と言われています。
私たちが花と思って白い4枚の部分は花弁ではなく、葉が変形した総苞(そうほう)です。実際の花弁は総苞よりも中央にあります。
春の花|球根の花8選
13.チューリップ

チューリップは春に花咲く球根植物です。チューリップの球根は直径3cmほどのものが多く、玉ねぎのような形をしています。球根の先はとがっていて、その先端から花茎や葉を伸ばします。花茎の背丈は種類にもよりますが、15cmよりも下のものはありません。おおよそ15cm~60cmのものまでが主に出回っています。花びらの色は皆さんもよくご存知の様に赤、白、黄色をはじめ、ピンク、紫、複色などさまざま。咲き方も、ユリ咲き、パーロット咲き、フリンジ咲き、八重咲きなどいろいろな咲き方があります。チューリップの開花時期は、大きく分けると、早咲き、普通咲き、遅咲きの3時期があります。同じチューリップでも開花の時期がかなり違うので、違う開花時期のものを一緒に寄せ植えすると、開花時期がずれてしまい見栄えが悪いので、鉢植えに植える場合は単一種を植え付ける方が一般的です。
14.ヒヤシンス

球根には最初から咲く色が少し出ています。大きな球根からまっすぐに長く伸びた茎と広がる葉、一つ一つの花はあまり大きくありませんが茎に集合して咲くのでブーケのように見えます。花が咲いたら茎を切って分球することで翌年も同じように大きな花を咲かせます。水栽培ではビンに深く伸びた白い根も観賞用として楽しむことができます。甘い香りが特徴でハチが好みます。シュウ酸が含まれているので素手で触ると痛痒くなる人もいます。水栽培の場合は小さな花が咲きます。水栽培の場合はすべての養分を使い果たすので翌年に咲くことはありません。
15.アネモネ

アネモネは分枝性の塊茎をもち、草丈25~40cmになるキンポウゲ科の多年草で、直立して直径10cm前後の花を咲かせます。和名はボタンイチゲ(牡丹一華)やハナイチゲ(花一華)といいます。まだ花の少ない2月下旬ごろから5月頃までと開花期が長く、赤、白、ピンク、紫や青など豊富な花色や一重だけでなく半八重や八重など花形の異なる多くの品種があり切り花や花壇で広く栽培されています。アネモネは花びらに見える部分はがく片です。性質は日当たりを好み、寒さに当てないと花芽が出来ない性質があるのでの冬も屋外で育てましょう。
アネモネの品種は、100品種以上あり、毎年のように新しい品種ができています。以前は、発色のよい色が中心でしたが、最近はパステル系の複色系の品種もあり、花のサイズも大輪のものから小輪のものまで豊富に揃います。園芸用以外に、切り花としても春を代表する球根花です。
16.スイセン(水仙)

春の球根の花の中では、開花が早い球根です。草丈は20cm~40cmで白と黄色以外にピンクや緑、オレンジ、など色とりどりの花が咲きます。最近は、八重咲種など、咲き方にも色々な特徴のある品種がでてきました。数年間は植えっぱなしで管理できて、環境が合えば球根がどんどん増え、年々花が見事になるので、群生すると見事です。
17.スズラン(鈴蘭)

漢字で書くと「鈴蘭」ですが、蘭の属性ではありません。自生するものでは、中部地方より北側の涼しい高原によく生えています。葉は細く長く、緑色で幅5cm前後、真っ直ぐ伸びる茎に添えられるように2~3枚生えてきます。葉の長さは10cmほどですが、茎はその倍20cmほどに生長します。そして、花茎から10個ほどの花を咲かせるのです。花の形はその名前の由来にもなった鈴に似た形をして、下向きに咲きます。スズランの花は真っ白で直径は1cmに見たない程小ぶりで、素朴なその姿が多くの人に愛されています。
18.ムスカリ

ムスカリは草丈15cmくらいで葡萄のような花を咲ます。とても耐寒性の強い花で、こぼれ種や自然分球で増え、毎年自然に花が咲きます。 小さな花ながら、花壇に群生させたムスカリが一斉に咲きそろった光景は見事です。チューリップなどの同じ時期に咲く球根花との色のコントラストも美しく、チューリップの脇役としても使われます。一度植えると、数年は植えっぱなしでも大丈夫なので、管理が楽な球根花です。
19.ラナンキュラス

ラナンキュラスは冬から春にかけて開花の多年草の球根植物です。秋に植えて開花時期は、3月~4月で、高温期は休眠します。ラナンキュラスの名前は、葉っぱが「カエルの足」に似ていること、また湿地帯に生息することから、ラテン語の「rana (カエル)」 から来ています。原種のラナンキュラスは5弁の黄色い花を咲かせます。その姿から、バターカップ(Buttercup)とも呼ばれています。最近は品種改良が進み、咲き方、色数がとても豊富。薄紙のように繊細な花びらが幾重にも重なった花姿が、光と温度に反応して開く姿がとても魅力的で園芸品種、生花品種とも、毎年新品種が創り出され、とても人気のある花です。ラナンキュラスは球根で植え付ける他、1月~3月に苗物としてもたくさんの品種が出回っています。
20.ハナニラ

桜の咲くころに、無数の星型の花が開花します。「ハナニラ」という名前の通り、葉っぱと球根をこするとニラの香りがしますが、葉をちぎったり、カットしたりしない限りは匂わないので、特に気になりません。ハナニラは秋植え球根で、9月~10月に植えて翌春から開花します。球根は植えっぱなしで大丈夫なので、庭や花壇などの地植えにした場合は、球根を植え付ければ、その後の管理は不要と言ってもよいくらいです。
ハナニラは光に反応する性質なので、夜や曇り、雨の日は花を閉じます。太陽に向かって花を咲かせるので、朝は東を向いて、午後は真上、夜は西を向きます。動きのある花です。
▼素敵な花言葉一覧
▼366日誕生花一覧
▼編集部のおすすめ