夏野菜一覧|特徴、定番から珍しい種類、食べ方やレシピまで
更新
公開

夏野菜の種類をわかりやすい一覧にしました。定番のものから珍しい種類、和の夏野菜まで、さらにおいしい食べ方や簡単レシピも紹介します。
目次
夏野菜とは?特徴

夏野菜とは、夏に旬を迎える野菜のこと。旬とは野菜や果物、魚介などの食べ物の味が最もおいしく、流通も盛んになる時期のことです。
スーパーマーケットなどで通年流通しているような野菜にも、それぞれ旬の時期というものがあります。旬の食べ物は味や香りが濃く、味覚で季節を感じさせてくれます。
夏野菜の特徴

夏野菜の色
夏野菜の魅力は何と言ってもその色です。夏の太陽をいっぱいに浴びて生長した夏野菜たちは、どれも色鮮やか。見ているだけで食欲をそそります。
夏野菜の味
夏野菜は水分を多く含んでいるものが多く、瑞々しいのが特徴です。また、夏の強い陽射しを浴びて光合成をしっかり行っているので、糖度が高く味が濃いのも特徴。さらに、生で食べられる種類が多いのも夏野菜の魅力です。
夏野菜の栄養
色鮮やかな夏野菜は、カロテンやビタミン類がたくさん含まれています。カリウムなどのミネラルも豊富で、むくみ改善や体を冷やす効果も。夏バテ予防に良いと言われているもの納得です。
夏野菜の定番10種
家庭菜園で育てられる夏野菜6種
キュウリ
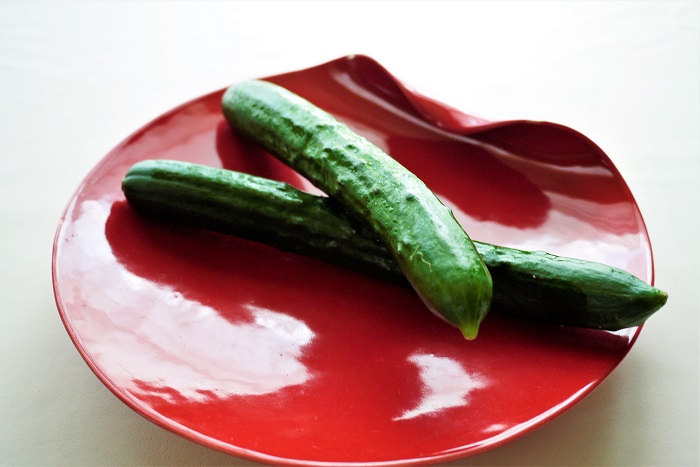
キュウリはウリ科の一年草。瑞々しく、シャリシャリとした歯ごたえが魅力の野菜です。
パプリカ
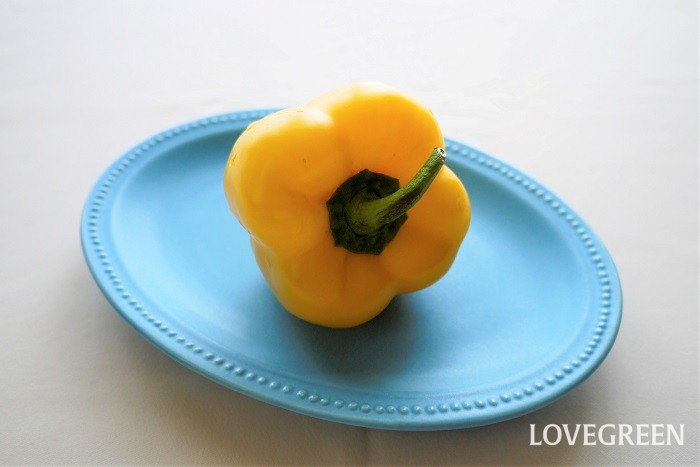
パプリカはナス科の夏野菜。ピーマンの仲間になります。肉厚で味が濃く、生でも加熱しても食べられます。
ナス

ナスはナス科の野菜です。一年中出回っていますが旬は夏の野菜です。油と相性が良く、揚げたり炒めたりする調理方法が人気です。
オクラ

オクラはアオイ科の夏野菜です。独特の粘りがあります。オクラの花は昼には閉じてしまう一日花です。オクラの花の可愛らしさまで楽しんでください。
ズッキーニ

ズッキーニはウリ科の夏野菜です。焼いたり、揚げたり、煮込んだりして食べますが、実は生でサラダにしてもおいしい野菜です。
トウモロコシ(ヤングコーン)

トウモロコシはイネ科の夏野菜です。旬のトウモロコシには甘く瑞々しいおいしさがあります。初夏にはトウモロコシの脇芽を欠いたものがヤングコーンとして出回ります。ヤングコーンは甘く柔らかく芯まで食べられます。
プランター栽培できる夏野菜4種
ミニトマト

ミニトマトは、トマトをぎゅっと小さくしたような野菜です。夏のミニトマトは甘みが濃く、生でも加熱してもおいしく食べられます。
ゴーヤ

グリーンカーテンでも有名なゴーヤは、ウリ科の夏野菜です。クセになる苦みがあるのが特徴です。
枝豆

枝豆は早い段階で収穫した大豆のことです。旬の枝豆は甘みが強く、ハッとするほど香りの高い野菜です。
バジル

バジルは、夏が旬の香りの良いハーブです。洋食のみならず、エスニック料理でも活躍する使い道の広さが魅力。生でも加熱しても食べられます。
珍しい夏野菜3種
アーティチョーク

アーティチョークはキク科のチョウセンアザミという花です。花が咲く前のつぼみの部分を食用にします。アーティチョークは蒸したり、揚げたりして食べます。
カラフルミニトマト

赤の他に黄色やオレンジ、スモーキーな紫色などの珍しい色のトマトです。
白いトウモロコシ
皮を剥くと中身が白いトウモロコシです。食べ方は通常のトウモロコシと変わりません。ちょっと見た目に変化を付けたいときに楽しい夏野菜です。
和の夏野菜2種

しそ(大葉)
しそは、大葉という名前でも親しまれているシソ科の野菜です。日本に古来から自生する野菜で、夏に盛んに生長します。香りが良く和ハーブとも呼ばれています。
ミョウガ
ミョウガは、ショウガ科の野菜です。しそと同様、薬味には欠かせない野菜として通年流通していますが、旬は夏です。ミョウガも和ハーブとして人気があります。
夏野菜のおいしい食べ方6選

ヒゲまでおいしいヤングコーン
▼ヤングコーンのレシピはこちら
しそは塩漬けにして保存できます
▼しその塩漬けレシピはこちら
ミニトマトのジャムはもう果物のようなおいしさ
▼ミニトマトのジャムのレシピはこちら
夏に食べたいトマトとニンニク、バジルのサラダ
▼トマトとニンニク、バジルのサラダのレシピはこちら
夏野菜の代表きゅうりの簡単レシピ集
▼きゅうりの簡単レシピはこちら
バジルの香りをとことん楽しむバジルソース
▼ジェノベーゼソースの作り方はこちら
ミニトマト大量消費におすすめのトマトソース
▼トマトソースの作り方はこちら
簡単でおしゃれな夏野菜レシピ3選
キュウリとミントのサラダ

爽やかな香りのサラダ。きれいなグリーンが目にも涼やかです。
材料
- キュウリ1本
- ミント2~3枚
- 塩一つまみ
- オリーブオイル少々
- レモン汁少々
作り方
1. キュウリは縦半分にし、3~5mmくらいに斜めにスライス
2. キュウリに塩を振り、オリーブオイルとレモン汁で和える
3. ちぎったミントを加えて軽く混ぜ合わせたら出来上がり
ズッキーニ、オクラ、枝豆のチーズ和え

ワインが止まらなくなるクセになる味。もちろん前菜にもおすすめです。チーズの塩分で十分なので塩は使いません。物足りないと感じたら足してください。
材料
- ズッキーニ1本
- オクラ10本くらい
- 枝豆好きなだけ
- オリーブオイル適宜
- チーズ(ペコリーノ・ロマーノあるいはパルミジャーノ・レッジャーノ)50gくらい
作り方
1. チーズはすり下ろしておく
2. ズッキーニは5mm程度のスライス
3. オクラはヘタを取って、縦半分にカット
4. 枝豆は塩を一つまみいれた熱湯で色よく茹でザルに上げ、サヤから豆を出しておく
5. ズッキーニとオクラを油を引かずに焼き目をつけるように焼く
6. ズッキーニ、オクラ、枝豆をお皿に盛り付け、オリーブオイルを回しかける
7. 上からチーズをたっぷりとかけて出来上がり
カラフルミニトマトのオイル煮

ミニトマトだけ。お肉もブイヨンも使ってないのに、びっくりするほど味の濃い一皿です。パスタに和えてもおいしくいただけます(その際は少し塩分を強くしてください)
材料
- カラフルミニトマト(ミニトマトでも可)食べたいだけ
- ニンニク1~2片
- 鷹の爪1本
- 塩少々
- オリーブオイル適宜
作り方
1. ミニトマトを洗って水気を切っておく
2. ニンニクは芯を取ってスライス
3. 鷹の爪は種を取って輪切り
4. 小鍋にミニトマト、ニンニク、鷹の爪を入れ、オリーブオイルを回しかけ蓋をして弱火で煮込む(落し蓋のような物が望ましい。なければ上からアルミホイルで覆っても可)
5. 途中蓋を開けて、中のミニトマトにシワが寄り、水分が出てきていたら塩を少々振って、また蓋をする
6. 5分くらい経って、十分にミニトマトがしんなりしていたら出来上がり
夏野菜キーマカレーのレシピ
夏に食べたくなるカレー。夏野菜を使ったシンプルなキーマカレーのレシピです。野菜とひき肉からでる出汁でしっかりと味が付くので余計なブイヨンは要りません。夏野菜がいっぱい入ったカレーです。
材料
- 豚ひき肉300g
- おろしニンニク少々
- おろしショウガ少々
- 鷹の爪1本種を取って輪切り
- タマネギ1個みじん切り
- トマト1個ざく切り
- ナス1個3~5mmのスライス
- ピーマン2個みじん切り
- 好みのカレー粉(カレールウではなく)
- サラダオイル
- しょうゆ(好みで)
作り方
1. 最初にスライスしたナスを油で揚げておく
2. フライパンにサラダ油とニンニク、ショウガ、鷹の爪を入れ、香りを油に移すように弱火で焦げないように炒める
3. タマネギを加え、しんなりするまで炒める
4. ひき肉を加え、ほぐしながら炒める
5. ひき肉の色が変わったら、カレー粉を加えて炒め合わせる
6. トマトを加えて水分が飛ぶまで炒め合わせる(しょうゆを少々回しかけると味がなじむ)
7. 程よく水分が飛んだら火を止め、器に盛る
8. 最後に揚げナスとピーマンをトッピングして出来上がり
ナスをココナッツオイルで揚げると、より奥深い味が楽しめます。
夏野菜の育て方

植える時期
夏野菜を植える時期は春以降です。詳しい植え付け時期はそれぞれの野菜によりますが、寒さに弱い品種がほとんどです。庭への植え付けは気温が暖かくなってからにしましょう。
用土
夏野菜は水はけ、保水性共に良い用土に植え付けましょう。市販の野菜用培養土で問題なく育てられます。
水やり
夏野菜の水やりは、表土が乾いて白っぽくなったらたっぷりと与えます。
夏の水やりの注意点は早朝か夕方気温が下がってから行うようにします。日中の水やりは土の中で水分温度が上がり、根を傷める原因となります。
トマトのように水を吸い過ぎると実が割れてしまう野菜もあるので、水やりの頻度は育てている種類に合わせて調整してください。
病害虫対策
乾燥が続くとハダニが発生しやすくなります。また、水のやり過ぎは根腐れを起こす心配もあります。注意しましょう。また、夏はネキリムシやカメムシなどが発生しやすくなる季節です。こまめに苗を観察して見つけ次第捕殺してください。
日当たり
夏野菜をおいしくするのは何と言っても光合成。日当たりの良い場所で管理すること、それから水やりを忘れないようにすることが大切です。
夏野菜は生でも加熱調理してもおいしいものがたくさん。目にもきれいな夏野菜を上手に生活に取り入れて、夏を楽しみましょう。
▼編集部のおすすめ












































































