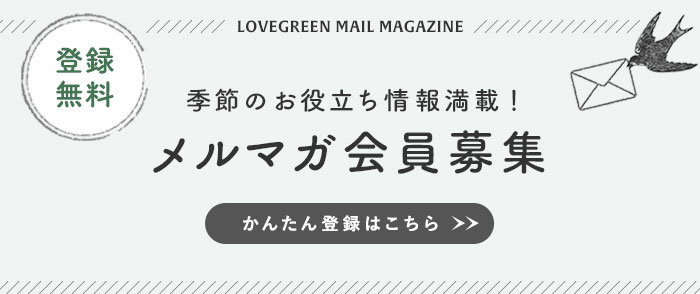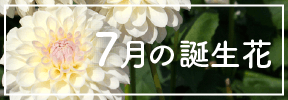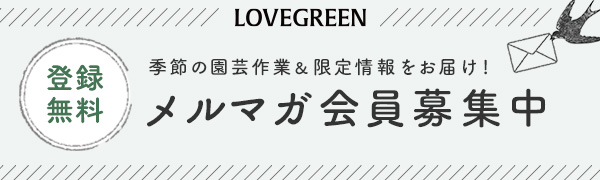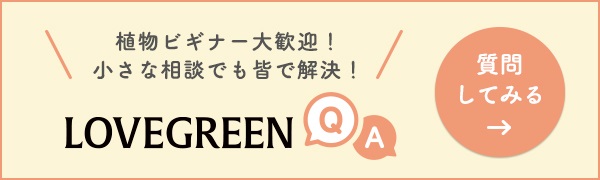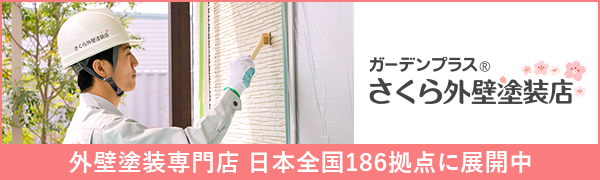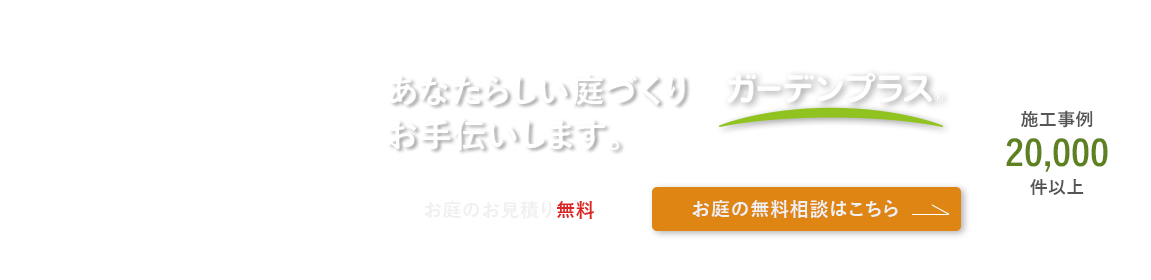黄色い花一覧。春夏秋冬の花の季節ごとに名前や特徴を紹介!
LOVEGREEN編集部
このライターの記事一覧

黄色い花を咲かせる植物の一覧です。春夏秋冬ごとに、草花と花木に分けて紹介します。
目次
春に咲く黄色い花

草花
オステオスペルマム
オステオスペルマムは、キク科の多年草。ディモルホセカとよく似ていますが、オステオスペルマムは多年草、ディモルホセカは一年草です。
花色は黄色の他、薄紫、ピンク、白、赤、オレンジ、アプリコット色、複色などがあります。
カウスリップ(プリムラ・べリス)
カウスリップ(プリムラ・べリス)は、ヨーロッパに自生する原種のプリムラの一種の耐寒性多年草。早春に石鹸のような優しい香りのする花がうつむきがちに咲き、ヨーロッパでは春の訪れを知らせる花のひとつです。
カタバミ
カタバミは、身近なところに自生するカタバミ科の多年草。ハート形の小葉が3枚まとまって付き、夜になると葉を閉じ、眠ったように見えるのが特徴です。
花色は黄色の他、白やピンクなどがあります。
ガーベラ
ガーベラは、キク科の一年草、または多年草。一輪でも絵になる大ぶりな花が人気です。
花色は黄色の他、赤、白、ピンク、オレンジ、紫、緑、複色などがあります。
キンセンカ(カレンデュラ)
キンセンカは、キク科の多年草。カレンデュラやポットマリーゴールドという別名もあります。
花色は黄色の他、黄、オレンジ、茶などがあります。
キンラン
キンランは、日本の本州から九州の山林に自生するラン科の多年草です。キンランの名前の由来は、黄色の花色を金色に見立てて付けられたものです。同じキンラン属にギンランという白花を咲かせる品種もあります。
クリサンセマム・ムルチコーレ
クリサンセマム・ムルチコーレは、キク科の一年草。冬に明るい黄色の花を咲かせます。
宿根ネメシア
宿根ネメシアは、ゴマノハグサ科の多年草。ネメシアには他に一年草もあります。
花色は黄色の他、白、紫、ピンク、複色などがあります。
スイカズラ
スイカズラは、スイカズラ科の多年草。香りの良い花を咲かせます。花には甘い蜜があるのも特徴。咲き始めは白、咲き進むにしたがって黄色へと変化していく様子から金銀花という別名もあります。
たんぽぽ
たんぽぽは、キク科の多年草。春に黄色の花を咲かせます。希少種で白花種もあります。
チューリップ
チューリップは、ユリ科の球根植物。春を代表するような花です。
花色は黄色の他、赤、白、ピンク、紫、アプリコット、黒、複色などがあります。
菜の花
菜の花は、アブラナ科の植物の花の総称。菜の花のつぼみは食用にもされます。
フリージア
フリージアは、アヤメ科の球根植物。香りの良い花を咲かせます。
花色は黄色の他、白、ピンク、紫、オレンジなどがあります。
ポテンティラ
ポテンティラは、バラ科の多年草。低くほふくするように伸びているのでグランドカバーとして人気です。
花色は黄色の他、白、オレンジ、ピンク、赤、アプリコットなどがあります。
ミヤコグサ
ミヤコグサは、マメ科の多年草。野原に這うように広がり、黄色い花を咲かせます。
ヤマブキソウ
ヤマブキソウは、落葉樹の株元などの明るめの森や林に自生するケシ科の宿根草。名前の由来は、落葉低木のヤマブキの花の色や形に似ていることからつきましたが、ヤマブキはバラ科の木、ヤマブキソウはケシ科の草なので、分類的には違う植物です。
ラナンキュラス
ラナンキュラスは、キンポウゲ科の球根植物。たっぷりとした花びらが特徴です。
花色は黄色の他、白、ピンク、赤、紫、オレンジ、アプリコット色、複色などがあります。
ラナンキュラス・ゴールドコイン
ラナンキュラス・ゴールドコインは、キンポウゲ科の宿根草。ハイキンポウゲの園芸品種です。4月~5月に小さな黄色い花が開花します。
リムナンテス
リムナンテスは、春から初夏に開花するリムナンテス科の一年草。ほふく性で広がるように生長し、春から初夏までたくさんの花が開花します。
黄色に白の縁取りの複色カラーが多く出回っていますが、黄色の単色や白などもあります。
ルピナス
ルピナスは、マメ科の多年草。高温多湿に弱いため日本では一年草として扱われていますが、厳密には多年草です。
花色は黄色の他、青、白、赤、ピンク、オレンジ、紫、複色などがあります。
花木
エニシダ
エニシダは、マメ科の落葉あるいは常緑低木。枝垂れた枝にたくさんの花を咲かせます。
花色は黄色の他、黄、白、複色などがあります。
キブシ
キブシは、キブシ科の落葉低木。ソメイヨシノの開花より少し早い時期に長さ5~10cmくらいのクリームイエローの房状の花が、枝からぶら下がるように開花する姿は印象的です。
キングサリ
キングサリは、マメ科の落葉高木。黄色い花を枝から下垂させて咲かせます。咲き方からキバナフジという別名もあります。
サンシュユ
サンシュユは、ミズキ科の落葉高木。春に咲く花木類の中では比較的開花が早い方です。背丈のある木の枝一面が黄色に染まり、開花時はとても華やかです。
カロライナジャスミン
カロライナジャスミンは、ゲルセミウム科の常緑つる植物。香りの良い花を咲かせます。ジャスミンと名につきますが、ジャスミンティーのジャスミンとは別種です。全草に毒があるので食用にはしないでください。
バラ
バラは、バラ科の落葉低木。花の女王という異名を持ち、香りの良い花を咲かせます。
花色は黄色の他、赤、ピンク、白、黄、オレンジ、紫などがあります。
ヒュウガミズキ
ヒュウガミズキは、マンサク科の落葉低木。淡い黄色の花を咲かせます。花も葉も樹形も美しく、庭木として人気です。
マンサク
マンサクは、マンサク科の落葉低木。春に黄色い変わったフォルムの花を咲かせます。
花色は黄色の他、赤、オレンジ、茶色などがあります。
ミツマタ
ミツマタは、ジンチョウゲ科の落葉低木。枝が必ず三つに分岐する特徴が名前の由来です。
花色は黄色の他、オレンジ、赤などがあります。
ミモザ
ミモザは、マメ科の常緑高木。細い枝の先にたわわに、金色の羽毛のような香りの良い花を咲かせます。
モッコウバラ
モッコウバラは、バラ科の常緑低木。カスタードクリームのような淡い黄色の花を咲かせます。
花色は黄色の他、白があります。
ヤマブキ
ヤマブキは、日本全国に自生しているバラ科の落葉低木。春から初夏にかけて明るい黄色の花を枝一面に咲かせます。山吹色の語源はこの花色からです。
レンギョウ
レンギョウは、モクセイ科の落葉低木。枝いっぱいに明るい黄色の花を咲かせます。
夏に咲く黄色い花

草花
エキナセア
エキナセアは、キク科の多年草。大ぶりな花が魅力です。
花色は黄色の他、赤、ピンク、オレンジ、グリーン、白、複色などがあります。
エルサレムセージ
エルサレムセージは、初夏から秋にかけて黄色い花を咲かせる常緑木立性の多年草。名前にセージとありますが、フロミス属のため、セージやサルビアとは別種の植物です。
エルムレス
エルムレスは、尻尾のような花姿が印象的なユリ科の球根植物。ロゼット状の葉から春にすらりとした穂状の花茎を立ち上げ、花穂の下から上に向かって小さな花が開花していきます。
花色は黄色の他、オレンジ、ピンク、アプリコット、白などがあります。
オクラ
オクラは、アオイ科の多年草。本来は多年草ですが、日本では一年草として扱われています。淡い黄色の花は一日花で、夕方には萎れてしまいます。
キュウリ
キュウリは、ウリ科の一年草。初夏から夏にかけて黄色い花を咲かせます。花には雌雄があります。
クラスペディア
クラスペディアは、キク科の一年草。丸いボールのような黄色い花を咲かせます。
グロリオサ
グロリオサは、イヌサフラン科の多年草。大きく個性的な花が印象的です。
花色は黄色の他、赤、オレンジ、ピンク、白、複色などがあります。
ゴーヤ
ゴーヤは、ウリ科の一年草。ニガウリ、ツルレイシという別名でも有名な野菜です。黄色い花を咲かせます。
ジニア
ジニアは、キク科の多年草。長期間花が咲き続けるので百日草という別名もあります。
花色は黄色の他、赤、白、ピンク、オレンジ、アプリコット、アンティークカラー、複色などがあります。
睡蓮(スイレン)
睡蓮は、スイレン科の多年草。花や葉を水面に出している水生植物です。
花色は黄色の他、白、赤、紫、ピンクなどがあります。
ダリア
ダリアは、キク科の多年草。華やかで印象的な花を咲かせます。
花色は黄色の他、赤、白、ピンク、オレンジ、アプリコット、紫、複色などがあります。
ナスタチウム
ナスタチウムは、ノウゼンハレン科の多年草。キンレンカという別名もあります。
花色は黄色の他、オレンジ、赤、アプリコットなどがあります。
蓮(ハス)
蓮は、ハス科の多年草。水生植物です。蓮の花は、朝開き、夕方には閉じるという特徴があります。
花色は黄色の他、白、ピンクなどがあります。
花オクラ(トロロアオイ)
花オクラ(トロロアオイ)は、アオイ科の半耐寒性多年草。オクラは実を食べる野菜ですが、花オクラ(トロロアオイ)は花を食べるエディブルフラワーで、実は食用には不向きです。
ヒペリカム
ヒペリカムは、オトギリソウ科の常緑低木。黄色で花びらが5枚の梅に似た花を咲かせます。
ヒマワリ
ヒマワリは、キク科の一年草。草丈高く、大ぶりな花が印象的です。
花色は黄色の他、オレンジ、白、濃赤、茶などがあります。
フェンネル
フェンネルは、セリ科の多年草。よく似たディルは一年草です。全草に甘い香りがあります。
ヘリクリサム
ヘリクリサムは、キク科の多年草。ヘリクリサム属にはたくさんの種類があります。
花色は黄色の他、赤、ピンク、オレンジ、白などがあります。
ポーチュラカ
ポーチュラカは、スベリヒユ科の多年草。耐寒性が弱いため、日本では一年草として扱われています。
花色は黄色の他、ピンク、赤、橙、黄、白などがあります。
マツヨイグサ
マツヨイグサは、アカバナ科の一年草。日が暮れてから開花するのが名前の由来です。
マリーゴールド
マリーゴールドは、キク科の一年草。花びらがたくさんの花を咲かせます。
花色は黄色の他、オレンジ、白、赤、複色などがあります。
メカルドニア
メカルドニアは初夏から秋に、小さな黄色い花をたくさん咲かせるゴマノハグサ科の草花。横に広がって生長する匍匐性の特徴を生かして、グランドカバーや寄せ植え、ハンギングバスケットなどに使われます。
メランポジウム
メランポジウムは、黄色の小花を初夏から秋まで休みなく次々と咲かせるキク科の一年草。高温多湿に強く、肥料の少ない場所でもよく育つので、夏に強い育てやすい花として人気があります。
ユリ
ユリは、ユリ科の球根植物。香りの良い大きな花を咲かせます。
花色は黄色の他、白、ピンク、オレンジ、赤、黒などがあります。
ルドベキア
ルドベキアは、キク科の一年草、または多年草。夏の間次々と花を咲かせます。
花色は黄色の他、茶、レンガ、アンティークカラー、グリーン、複色などがあります。
花木
ハイビスカス
ハイビスカスは、アオイ科の非耐寒性常緑低木。花は一日花で夕方には萎れてしまいます。
花色は黄色の他、赤、黄、白、ピンク、オレンジ、紫、複色などがあります。
ランタナ
ランタナは、クマツヅラ科の常緑低木。寒さに弱く、冬には葉を落とすこともあります。
花色は黄色の他、白、赤、ピンク、オレンジ、黄、複色などがあります。
秋に咲く黄色い花

草花
オミナエシ
オミナエシは、スイカズラ科の多年草。クセのある香りのする花を咲かせます。
キク
キクは、キク科の多年草。昔から日本で愛されてきた花で、多くの園芸品種があります。
花色は黄色の他、白、ピンク、オレンジ、赤、紫などがあります。
キバナコスモス
キバナコスモスは、キク科の多年草。コスモスより草丈が低く、開花時期もコスモスより早いのが特徴。
花色は黄色の他、オレンジ、黄、赤などがあります。
ケイトウ
ケイトウは、ヒユ科の一年草。鶏のトサカに見立てたのが名前の由来です。
花色は黄色の他、赤、オレンジ、ピンク、グリーンなどがあります。
コスモス
コスモスは、キク科の一年草。風に揺れるような優しい花が人気です。
花色は黄色の他、ピンク、白、赤、アプリコットカラー、複色などがあります。
セイタカアワダチソウ
セイタカアワダチソウは、キク科の多年草。名前の通り草丈が高く、大きなものになると3mを超すものもあります。
冬に咲く黄色い花

草花
シンビジウム
シンビジウムは、ラン科の常緑植物。半着生のランです。
花色は黄色の他、グリーン、白、ピンク、オレンジなどがあります。
スイセン
スイセンは、ヒガンバナ科の球根植物。冬から春にかけて香りの良い花を咲かせます。
花色は黄色の他、白、緑などがあります。
ツワブキ
ツワブキは、キク科の常緑多年草。フキに似た常緑の葉とキクに似た花が特徴です。
花色は黄色の他、白、クリーム色、オレンジなどがあります。
パンジー
パンジーは、スミレ科の一年草。秋から春まで咲き続けるので、冬の寂しくなった花壇の強い味方です。
花色は黄色の他、紫、白、ピンク、オレンジ、アプリコット、黒、茶、赤、複色などがあります。
ビオラ
ビオラは、スミレ科の一年草。パンジーより小さな花が特徴です。開花期が長いのも人気の理由です。
花色は黄色の他、紫、白、ピンク、オレンジ、アプリコット、黒、茶、赤、複色などがあります。
福寿草
福寿草は、キンポウゲ科の多年草。明るい黄色の花を咲かせます。縁起物としても好まれます。
ユリオプスデージー
ユリオプスデージーは、キク科の常緑低木。シルバーグリーンの葉が美しい花木です。明るい黄色の花を咲かせます。
花木
ロウバイ(蝋梅)
ロウバイは、ロウバイ科の落葉低木。花の中が赤みを帯びているものはロウバイ、中まで黄色のものがソシンロウバイです。
▼編集部のおすすめ
関連ワード
今月のおすすめコンテンツ
「黄色い花一覧。春夏秋冬の花の季節ごとに名前や特徴を紹介!」の記事をみんなにも教えてあげよう♪